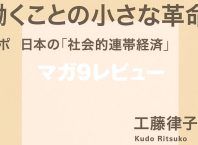第二次世界大戦後史上最悪の人道危機と言われるシリア内戦のリアルを伝える長編ドキュメンタリー。スクリーンに映し出されるあまりの惨状に息をのみ、言葉を失った。う〜ん、重いなあ。レビュー原稿を書くのはしんどいなあ、と萎えそうになったとき、パンフレットの表紙の、本作の監督にして主人公のワアド・アルカティーブの鋭い視線に射貫かれた。「あなたが今見たのは、この地球上で現在進行形で起こっていることなのよ」。彼女が命がけで撮ったこの現実を語ることは、この映画を見たものの、同時代に生きるものの使命だと思い直した。
作品の舞台となるシリア北部のアレッポは、首都ダマスカスを上回る人口を有するシリア最大の都市で、古くはシルクロードの要所でもあり、世界遺産にもなっていた美しい街だった。だが2011年に興ったアサド政権に対する民主化運動を機に、街はシリア政府軍と反体制派が軍事衝突を繰り返す戦場と化した。
2012年、ジャーナリストに憧れていたアレッポ大学の女子大生ワアドは、民衆のデモをスマホで撮影し始める。運動に共鳴し取材を続けるうち、空爆で傷ついた市民を献身的に治療する青年医師ハムザと出会う。二人は恋に落ち結婚、娘を授かる。赤ん坊は、自由と平和への願いを込めてアラビア語で「空」を意味するサマと名付けられる。「こんな明日をも知れない世の中にあなたを産んだことを許してくれる?」と、繰り返し娘に語りかけるワアドのナレーションで、戦火に生きる人々の物語は進む。ジャーナリストの冷徹な視点で描かれたドキュメンタリーではなく、母から娘へのつぶやきといった情愛あふれる語りが、この映画の真骨頂だろう。
サマの誕生後、アサド政権とロシアなど同盟国の空爆は激しさを増し、狙い定めたように医療施設を爆撃、ハムザらの病院はアレッポ最後の医療拠点となる。そこにはひっきりなしにけが人が運び込まれる。血まみれの子ども、息絶えた弟を呆然と見守る幼い兄、半狂乱の母親。ベッドも床も血まみれで、拭いても拭いても切りがない。「目をつぶっても視界が赤い」と、ワアド。
そんな凄惨な状況下でも、女たちは乏しい食材をやりくりして料理を作り、花一輪、柿の実ひとつに歓声を上げる。子どもたちは壊れたバスを遊び場にして屈託なく遊ぶ。男たちには、がれきの山を背に街頭チェスに興じるひとときもある。私たちと変わらない普通の人々の暮らし、喜怒哀楽がそこにある。
圧巻は瀕死の重傷を負った臨月間際の妊婦のおなかから、赤ん坊が帝王切開で取り出されるシーン。へその緒のついた赤ん坊は灰色のゴム人形のようで、全く動かない。医師は背中をたたいたりぶら下げてゆすったり、胸を押したり蘇生を試みる。あきらめない。生きて生まれても、明日には死んでしまうかもしれないのに……。隣の部屋ではバタバタと人が死んでいるというのに、たったひとりの命を全力で救おうとする。血まみれになって息絶える命と隣り合わせに、生まれる命がある。死が日常になっても、人は生きようとする。
主人公の娘サマの愛くるしさといったらない。戦場で生まれ、爆撃音を子守歌代わりに聞いて育つサマは、地下壕の中でも、にこにこして機嫌がいい。普通なら怖くて泣き叫ぶだろうに、それが平気になってしまっているという悲劇、そして人間のたくましさ。人間の残虐さ、愚かさを見せられれば見せられるほど、合わせ鏡のように命の強さ、尊さが際立つ。
試写を見たその日の夕刊に「シリアで空爆、23人死亡か」との記事があった。23人のなかには、サマのような子どももいただろうか。活字のみの記事の行間に、その日映画で出会った一人ひとりの顔が浮かんだ。
(田端 薫)
『娘は戦場で生まれた』
2020年2月29日(土)よりシアター・イメージフォーラム(東京)ほか全国順次公開
※公式サイト http://www.transformer.co.jp/m/forsama/