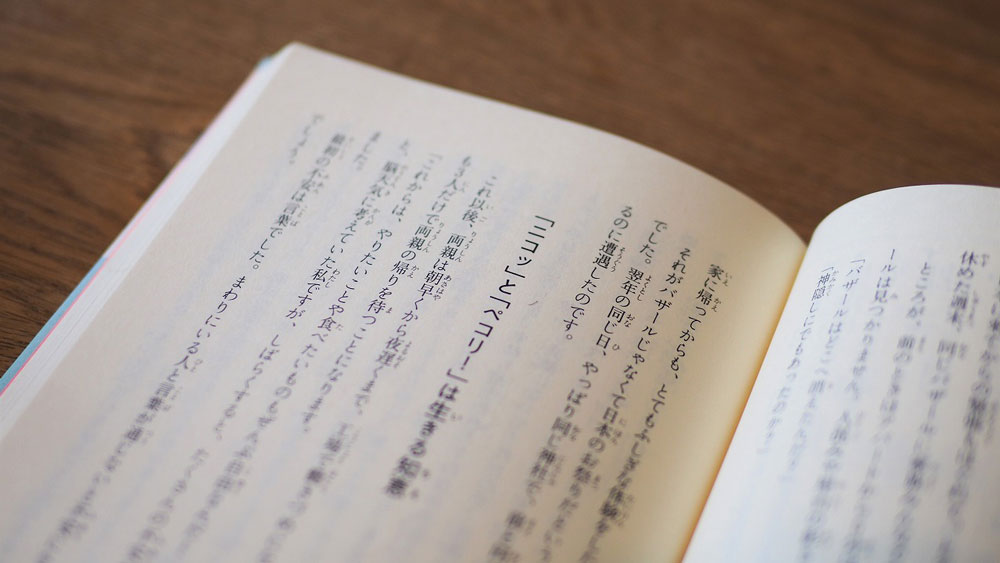1991年、戦争が終結したばかりのイランから「出稼ぎ」に来た両親に連れられて、弟2人とともに日本に来たナディさん。オーバーステイ(在留許可期間の超過滞在)のまま日本で育ち、高校在学中に在留特別許可を得て定住資格を獲得。現在は都内の企業で働きながら、2人のお子さんを育てています。昨年6月に『ふるさとって呼んでもいいですか 6歳で「移民」になった私の物語』(大月書店)を上梓したナディさんに、お話を伺いました。
「主張してはいけない」と思っていた
――子ども時代の体験を記録して本にすることを最初にすすめられたのは、ナディさんが高校3年生のときだったと聞きました。『ふるさとって呼んでもいいですか』を出版されたのは34歳のときですが、15年の間には、いろいろな心境の変化もあったそうですね。
ナディ この本には、4歳のときの記憶から現在までのことを書いています。子ども時代のことは起きた出来事をそのまま書けばよかったのですが、大学生くらいになるとアルバイト探しや就活で「外国人」に対してのハードルを感じたり、アイデンティティのことで悩んだり、社会に出るなかでいろいろな疑問がわいてきます。時間が経つほど、そういうことをどう書いたらいいのか、と分からなくなっていきました。
最初は「こういうことがありました」と書くだけで、「だから社会を変えていきたい」なんてことは書けなかったんですよ。自分はオーバーステイで日本に滞在して、在留特別許可をもらって「特別に日本にいさせてもらっている身」だから、自分から社会に何かを要求するのは厚かましいし、主張してはダメなんだと思っていました。でも、そんなときに、望月優大さんの『ふたつの日本 「移民国家」の建前と現実』(講談社現代新書)を読んだんです。
――著者の望月さんは、NPO法人難民支援協会のウェブマガジン『ニッポン複雑紀行』の編集長でもあります。『ふたつの日本』では、これまでに日本がどんな「移民政策」をとってきたのかを示しながら、すでに多くの在留外国人が日本に暮らしていることを指摘されています。
ナディ 1980年代から90年代には、私の両親のようにオーバーステイで働く外国人が日本に多くいました。その後、取り締まりが厳しくなり、日系ブラジル人や日系ペルー人など、日本の「血を引く」外国人に限った在留資格がつくられて、多くの日系人が日本に来ました。さらに「研修生」や「技能実習生」などの新しい在留資格ができ、いまは「留学生」という建前で働く例も増えています。そして、昨年は「特定技能」が新設されて在留資格の定義が大きく変えられました。そうやって外国人を受け入れる政策はシフトしていきましたが、どれも全部「労働」という点でつながっているんですよね。
たしかにオーバーステイの状態で日本に居続けたのは私たちですけど、望月さんの本を読んで、そういう状況が生まれた背景には日本の経済が外国人の「労働力」を必要としていたことがあったんだと気づきました。だから、当時はオーバーステイで働く外国人がいるのがわかっていても、いまほど厳しくは取り締まらず黙認しているところがあった。大きな背景を知ったことで、私たちだけが罪悪感をもって遠慮することはなくて、お互いにもっといい関係を築くためにも「ここを変えていったほうがいい」と言ってもいいんだと思えるようになったんです。
戦争の影響で、日本に「出稼ぎ」へ
――ナディさんが家族とイランから日本に来たのは、8年間続いたイラン・イラク戦争が終結して2年後のことでした。戦争が終わったときにナディさんは4歳でしたが、当時のことを覚えていますか。
ナディ すごく怖かったので、よく覚えています。私は小さい頃からおてんばだったみたいなのですが、空襲警報のサイレンが鳴り始めると一瞬で静かになって、弟と母のいるキッチンへ全力で走っていきました。そこから、おばあちゃんと一緒に家の地下室へと走りました。爆弾の標的になってしまうので、夜は電気をつけずにランプを使っていました。日本に来た最初の頃も、甲子園のサイレンを聞くと空襲かと思って……多分トラウマなんでしょうね。
思い出したくない記憶なので、父も母も戦争の話はほとんどしません。私の場合、戦争は4歳のときに終わったので、長期的にそういう状況下にある人たちには及びませんが、それでも一回でも戦争を経験したら二度と忘れることはできないと思います。
――ご両親はもともと裕福な家庭の出身だったそうですが、日本に働きに来ることになった理由には戦争の影響があったのでしょうか。
ナディ そうですね。戦争のあと、イランでは経済が安定しませんでした。食料や生活必需品は配給制でしたが、配給される物資だけでは子どものミルクなどが足りない家庭もあったんです。父は祖父の代からのお店を経営していましたが、ほかのお店は高い値段で売りつけるのに、父はその人が払える金額で売っていました。父は裕福な家庭で育ったこともあって、人を疑うことを知らないんです。困っている人がいれば助けるし、お金を必要としている人には渡す。でも、戦後の混乱期には、そこにつけこんでだます人もいたそうです。お店に泥棒が入ったこともありました。
結局、お店はつぶれて大きな借金ができて、日本に働きに来ることを決めました。日本に来てから知り合ったイランの人たちは父のことをすごく尊敬していて「これほどの善人に会ったことはない」って言います。でも、家族はそれで大変な目にも遭ってきたんですけどね……(笑)。
「迷惑をかけないように」と過ごした日々
――当時は、事前にビザを申請しなくても、イランから入国する際に短期の観光ビザが発行されました(※)。観光ビザでは働くことはできませんが、実際には工場などで雇われて、ビザが切れたあとも日本で働く人が多くいたわけですね。ほとんどが単身で、家族で来日するケースは少なかったと思うのですが、ナディさんはどのように生活されていたのでしょうか。
ナディ 仕事やアパートは、日本で働いていたことのある近所の夫婦がイランにいるときに手配してくれていました。でも、アパートに着いたら、そこに住むイラン人のおじさんたちが驚いて「どうして子どもなんて連れてきたんだ?」って部屋に集まってきたんです。家族で来ているのは、すごく珍しかったと思います。みんな出稼ぎで来ていてビザの期限が切れているので、子どもが目立ったら警察沙汰になって強制送還されるかもしれないとおびえていました。
アパートでの様子から自分たちが歓迎されていないことを感じて、私は迷惑をかけないようにしなくちゃと思っていました。日本でも学校に通えると思っていたけれど、どうやら無理そうだってことも分かりました。両親は朝から夜遅くまで工場で働きづめだったので、5歳と1歳の弟2人の面倒を見ながら家と公園の往復だけして、なるべく目立たないように過ごしていました。でも、外国人の子どもが3人でいて目立たないわけがないですよね(笑)。実は、地域で有名だったみたいです。
言葉が通じない不安をカバーするために、私たちが覚えたのが笑顔とおじぎでした。アパートの住人にも外で会う人にも、嫌われないように「ニコッ」と「ペコリ!」をしていたので悪い目立ち方ではなく、礼儀正しい子どもたちと思ってもらっていたようです。
※当時、イランと日本はビザ相互免除協定を結んでいたが、1992年4月にビザ免除措置は停止された
――まだ6歳なのに「周りから嫌われてはいけない」と考えて……
ナディ 仕方ないですよね。あとになって外国人支援を行っているNPO法人「ASIAN PEOPLE’S FRIENDSHIP SOCIETY(略称:APFS)」で出会った子どもたちが「自分たちはビザがないことを知らなかった」と言っているのを聞いたときには、「ああ、いいな」って思いました。知らずに生きていくことができたなら、そのほうが私もよかった。日本に来る前にこんな生活が始まるとわかっていたら、絶対「イヤだ」って言っていました。病院にも学校にも行けないし、まして周囲から嫌われている可能性があるから好かれるように振舞わないといけないし……。
でも、戦争もそうですけど、どんなに小さくて甘えたい年齢でも環境が許さないということもあります。戦時中に「おなかすいた」と騒いでも仕方ない。子どもは周りの空気をよく察するじゃないですか。近所の公園で友達になった日本の子どもたちを見て「いいな」と思うことがあっても、「うちは違うから」と弟たちにも言っていました。
日本の人たちが働きたがらない職場で
――日本語はどのように覚えたのですか。
ナディ イランに帰国する知り合いからテレビをもらったのでそれを見たり、公園で会う日本人の親子と話したりしながら、自然と日本語を覚えていきました。公園にいたお母さんたちは優しくて、自分の子どもたちと同じおやつを私たちの分も持って来てくれていました。みんなが優しい目で見ていてくれたから、大変でも非行に走るようなことがなかったのかもしれない。もし「なに、あの子たち?」みたいな目で見られていたら、こわくて家から出られなかっただろうし、そうしたら日本語も覚えなかっただろうと思います。
――その後、支援してくれる方と出会ったこともあり、ナディさんは来日して3年経ってから公立小学校に3年生として入学します。入学にあたって役所で外国人登録証明書をつくったそうですが、そのときに在留資格がないことは問題にならなかったのでしょうか。
ナディ あの頃は毎年「在留資格なし」のままで更新しても、ずっと収容されるようなことはありませんでした。いまとは全然違いますよね。ちょうど日系人の受け入れを拡大している時期だったのだと思いますが、働く日系人の数が揃うまではオーバーステイだとわかっていても黙認していたんじゃないでしょうか。
たしかに、日本にいたイラン人のなかには偽造テレホンカードなどの犯罪にかかわっていた人もいましたけど、きちんと働いていた人も多くいました。工場で雇う側にも、真面目な人たちだったら働いてほしいという雰囲気があったと思います。いまでこそ「ブラック企業」は社会的な問題になっていますが、当時から労働条件の厳しい職場はあって、日本の人は誰も働きたがらなかった。そういうところで働いていたのが私の両親とかだったのだと思います。
国にも、法律を整備して日本の人たちが働きやすい賃金や労働条件にするのではなく、外国から来た人たちが働けばいいという考えがあったんじゃないかなって思うんですよね。
(その2)につづきます
(構成・写真/マガジン9編集部)
ナディ 1984年イラン生まれ。91年に両親とともに家族で来日して、オーバーステイ(超過滞在)のまま首都圏郊外で育つ。小学3年から公立小学校に通い、高校在学中に家族とともに在留特別許可を得て定住資格を獲得。大学卒業後は都内の企業に勤務し、現在は2児の母でもある。著書に『ふるさとって呼んでもいいですか 6歳で「移民」になった私の物語』(大月書店)。