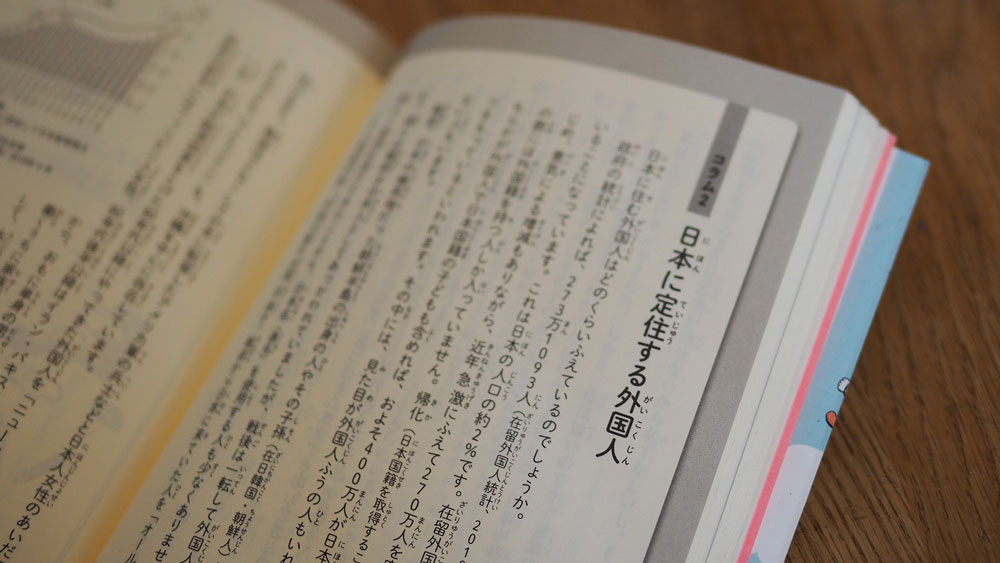1991年、戦争が終結したばかりのイランから「出稼ぎ」に来た両親に連れられて、弟2人とともに日本に来たナディさん。オーバーステイ(在留許可期間の超過滞在)のまま日本で育ち、高校在学中に在留特別許可を得て定住資格を獲得。現在は都内の企業で働きながら、2人のお子さんを育てています。昨年6月に『ふるさとって呼んでもいいですか 6歳で「移民」になった私の物語』(大月書店)を上梓したナディさんに、お話を伺いました。(その1)はこちら。
私たちは外国人だから……
――ナディさんは来日して3年目にやっと小学校に通えるようなりますが、学校でいじめなどには遭わなかったですか。
ナディ それは大丈夫でした。教室には公園で一緒に遊んでいた子もいましたし、日本語が話せたからですかね。小学校5年生のときには成績も上位でした。でも、それはめっちゃ勉強したからなんです。勉強しないと「気に入られない」って思っていました。だって、オーバーステイの勉強できる子と勉強できない子だったら、勉強ができるほうが好かれそうじゃないですか。
当時は、自分が何をしたいかよりも、日本にとってメリットになり得る存在か、気に入られるかどうかが行動の基準でした。無意識ですけどね。親も「私たちは外国人だから気に入られないとダメ」だと言っていました。日本の人たちが私たちを好きじゃなかったら生きていけないからって。
でも、いま思えば、勉強が苦手な子だっていますよね。「勉強ができるのはいい子」というのは世界共通のイメージだと思うんですけど、私はたまたま勉強ができたからその型にはまった。だけど本当は生きているだけで、もう十分なんですよ。何も分からないのに学校に行くだけでもすごいことだし、何も分からない子が隣にいてもいじめがなく過ごせるのもすごいことだし、いろいろな子がいていいし、みんなすごいんだよって伝えたいです。
――いま振り返って「もっとこういうサポートがあったらよかった」と思うことはありますか。
ナディ 学校では、先生が特に何かしてくれたという記憶がないんです。私が一人でなんとかやっていたから「この子は大丈夫」と思われていたのかもしれない。初めての外国人だったので、先生もどうしていいのか分からなかっただろうし。でも、最初は国語の授業で漢字が分からなくて毎回0点をとっていたので、まず小学1、2年生の漢字を学ぶような機会があったらよかったなと思います。
あと、たとえば調理実習で「三角巾」が必要だと言われても、どこに売っているのかもわかりませんでした。そういうものは友達の家に聞きに行っていました。夏休みの自由研究も、親もやった経験がないので何をするのか想像もつかない。いまなら「毎日の天気と温度の記録だけ付けておけばいいよ」ってなりますけど(笑)。イスラム教の教えを守るようになってからは、給食の献立によっては食べられるものがみかんと牛乳だけということもありました。そういうのは大変だったなって思います。
「教えて」と言える人がいる大切さ
――弟さん2人も、それぞれ小学2年のクラスと保育園に入ります。
ナディ 一歳下の弟は、ひらがなやカタカナが書けなかったので、国語の勉強では苦労していました。そのかわり、父に励まされて算数を頑張っていましたね。一番下の弟は保育園からだったので、良いことも悪いことも日本の子たちとほとんど同じ感覚でやっていたと思います。でも、親も私も「私たちは同じことをしても日本人とは違う。うちらはガイジンで罰が重いから悪いことはしちゃだめ」といつも説明していました。弟は「いや、同じ人間じゃん」って言うのですが、「世の中は違う、社会はそう思わないから」って。
――そう言われても納得できないでしょうね……。ナディさんが困ったとき、周りに頼れる人はいましたか。
ナディ 近所で友達になったゆいちゃんのお母さんがそうでした。両親は日本語が読めないので、保護者向けの「おたより」や学校のプリントは弟の分も解読するのは私の役割だったんですけど、通信簿などの手書き文字は私も大体読めないし、漢字の画数も調べにくい。そういうのは、「ゆいちゃんのおばちゃん」に「読んで」って頼んでいました。あと、宿題で文章題が読めないときも。でも、あんまりたくさんだと大変かなと思って、優先順位が高そうなものから選別していました。読んでいた少女漫画雑誌『なかよし』の懸賞ハガキは、ゆいちゃんのお父さんが一緒に書いてくれたんですよ(笑)。ゆいちゃん一家は、そんな感じで本当に優しかったです。
――そういう相手がいるかどうかは大きいですね。
ナディ めちゃめちゃ大きいです。私はいま2人の子どもを育てているのですが、子育てにたとえると少し想像しやすいかもしれません。たとえばベビーカーだと階段が登れないので遠回りしないといけないし、駅に行くだけでも大変になりました。そんなとき、周りに「助けて」とか「一緒に手伝って」と言えるかどうかで全然違う。育児で不安なことがあるときも、相談できるママ友がいるだけで心が軽くなります。同じように、言葉や文化がわからないときに周りに「教えて」って言える人がいることはすごく大事です。
「一緒に暮らす仲間」という視点
――ナディさん一家は、当初は3年で帰国する予定だったそうですが、どうして滞在を延ばしたのでしょうか。
ナディ ちょうど3年経ったときに私たちが学校や保育園に入ったことが大きいと思います。子どもたちが日本で頑張って勉強して教育を受けているのをみて、両親はイランに戻って振り出しに戻すのもかわいそうかな、と思っていたんじゃないでしょうか。日本の国内で転校するときだって、親はそう考えますよね。
「技能実習」や「特定技能」についての法律をみると、期限があったり、家族を連れて来る制限があったり、「労働者としての外国人は必要だけれど、住み着かれたら困る」という思惑を感じます。私たちも人間なんだってことをきちんと考えないで、ただ「労働力」としてしか見ていないから、自分の思い通りに動かせると考えてしまうんでしょうね。でも、日本の人だって生まれた市町村に死ぬまでずっといる人ばかりじゃありません。移動もするし、子どもが生まれたらそこに定住したいと思うのは普通のことです。
最初は「出稼ぎ」でくる外国人であっても、「これから一緒に住むかもしれない人たちなんだ」という目で見て、これからはもう少しきちんと考えていく必要があると思います。 国の政策を見ていると、外国人を労働者としてしか見てない状況は30年前とまったく変わっていないし、むしろその「労働力」の部分だけを確実に確保しようとする体制へと変わってきているように思います。
――ご家族で入国管理局へ在留特別許可を求めて出頭したのは、ナディさんが中学3年生のときでした。高校在学中に在留特別許可が出ましたが、一歩間違えれば強制送還されていたかもしれないわけですよね。
ナディ それまで在留資格がないまま生活してきましたけど、健康保険に加入できないのでケガしても病院にも行けないし、学校に行けない時期もありました。当時、中学生だった私も、いつ強制送還されるかわからないと思いながら高校受験のための勉強をしていました。日本の高校に入っても、強制送還されてイランに戻されたら一から生活をやり直さなくてはいけません。そういう出口のない状況がイヤになって出頭することにしたんです。
私たちは幸い在留許可を得られましたが、いまはもっと状況は厳しくなっていて在留特別許可が下りなくて入管施設に収容される人も多くいます。しかも、入管施設には収容期限がないので、何年もの間収容され続けている人もいるんです。オーバーステイ=犯罪者ではないのに、刑務所よりもひどいですよね。
なぜコンビニで働く留学生が増えたのか
――ナディさんはその後、日本で大学に行き、就職もしています。それでもずっと「日本では気に入られないといけない」という気持ちを感じていらしたとか……。
ナディ そうです。日本で生まれ育った人は「私は健康保険を受けられているから日本に恩義がある」なんて思わないのが普通でしょうけど、私はそういう風に感じてきました。それは、そう思わずにはいられない雰囲気を社会がつくっているからじゃないかなって思います。「なんで外国人がこんなに日本に来るの?」「なんで外国人のためにこんなことをしなくちゃいけないの?」と思われているように感じます。
たとえば、コンビニで留学生が働くことが増えましたが、「なんで日本語をちゃんと話せないの」という話が出てきますよね。でも、そうじゃなくて「なぜ以前は外国人がいなかったのだろう」「なんで日本人は働いていないのだろう」と、そこに外国人がいる背景について考えてみてほしい。外国人が来ることで日本が得るものは「労働力」だけではありません。日本の「当たり前」を基礎にしてない人たちの見方から学ぶことで、お互いが気持ちよく過ごせる働き方や暮らし方を考えるきっかけにもできると思います。
私はずっと日本が一番素晴らしいと思っていて、日本崇拝主義者みたいな感じだったのですが、昨年子どもを連れて40日間イランに滞在したことで少し見方が変わりました。イランでは子ども連れにすごく優しくて、知らない人でも助けてくれます。子どもが1歳と3歳だったので、食事中に騒いだり、こぼしたりすることがあるのですが、店員さんが「子どもなんだから、いいですよ」と言ってくれて泣きそうになりました。日本だと周りの視線が気になって子連れではなかなか外食もできないですよね。こういう心のゆとりを私たちは忘れているな、と思いました。
――アイデンティティに悩んだ時期が長くあったそうですが、自分は「イラン系日本人」だと思うに至るまでは、どういう思いだったのですか。
ナディ ずっと他人目線で自分のことを考えていたんですよね。顔立ちで日本人かどうかを判断する人もいれば、日本にいる期間にこだわる人もいる。そういうものにずっと振り回されていました。でも、そうじゃなくて「自分が何人か」は自分で決めていいんだって思えるようになったのは、周りに自分で決めている子たちがいたからです。
昔からの友達で、ふだん自分のことを「朝青龍みたいな顔」と自称していた子がいたのですが、あるとき「モンゴル人に見えますが、日系アルゼンチン人です! ルーツは日本ですが、アルゼンチンのアイデンティティなんです」と自己紹介しているのを聞きました。見た目と中身のギャップを気にしないどころか、「自分」という一人の人がいくつもの要素を含んでいることを前向きに認めていました。
私はそれまで自分を「イラン人らしさ」「日本人らしさ」のどちらかにあてはめようとしていました。いろいろなルーツの人に出会ってきたのに、視野が狭かったんです。周りが見えるようになったら、自分の考え方も広がりました。人生はその繰り返しなんだなって思います。
私のように頑張らなくてもいい社会に
――本を出したことで、周りからどんな反応がありましたか。
ナディ 高校時代の同級生が連絡をくれたのですが、その人は建築関係の仕事をしていて、技能実習生の外国人と一緒に働いているそうです。「ずっと日本人がいちばん真面目だと思っていたけど、技能実習生と仕事をしてみたらすごく真面目でびっくりした。ナディの本を読んで、もっと積極的に彼らとかかわっていかなきゃいけないなと思った」という内容で、夜中にすごい長いLINEをくれたんです(笑)。それが、すごく嬉しかったですね。
もっと批判的な意見がくるんじゃないかと思っていたんですけど、「よく頑張りましたね」って言われることのほうが多いです。それはとても嬉しい反面「よく頑張らなかった私」だったら、どうだったんだろうな? と思ったりもします。私は周りに気に入られなくちゃいけないと思って礼儀正しくして勉強も頑張ったけど、もし私がぐれていたら周りの反応は変わっていたかもしれませんよね。
私たちよりあとから日本に来たというフィリピンルーツの女性からも感想をもらったのですが、彼女には子どもが3人いて「うちの子どもも大変なことはあると思うけど、こんな風に頑張っていってほしいな」と言っていました。でも、私は、ここまで頑張らなくてもいい社会になってほしいと思っています。
どんどん日本はゆとりのない社会になっていて、少しでも枠からはみ出すと「お前が悪い」と非難されてしまう。日本の人にとっても暮らしにくい国になっているのではないでしょうか。その前に「変えていきましょうよ」と伝えていきたい。これからも一緒に日本で生きていく仲間として、この社会を暮らしやすくしていくために、私たちも声を上げていく時代になっているのだと思います。
(構成・写真/マガジン9編集部)
ナディ 1984年イラン生まれ。91年に両親とともに家族で来日して、オーバーステイ(超過滞在)のまま首都圏郊外で育つ。小学3年から公立小学校に通い、高校在学中に家族とともに在留特別許可を得て定住資格を獲得。大学卒業後は都内の企業に勤務し、現在は2児の母でもある。著書に『ふるさとって呼んでもいいですか 6歳で「移民」になった私の物語』(大月書店)