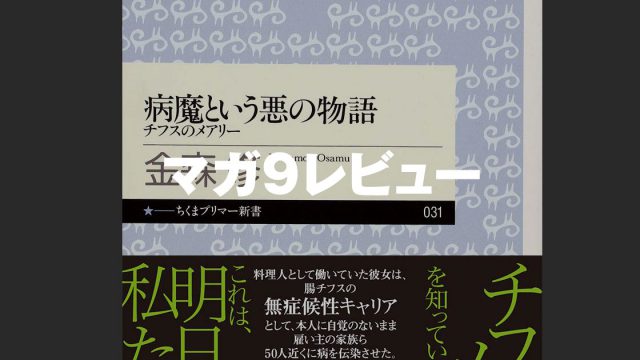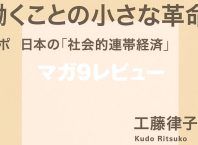今から100年あまり前のアメリカで、“チフスのメアリー”と称されたひとりの女性の人生を追った本書は、初版2006年、10代の若者向けに書かれた地味な新書だった。それが急遽注目を浴びるようになったのは、新型コロナウイルスの感染が広がった今年5月頃。「今日のコロナ禍を予言している」「公衆衛生と人権を問う衝撃の実話」と話題になり、「伝染病の恐怖と戦う現代人が今読むべき歴史的教訓の書」として緊急復刊された。
本書の舞台は20世紀初頭のニューヨーク、主人公はメアリー・マーロンという実在の人物。メアリーは1869年北アイルランドに生まれ、少女時代に家族とともにアメリカに移住し、ニューヨーク周辺で賄い婦として働いていた。料理上手で子どもの面倒見もよく、雇い主からも信頼されて、貧しいながらもそれなりに平穏な人生を送っていた。
その人生が暗転したのは37歳の時。当時流行っていた腸チフス菌を体内に隠し持ち、料理を通じて何人もの人に感染させたという嫌疑で、公衆衛生当局により身柄を拘束されたのである。
実は、彼女が働いていたある一家から6人の腸チフス患者が出て、その感染経路を追う中でメアリーの存在が浮上したのだ。調査を進めるうちメアリーが過去10年ほどの間に雇われていた家族のなかから、実に50人近い感染者がでており、死亡者もいることがわかった。公衆衛生の専門家はメアリーが感染源に違いないと確信し、強制的に検査を受けさせる。はたしてメアリーの便からは高濃度の腸チフス菌が検出された。
そう、メアリーは、健康状態が良好でありながら菌を体に持ち続ける「健康保菌者」、いまでいうなら「無症候性キャリア」のスーパースプレッダーということになる。納得のいかないメアリーは必死に抵抗するものの、市民の安全、公共の福祉のためという錦の御旗を掲げる公衆衛生局の権力は絶大で、マンハッタンのイースト川に浮かぶ孤島の病院に強制隔離されてしまう。
3年後、メアリーは一連の措置は不当だとして裁判に訴えるが、隔離、強制的な検査、私権の制限は、防疫上正当化されるとして敗訴。条件付きで一時解放されたものの、5年後に再び集団感染を起こしたとして逮捕、隔離。以後23年間、69歳で亡くなるまで、孤島の隔離病院から出ることは叶わなかった。
メアリーは当時のマスメディアの格好の餌食になった。大衆紙は「毒婦」「無垢の殺人者」「歩く腸チフス工場」「人間・培養試験管」「毒をまき散らす米国で最も危険な女」と書き立てた。さらに「チフスのメアリー」というタイトルのもと、フライパンの上で小さなどくろを料理する女性のイラストをのせ、“腸チフス菌を体に抱えたまま料理する女”というイメージを市民に植え付けた。
20世紀初頭のアメリカでは年間20万人前後のチフス患者が発生していたといわれ、メアリーと同様のキャリアも相当数いたと思われる。なのになぜメアリーだけが悪の象徴とされたのだろう。その背景にはメアリーがアイルランド系移民のカトリック教徒で、貧しい独身の賄い婦だったことなど、社会的条件が複雑に重なり合っているのではと、著者は指摘する。
これが実話だということに慄然とする。そして著者の予言的な慧眼にも驚嘆する。
〈社会に住む不特定多数の人たちの命を救うためなら、一人の人間、または少数の人間たちの自由がある程度制限されても、仕方のないことなのか。その場合、一言で制限といっても、どの程度までの制限が許されるのか〉(本書13ページ)
〈恐ろしい伝染病が、いつ社会に蔓延するかは誰にもわからず、もしそうなれば、電車で隣に座る人が、恐ろしい感染の源泉に見えてこないとも限らない。(中略)そして、この生物学的な恐怖感が私たちの心の奥底に住み着き、いつその顔を現すかはわからないような状況が、人間社会の基本条件なのだとするなら、未来の「チフスのメアリー」を同定し、恐怖を覚え、隔離し、あざけり、貶めるという構図は、いつ繰り返されてもおかしくはない〉(本書137ページ)
全くその通り。たとえば昨今コロナ無症状感染者を巡って、「無症状無自覚なまま、ウイルスをまき散らしている」「徹底検査で感染者をあぶりだし、隔離せよ」「検査陽性者を封じ込めろ、野放しにするな」「(一定の観察期間が終わったら)無罪放免」など、まるで犯罪者扱いの物言いが気になる。
また「徹底検査で陽性者を見つけ出して隔離し、陰性の人は安心して社会に出ることが防疫と経済活動の両立に有効」とも言われる。なるほどと思いつつ、「コロナのメアリー」がでてこないか、一抹の不安はぬぐえない。
本書の著者・金森修氏は科学思想史の研究者。この本を書きたいと思ったのは“ある種の悲しみに心を突き動かされて”という。著者のまなざしは温かく、常にメアリーに寄り添い「どうか彼女の身になって考えて欲しい」と読者に呼びかける。そして最後にこう締めくくる。
「どこかで未来のメアリーが出現するようなことがあったとしても、その人も、必ず、私たちと同じ夢や感情をかかえた普通の人間なのだということを、心の片隅で忘れないでいてほしい」と。コロナ禍の今、金森さんは何を思うか聞いてみたいと思ったが、残念なことに2016年に亡くなっている
先日の新聞にちょっとホッとする記事を見つけた。新潟県見附市の公式フェイスブックに「安心して感染したい」というタイトルの漫画が掲載されたという。長らく感染者ゼロだった小さな市では、病気そのものより、万が一感染した場合の周囲の目を恐れる空気が強かった。そんな息苦しさに「もし感染しても、早く完治してねと励まし合う町であって欲しい」との思いから市在住のイラストレーターが描いたという。誰もが安心して感染できる、それをみんなが温かく支え励まし回復を願う。今日のコロナ禍を見ずして逝った金森さんに知らせたいエピソードではある。
(田端 薫)