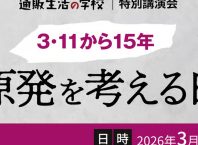編集部に恵投いただいた書籍や、ただいま絶賛「積ん読」中! な本、これから見たいあの映画……などなど、スタッフが「気になる」本や映像作品を時々ご紹介していきます。読書や映画鑑賞の参考に、どうぞ。

〈書籍〉『いちばんたいせつなもの』(斎藤貴男作・おとないちあき絵/新日本出版社)
これはお話絵本です。あの舌鋒鋭く政治批判をするジャーナリスト・斎藤貴男さんが初めて書いた子ども向けの小説なのですから、ちょっとびっくりします。でも、ものすごく面白いです。
実は、斎藤さんの子どものころ(小学3年生)の体験をお話にして書いたものです。主人公の少年テツオくんは、斎藤さんの記憶の中の自分です。体が弱かったテツオくんは、海辺の「健康学園」で、親元を離れてしばらく暮らしました。それは少年にとって楽園のような日々でした。でもその楽園で、少年は涙を流します。なぜ泣いたのでしょう。それがこの本の「いちばんたいせつなもの」なのです。大人になってしまったかつての少年がいま読んでも、とても素敵な本なのです。
*

〈書籍〉『音楽プロデューサーとは何か 浅川マキ、桑名正博、りりィ、南正人に弔鐘は鳴る』(寺本幸司著/毎日新聞出版)
音楽プロデューサーって、どんな仕事なのだろう。一般人にはちょっと想像もできない世界だが、ちょっと覗き見してみたい。そんな興味からページを開けば、たちまち読者は引きずり込まれてしまう。これは、そんな稀有な世界の、稀有な人間の、そして稀有な人たちとの関わり合いを、稀有な筆致で書き綴った稀有な本なのである。
誰もが名前くらいは聞いたことはあるだろうミュージシャンたち。浅川マキ、桑名正博、りりィ、南正人らと、深い関係を築き、表層から深層までを同伴した男の半生記でもある。ことに、浅川マキという不世出の歌手との出会いと別れ、そして死。
まるで現場に一緒にいるように、読者をいざなう著者の文章はただものではない。読めば、ここに出てくるミュージシャンたちの歌を、あなたは絶対に聴きたくなるはずだ。そんな不思議な魅力にあふれた本である。
*

〈書籍〉『いないことにされる私たち 福島第一原発事故10年目の「言ってはいけない真実」』(青木美希著/朝日新聞出版)
懸命に福島を追いかける著者。その最新刊がこれ。
サブタイトルに「福島第一原発事故 10年目の『言ってはいけない真実』」とあるように、なぜか避難者統計には存在しない、むしろ統計上は消されてしまった避難者たちの悲痛な語りが全編を覆い尽くす。
汚染した水を飲んだ私が赤ん坊に母乳を与えてしまった。それが将来、どのような影響を及ぼすか……と悩んだ母の言葉は、重く心に沈殿したままだ。しかもその親子は避難者統計から消されていた。それが「第1章・消される避難者」。そして「第2章・少年は死を選んだ」は、家族5人で避難した末の悲劇。読むのが辛くなるけれど、目を逸らすことができない。著者の筆は、次第に怒りを伴って……。10年目の真実がここにある。
*

〈書籍〉『災害からの命の守り方―私が避難できたわけ―』(森松明希子著/文芸社)
『いないことにされる私たち』に登場する森松さんが自ら著した労作で、なにしろ470ページを超える分厚さの本だ。序章から全11章、そして終章まで。あの原発事故からふたりの子どもを伴って逃げ続け、闘い続けた母親の全記録。書いても書いても途切れることのない問題が湧き出てくる。著者は誠実にそれに向き合い、その解決へ向けて考え続ける。「逃げることは権利だ!」との主張は、やがて日本国憲法によって裏付けられる。
だが、「お金もらってやってるんでしょ」などの心ない差別が心を痛めつける。負けない。著者は「自分の頭で考えることが最高の危機管理」だと思い知る。だから、国連にまで出かけて訴えのスピーチをする。
最終章、コロナ禍でも闘いは続く。これだけの分厚さが確かに必要だったと思わせる、熱気と訴えの心情に満ちた本である。
*

〈書籍〉『レストラン「ドイツ亭」』(アネッテ・ヘス著・森内薫訳/河出書房新社)
なぜ主人公エーファ・ブルーンスはポーランド語ができるのか。ホロコースト裁判からおもむろに始まるこの物語を読み進んでいくうち、その理由も見えてくる。ナチス・ドイツの過去に対する清算は、彼女自らをもえぐるものでもあった。しかし、年配者たちは言う。私たちは何も知らなかった、あの時代は仕方がなかった、と。
その数年前、エルサレルムでは元ナチスの親衛隊中佐のアドルフ・オットー・アイヒマンの裁判が行われた。アウシュヴィッツへのユダヤ人大量輸送の責任者であった彼が、「自分は命令に従っただけ」という証言を繰り返す姿を観察した哲学者・ハンナ・アーレントは、アイヒマンを「凡庸な悪」と評して物議を醸した。決して他人事ではない。「凡庸な悪」は私にも、あなたにも宿る可能性がある。この作品を1967年生まれの作家が書いたことにも注目したい。
*

〈書籍〉『ドイツの学校にはなぜ「部活」がないのか 非体育会系スポーツが生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間』(高松平蔵著/晃洋書房)
ドイツのスポーツ文化の歴史は都市の発展と密接な関係がある。スポーツは住民の健康と楽しみ、そして互いの交流の手段であり、体操、サッカー、水泳、バレエ・ダンス、テニスなどをやりたい子どもたちは地域のクラブに入る。
スポーツクラブ会員は多世代にわたる。注目すべきは41~60歳が一番大きな層を形成していることだ。日本では地域との関わりがもっとも薄い世代(とくに大都市の男性)と思われる大人たちがスポーツに汗を流し、クラブハウスでビールを飲んで歓談しているのである。地域の様々な人たちが集まるクラブには厳しい上下関係はない。お互いが「君」「お前」と呼び合う、いわゆる「タメ口」が当たり前の環境のなかで、未来のトップアスリートも育っていく。
*

〈映画〉『JUNK HEAD』(2017年/堀貴秀監督)
総ショット数は約14万コマ、セットもフィギュアもすべて手作り。数センチ単位でフィギュアを動かしては撮影という気の遠くなるような作業を重ねて完成させたアニメーションである。
人類は遺伝子操作により長寿を獲得したが、その代償として生殖能力を失った。世界は環境汚染、ウイルス感染により、滅亡への道を歩んでいる。人類が生き延びるためにはどうすればいいか。そのカギは地下にあった。幾層にもわたる奈落には独自に進化した人工生命体マリガンがいて、それを地上に持ち帰るべく、主人公は奥底へと潜っていく。
全編交わされる言語は解読不能。すべて「字幕」。初めは面白おかしく見ていたが、奇怪なフィギュアの動きと字幕を追っていくうちに、こちらも閉塞感に襲われる。すべての人におススメではないが、かつて見たSF映画の断片がときどきフラッシュバックすることで、スクリーンは厚みを増していった。