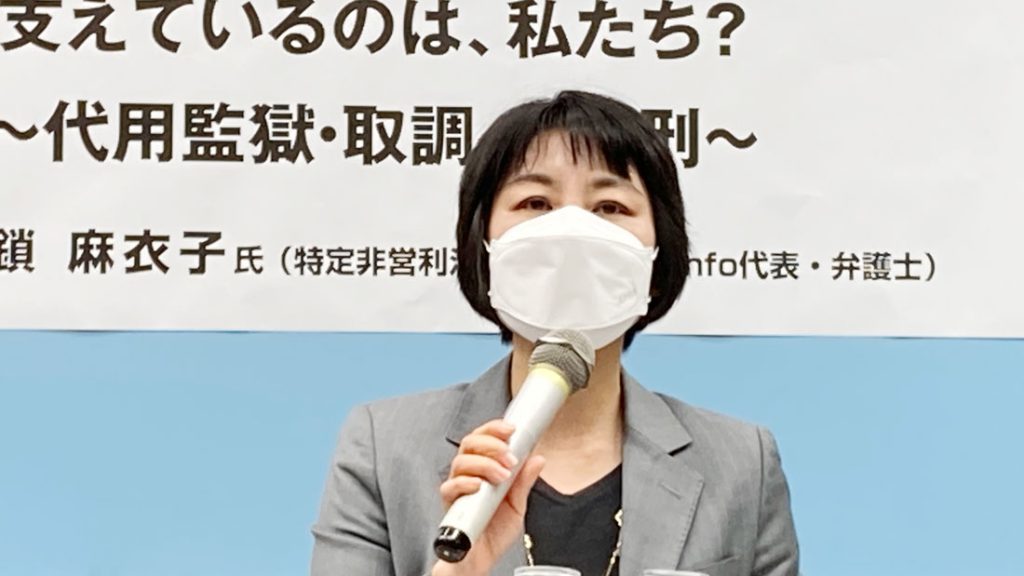日本の刑事司法における代用監獄と死刑制度は、いずれも国連の条約機関などから国際人権基準に合致しないとして、廃止や運用の改革を求められています。しかし、日本政府はそうした国際社会の声に応えず、人権条約委員会による勧告も拒否し続けてきました。国際人権基準と日本の刑事司法制度の乖離はなぜ生じているのでしょうか。代用監獄や死刑といった制度を支えているものは何なのか、刑事司法のさまざまな問題に関して正確な情報を提供する特定非営利活動法人CrimeInfo代表、田鎖麻衣子さんにお話しいただきました。[2022年4月9日(土)@渋谷本校]
なぜ留置施設に勾留され続けるのか?
今日は、刑事司法をめぐる代用監獄、取調べ、死刑の問題についてみなさんと一緒に考えていきたいと思います。
現在の日本の刑事手続では、犯罪が起きたかもしれないとなると、捜査、起訴、公判を経て最終的に判決に至ります。警察が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に被疑者を検察官に送致しなければなりません。それを受けた検察官は、勾留というさらなる身体拘束を求めるかどうかを24時間以内に決めます。ここで勾留が請求されると、その勾留を認めるかどうかを裁判官が判断します。そして、裁判所が勾留を決定すると、その後の延長も含めて20日間までの勾留が可能となります。最初の逮捕から数えると、最長で23日間。この期間中に、検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断します。
被疑者の逮捕というものは簡単に行われるように思われるかもしれませんが、事件が起きて「この人が犯罪を行ったのではないか」と警察が疑った人の約3分の2は、逮捕に至っていません。残りの約3分の1の人については、警察が「逮捕が必要」と判断し、裁判官に逮捕状を請求するわけですが、この場合の逮捕状発付率は、ほぼ100%。さらに勾留状の請求率も令和3(2021)年のデータで93.7%、そのうち却下率は4.2%となっています。つまり、逮捕率はそれほど高くないけれど、いったん逮捕されると身体拘束状態からの解放は難しいといえます。
こうした刑事手続の流れの中で、身体拘束をされた被疑者は物理的にどこに置かれるのでしょうか。警察によって逮捕された場合、最初は警察留置場、すなわち留置施設に入ります。そして、勾留が認められると拘置所、つまり警察ではなく法務省が管轄する刑事施設に移るのが、法律上の原則です。刑事訴訟法では、勾留状には「勾留すべき刑事施設」を記載することになっているからです。しかし、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に、「刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置できる」と規定されています。
この規定は、明治41(1908)年の「監獄法」が元になっており、当時は刑事施設の整備が進んでいなかったので、警察署の留置場を監獄の代わりに使えますよという、やむを得ない制度だったのです。しかし現在では、令和2(2020)年時点の未決の被疑者・被告人を収容する刑事施設の収容率は34.8%。刑事施設がスカスカになっているのには、平成15(2003)年あたりをピークに犯罪認知件数が急激に減っているという背景がありますが、刑事施設にはゆとりがあるのに、いまだに「代用監獄」として警察署の留置場が使われ、しかも例外であるところの「代用監獄」にほとんどの被疑者が勾留されます。いわば原則と例外が逆転する事態が生じているわけです。
代用監獄制度の問題点とは
代用監獄制度は、国際人権基準から見て問題があると指摘されています。日本が批准する代表的な国際人権条約が、「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」です。この規約の締約国は、規約で保障された権利が実際に国内でどのように実現されているのか、定期的に自由権規約委員会に報告する義務を負っています。そして委員会は、締約国の報告を審査します。
自由権規約9条3項は、「刑事上の罪に問われて逮捕され又は抑留された者は、裁判官又は司法権を行使することが法律によって認められている他の官憲の面前に速やかに連れて行かれるものとし、妥当な期間内に裁判を受ける権利又は釈放される権利を有する」と定めています。
自由権規約委員会は、この規定について「司法統制を伴わない法執行官の管理下でのより長い抑留は、虐待の危険を不必要に増加させる」との解釈を示しています。ところが、日本では警察に逮捕された被疑者は、勾留後もそのまま警察のコントロール下に最長で23日間も置かれ続けます。そこで、これに対して自由権規約委員会は、代用監獄制度を「廃止するためにあらゆる手段を講じること」を勧告しているのです。また、「拷問等禁止条約」の実施機関である拷問禁止委員会からも、代用監獄制度について「捜査と拘禁の機能の分離」をするよう勧告されています。
こうした勧告に対して日本政府は法律上、「留置担当官はその留置施設に留置されている被留置者に係る犯罪の捜査に従事してはならない」し、犯罪捜査規範でも「現に被留置者に係る犯罪の捜査を行っている捜査官が当該被留置者の処遇を行うことを禁止している」から、「捜査と留置管理の機能は完全に分離されている」と述べています。しかし、ここでいう「分離」とは、留置施設Aの留置担当官が留置施設Bの被留置者の捜査を行うことや、C警察署で被疑者Dの捜査を担当する捜査官が、C警察署の留置施設にいる被疑者Eの処遇を行うことを禁止するものではありません。捜査と留置管理の機能が完全に分離されているとは、とてもいえません。
例えば、引野口事件と呼ばれるケースでは、定員2名の女性用留置場で、犯行を否認している被疑者と一緒に収容されていた被留置者が、「彼女は私に犯行を告白した」という主旨の供述をして、それが検察官により証拠として提出されました。裁判所は、取調べとは区別されるべき身体拘束が捜査のために濫用されたと批判し、最終的に彼女は無罪になりました。取調べと勾留が、ともに警察施設内で行われる代用監獄制度には、現実の弊害があるのです。
けれども、代用監獄は必要だというのが日本政府の説明です。自由権規約委員会の審査で、政府代表はこう発言しています。「日本の刑事司法においては逮捕から23日間という限られた期間内に綿密な操作をし、事案の真相を解明して、その上で起訴するかどうかを決めなければならない。そのためには被疑者を拘束する場所は捜査機関と近く、かつ取調室が整備された場所である必要がある」。「よって代用監獄は必要なのだ」と。
さらに政府は、取調べで被疑者が後悔や謝罪の念を抱くようになることで「社会復帰の率も高まり、低犯罪率にも寄与する」とも述べています。政府にしてみれば、代用監獄の廃止は、刑事政策上も重要な意義を持つ被疑者取調べを困難にし、日本における刑事政策のあり方を根底から変容を迫るものであり、到底受け入れられない、ということになるわけです。
代用監獄制度を支えているのは私たち?
こうした日本の捜査、取調べについては、検察官出身の元最高裁裁判官が次のような文章を書いています。「捜査官・公訴官の使命は、伝統的に、真犯人と確信できるものを特定して、起訴し、有罪判決を獲得することにあり、精密捜査・厳格起訴が当然のやり方とされてきた」のであり、無罪となった場合は、「職務遂行上の重大な過誤と受け止められ」厳しく非難される、と(亀山継夫「刑事司法システムの再構築に向けて」(『松尾浩也先生古稀祝賀論文集 下』(1998)所収))。
日本では起訴される事件は非常に絞り込まれ、検察官が起訴する必要がないと考える場合には起訴猶予となります。実際に起訴猶予は多用され、令和3年度版犯罪白書によると、令和2年に検察庁が捜査段階で最終的に処理した事件の被疑者のうち、公判請求は9.8%、略式命令請求が21.5%に対し、起訴猶予は55.5%となっています。したがって、公判請求がされた段階で、ほぼ有罪という印象を、社会全体がもつのです。日本の刑事裁判の有罪率は世界的にもかなり高いのですが、検察官が「間違いなく有罪に持ち込める」と考えるものばかりが起訴されているので、有罪率は当然高くなるのです。
しかし、そうなると「無罪の推定」の原則はどうなってしまうのでしょうか。自由権規約14条2項には「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定される権利を有する」と書かれています。もちろん日本の刑事訴訟も無罪の推定を前提として行われていますが、現実には、起訴されると、ほとんどが有罪になる。しかも、再審で無罪になった例ですら、捜査官が「今でも犯人だと思っている」と堂々と言うほどです。捜査官だけでなく、市民社会の側も、無罪判決が出てもその人を犯人視し続け、偏見が根強く残ってしまいます。
「10人の罪ある人を逃すとも、1人の無辜を罰するなかれ」という格言があります。ですが、社会の中に「緻密な捜査をして、犯人は必ず罰しなければならない」という要求があり、国民が無意識のうちに捜査官にプレッシャーを与えているとしたらどうでしょうか。事案の真相解明、そのための綿密な被疑者取調べ、被疑者取調べに必要とされる代用監獄。こういったものを、実は私たちが支えてしまっているのではないかという疑問が湧くわけです。
死刑制度を廃止しない理由
ここからは死刑についてお話をしたいと思います。日本の刑法は、主刑として、生命刑である死刑、自由刑である懲役・禁錮・拘留、財産刑である罰金・科料を規定しています。死刑の適用が可能な犯罪は、殺人、強盗殺人・致死などの他、人の生命が奪われない犯罪も含め、全部で19罪あります。
死刑の適用状況を見ると、第一審での死刑判決数は1940年代は非常に多かったのですが、以後は急激に下がり、死刑執行数も1970年代以降は減少傾向にあります。また、1966年から2020年までに殺人の罪によって亡くなった被害者の数と殺人認知件数の推移を見ると、どちらも減っていることがわかります。令和2年に、殺人の既遂で有罪となった125人のうち、120人は有期懲役、3人が無期懲役、死刑は2人。それほど、死刑はまれにしか言い渡されないということです。
日本の死刑制度は、国際社会からどのように見られているのでしょうか。自由権規約6条1項は「すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によって保護される。何人も、恣意的にその生命を奪われない」と規定します。はっきりと「死刑は廃止しなさい」と書いているわけではありませんが、2項では死刑は「最も重要な犯罪についてのみ科することができる」としています。
規約6条の解釈において、自由権規約委員会は、死刑は生命に対する権利の「完全な尊重と両立することは不可能」と述べています。要するに「死刑の廃止が望ましい」ということを示しているわけです。また、死刑判決へとつながる裁判は、「公正な裁判を受ける権利の保障が特に重要」であり、この権利が尊重されなかった結果として死刑判決が言い渡されることは、生命に対する権利の侵害になる、とも述べています。
こういった見解を前提に、委員会は、日本に対して勧告を行っています。まず、死刑適用可能犯罪が19罪もあることについて「死の結果を伴う最も重大な犯罪」に限定すべきだと言っています。そして「公正な裁判の保障」として、連日厳しい取調べが行われた末に被疑者が自白し、えん罪が疑われる「袴田事件」のように、「拷問あるいは虐待により得られた自白が証拠として用いられる」ことにも懸念を示しました。さらに「死刑の廃止を目指し、規約の第二選択議定書(死刑廃止を目的とする選択議定書)への加入を考慮するべきである」と勧告しています。
こうした勧告に対して、日本政府はどう回答しているのでしょうか。死刑制度をなぜ維持するのかについては、政府による委員会への説明は一貫しています。「国民世論の多数が極めて悪質・重大な犯罪については死刑もやむを得ないと考えている」こと、それから「凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況」にあること。つまり国民世論と犯罪情勢を理由として、「死刑廃止は適当ではない」というわけです。しかし、犯罪件数は先に見たように減っています。ですから、実質的な理由付けは国民世論ということになります。
死刑制度をめぐる国民世論の実際
では、国民世論は実際にどうなのでしょうか。内閣府が5年ごとに行っている死刑制度に関する意識調査を見ると、「死刑は廃止すべきである」は9%、「死刑もやむを得ない」が80.8%、「わからない」が10.2%(2019年)。「やむを得ない」と答えた人に、死刑制度を存置する理由を聞くと(複数回答)、「死刑を廃止すれば、被害を受けた人やその家族の気持ちがおさまらない」「凶悪な犯罪は命をもって償うべきだ」という理由をあげた人が多く、「凶悪な罪を犯す人は生かしておくと、また同じような罪を犯す危険がある」が続きます。
この内閣府調査をさらに詳しく分析するために、ミラー調査という手法での意識調査が行われました。その報告書(佐藤舞、ポール・ベーコン『「世論という神話」日本はなぜ、死刑を存置するのか』2015年)を見ると、ミラー調査では「死刑は絶対にあったほうがいい」「どちらかといえばあったほうがいい」「どちらともいえない」「どちらかといえば廃止すべきだ」「死刑は絶対に廃止すべきだ」の5段階に分けて聞いています。「絶対にあったほうがいい」(27%)と、「どちらからといえばあったほうがいい」(46%)を合わせて73%。たしかに廃止派は少ないのですが、徹底した存置派もそれほど多くありません。そして「絶対にあったほうがいい」「どちらかといえばあったほうがいい」と答えた人に、「もしも死刑が廃止されたらどうするか」という質問をすると71%の人が「政府(の)政策として受け入れる」と回答しています。ですから、必ずしも圧倒的多数の人たちが「死刑は絶対にあったほうがいい」と考えているわけではないことが示唆されるわけです。
日本政府は、「国民の多数が死刑もやむを得ないと考えている」と言いますが、正確な情報に基づいて考えているかというと、そうでもありません。例えば、犯罪が起きて、犯人が死刑にならなければ「被害を受けた人やその家族の気持ちがおさまらない」という回答が多くありました。そこでは、凶悪な事件の犯人は死刑判決を受けるということが暗黙の前提になっていますが、実際は殺人の既遂で有罪となった人のほとんどは死刑になっていない、そうした情報が把握されていないのです。
また、ミラー調査を実施した佐藤舞さんたちは、市民が死刑の問題についてディスカッションをして、ディスカッションの前と後で意見がどう変化するかも調査しています。この調査のもようはCrimeInfoのウェブサイトでドキュメンタリー映像(「望むのは死刑ですか 考え悩む“世論”」)として見ていただくことができます。
このように世論は固定化されたものでも、徹底したものでもなく、正確な情報に基づいて世論が形成されているともいいきれません。しかし、政府は、世論、すなわち私たちが望んでいるから、死刑を維持せざるを得ない、と説明しているのです。
代用監獄や取調べに関しては、仮にその在り方を意識的に批判する側に立っているつもりでも、実はその行動が制度を支えることにつながっているのではないか、というお話をしました。他方、死刑制度に関しては、政府の側は、世界に向かって、私たち(国民世論)が必要だというから死刑を維持しているのだと説明していますが、言われている私たちの側は、それを意識していません。
こうしてみると、形は違いますが、いずれの局面においても、私たち自身が、制度や運用の維持を間接的に支えているのではないか、と私には思われるのです。ぜひ、皆さんにも考えてみて頂きたいと思います。
*
たぐさり・まいこ 特定非営利活動法人CrimeInfo代表、弁護士。東京大学法学部卒業。一橋大学大学院法学研究科博士後期課程修了。博士(法学)。一橋大学法学研究科非常勤講師。1995年、弁護士登録(第二東京弁護士会)。以降、死刑再審事件や、刑事施設での処遇をめぐる国家賠償請求事件などに取り組みながら、日弁連の刑事拘禁制度改革実現本部・人権擁護委員会などの弁護士会活動や、死刑廃止や刑務所改革を目指す国内外のNGO活動に従事。2016年、CrimeInfoの前身となるプロジェクトを英国・レディング大学と共同で開始。2019年、死刑制度をはじめ、日本の刑事司法制度に関し、正確で信頼できる情報を提供し、市民による刑事司法への理解を促進することを目的に、特定非営利活動法人CrimeInfoを設立。2021年、フランス共和国教育功労章シュヴァリエ受章。主な共著に『「被害者問題」からみた死刑』(日本評論社)、『孤立する日本の死刑』(現代人文社)、『刑務所のいま―受刑者の処遇と更生』(ぎょうせい)、『人権読本』(岩波ジュニア新書)など。