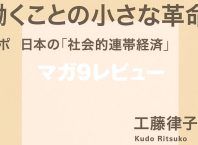舞台は19世紀末のパリ。冒頭、フランス陸軍大学校の校庭に、ユダヤ人のアルフレッド・ドレフュス大尉は両脇を兵士に挟まれて引き出される。罪状は敵対するドイツへの機密情報の漏洩。すなわちスパイ行為だ。その場で軍籍を剝奪されたドレフュスは、軍服のボタンを引きちぎられ、サーベルは真っ二つに折られた。
私は無実だ――毅然と叫ぶドレフュスに校庭の柵の向こうに集まった群衆から罵声が浴びせられる。その一部始終を神妙な表情で見つめていたのはピカール中佐だ。彼もユダヤ人に対していい感情を抱いていなかったが、ドレフュスの日頃の言動から、彼がそのような裏切り行為をする人間だろうかと疑問を抱いていたのである。
ドレフュスはその後、南米仏印ギニアの絶海の孤島、通称「悪魔島」に流刑される。映画『パピヨン』で主人公が収容されたところだ。同作品は悪魔島から自由を目指して脱獄する囚人の物語であるが、本来島を出ることなど不可能である。にもかかわらず、ドレフュスは寝るときに足かせによってベッドに括りつけられた。
そのころピカール中佐は、ドレフュスの筆致とされるメモがエステラージー少佐の筆跡と酷似していることに気づく。そして真実の究明に乗り出すのだが、軍上層部はそれをもみ消そうとし、それに抗議するピカールを拘束。作家であるエミール・ゾラが「私は糾弾する」(この映画のオリジナルタイトル)と題する記事を新聞に発表し、軍の関係者たちを名指しで非難すると、彼も逮捕された。
それでも真実を求めてやめないピカール、弁護士、ジャーナリストたちの地道な活動は続き、ドレフュス逮捕から12年後、最高裁判所は軍法会議の判決を破棄。ドレフュスは自由の身になった。
この間の流れを息をつかせぬ展開で見せるロマン・ポランスキー監督は、ポーランドのユダヤ人家庭の生まれ。第二次世界大戦中に両親をアウシュヴィッツで失った彼は、『戦場のピアニスト』において、ワルシャワゲットーで繰り広げられたナチスによるユダヤ人への蛮行を描いた。反ユダヤ主義の歴史をさらに掘り下げたのが本作品である。
ドレフュス事件当時、ドイツ系ユダヤ人のテオドール・ヘルツルがウィーンの新聞『ノイエ・フライエ・プレッセ』のパリ特派員として駐在していた。ヘルツルは、自由・平等・博愛をうたうフランス国内でドレフュスに対して「売国奴」「ユダヤ人に死を」と叫ぶ群衆の姿を見て、「ユダヤ人も自分たちの国家をもたなくてはだめだ」と考え、シオニズムを提唱。それがイスラエル建国へとつながっていく。
ドレフュス事件は現代のパレスチナ問題にもつながっているのである。本作の完成時に86歳であったポランスキーの「どうしてもつくっておかなければならない」という思いがスクリーンを通してこちらにひしひしと伝わり、彼の創造への意欲に感服することしきりだった。
(芳地隆之)
*