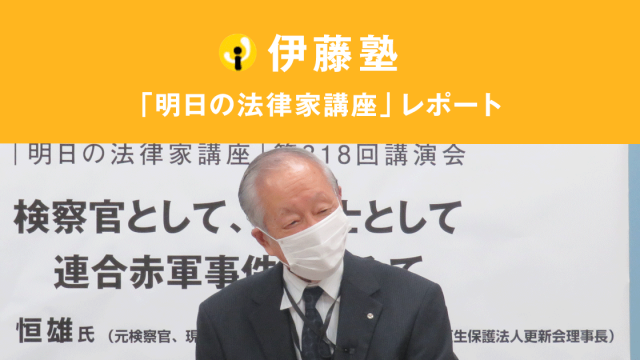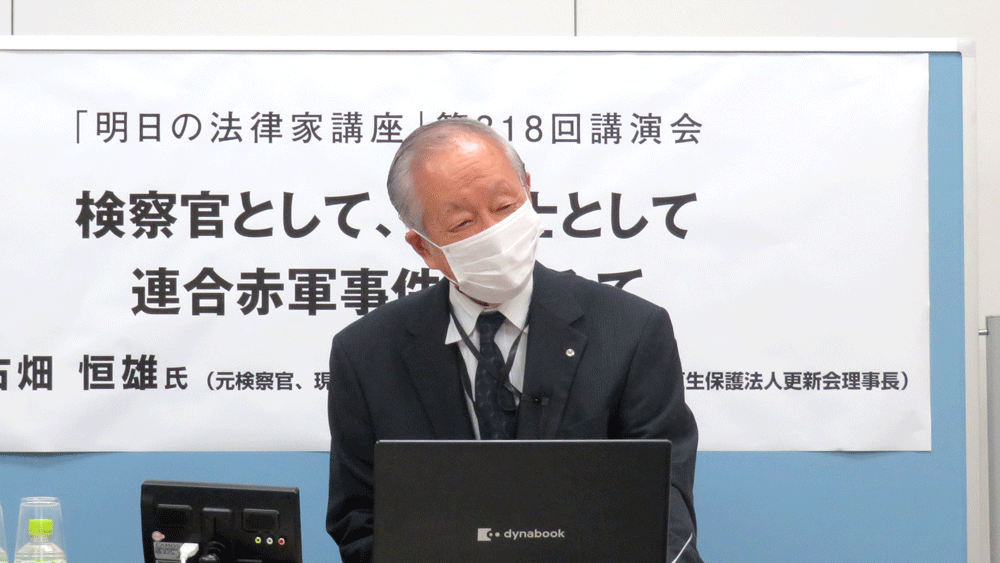古畑恒雄さんは、1960年に検事に任官されて以来、60年以上法曹界で活躍されてきた「大先輩」です。検察官、そして弁護士として多くの受刑者と向き合ってこられましたが、その姿勢は一貫して「生まれながらの犯罪者はいない」「受刑者と私とは決して別世界に住む異質な人間ではない」「罪を犯した人間も社会に復帰する権利がある」という人道的刑事政策の立場。古畑さんがその信念を深めるきっかけともなった連合赤軍のメンバーとの関わりをお話しいただき、日本の刑事政策の在り方を考えました。[2022年8月20日@渋谷本校]
連合赤軍との出会い
今から半世紀前、学生運動の最左翼として活動していた連合赤軍。彼らが起こした「あさま山荘事件」から、今年の2月で50年ということで、マスコミでは連合赤軍関連の話題が久々に報道されました。私もいくつかのメディアから取材を受け、当時のこと、またその後のメンバーの様子をお話しする機会をいただきました。
私と連合赤軍との出会いは1972年2月19日、まさに「あさま山荘事件」が起きたあの日にさかのぼります。長野地検の公安担当検事だった私は、検察庁からの緊急呼び出しで、軽井沢警察署に駆けつけました。そこにいたのは軽井沢駅で登山ナイフの不法携帯の罪で逮捕された4名の若者で、実はあさま山荘に立てこもって銃撃戦を始めた連合赤軍の別働隊のメンバーだったのです。
「あさま山荘事件」を契機に、連合赤軍内部で「総括」と称する仲間のリンチ殺人が行われていたことが判明し、群馬県の山中から12名の遺体が発掘され、日本中を震撼させました。
私は公安担当検事として、軽井沢駅で逮捕された当時23歳の男性Aの取り調べを担当しました。「職業は?」と問うと「革命戦士です」と即答したきり、あとは黙秘し、福島から駆けつけた父親の説得にも応じませんでした。それでも対話を重ねるうち次第に心を開くようになり、山岳ベースでのリンチ殺人の詳細をぽつりぽつりと語り始めました。一人ひとりを殺害していく凄惨な状況を調書に取っていくのはつらく、取り調べ室のストーブの炎が血の色に見えたものです。
少しでも世の中をよくしたいと思って、学生運動にのめり込んだこと、山岳ベースでは、幹部の命令は絶対で、逆らえば自分が殺されるという状況に追い詰められ、仲間の殺害を止めることが出来なかったことなど、Aは素直に供述するようになり、私は「革命戦士」の心の内を知るようになりました。検事と容疑者という関係ではありましたが、彼とは心が通じ合うような気がして、彼が読みたいという『カラマーゾフの兄弟』の文庫本3冊を差し入れたりしたこともあります。
事件から2ヶ月後の4月に私は東京地検に異動となり、Aと直接関わることはなくなりましたが、裁判では無期懲役の求刑に対して、懲役20年の刑が確定したことを知りました。第一審判決文中には、「被告人は当公判廷において全ての事実関係を自白して反省の資とすべく努め」「被告人なりに真摯な反省を加えている」という文言がみられ、大幅に情状が酌量されたことがうかがわれました。組織において彼は従属的な立場であったことを強調した私の調書が生かされたのかなと、少し安堵しました。
その後Aは宮城刑務所に服役、92年に実質18年弱の服役で仮釈放となりました。私は彼の社会復帰を、心から祝福しました。
Aとはその後新聞や雑誌の取材を通し、2回ほど会いました。そのとき彼は、「私は古畑さんとお会いできて本当に良かった。多くの場合検察官は敵であり、古畑さんのように敬意を払える検察官に会ったことはありません」と語ってくれました。また「オウム真理教の事件の後だったら、僕は確実に死刑だったと思う」とも。たしかに十数名もの殺人に関わったのですから、今の感覚で言えば世論も極刑を求めたでしょう。
Aは、40歳代前半で仮釈放となったため、結婚して子に恵まれ、現在は企業の責任ある立場で活躍しています。
「寄り添い弁護士」として
私は1993年最高検公判部長を最後に退官し、公証人を経て2003年に弁護士になりました。そして現在まで東京の西早稲田にある更生保護法人(※)「更新会」の理事長として、罪を犯した人の社会復帰を助ける更生保護の仕事に関わるかたわら、「寄り添い弁護士」活動を提唱、実践しています。
「寄り添い弁護士」制度とは、罪に問われて服役した元受刑者らの社会復帰を支援する制度で、出所後の就労、住居確保、家族や地域住民との交渉仲立ちなど、弁護士として生活全般のお世話をします。私がこれまでに関わった元受刑者は50人余。多くは無名ですが、角川春樹氏、鈴木宗男氏、堀江貴文氏、河井克行氏など著名人もいらっしゃいます。皆さん各界で活躍された大物ばかりで、その人間像に触れることが出来たのは得難い経験でしたが、まさか法務大臣経験者の寄り添いをすることになろうとは、思いもしませんでした。
寄り添い弁護士も更新会も、犯罪や非行をした人たちに対し、社会の中で立ち直りに向けた指導や支援を行うことにより、その再犯を防ぎ、社会復帰と自立を助けることを目的としています。30年以上検察官として訴追してきた側から、今度は防御する側へ回ったわけで、そのおかげで刑事政策を多角的に見る目が養われたと感じています。
思うに、誰しも初めから犯罪者であったはずはありません。何かの拍子で不幸にも道を踏み外したにすぎない。かくいう私でも、いつどんな事情で罪に問われる行動に走ったかも知れないと思うことがあります。そうならなかったのは、たまたま親きょうだいの愛情や、師、友人など周囲の人間関係に恵まれていただけのような気がしてなりません。受刑者と私とは決して別世界に住む異質な人間ではない。私とていつ罪に陥ったかも知れない紙一重の存在だ。そう思いつつ温かいまなざしと優しい言葉で、元受刑者に接するよう努めています。
こうした私の更生保護活動の支えとなっているのは、フランスの刑事法学者マルク・アンセルの「罪を犯した人間も社会に復帰する権利がある」という人道刑事政策の考えです。遠く20代の若手検事のころに出会ったこの考えを、その後も信念として持ち続け、弁護士となってからも受刑者たちに伴走し続けています。
※更生保護法人:1996年4月に施行された更生保護事業法により創設された法人で、更生保護施設の運営など更生保護事業を営むことを目的とする団体が法務大臣の認可を受けて設立されたもの。全国に103箇所ある。
もう一人の革命戦士
弁護士になってから、もう一人連合赤軍のメンバーと出会うことになりました。リンチ殺人事件、あさま山荘銃撃事件の実行犯として、無期懲役刑を言い渡され、千葉刑務所に服役中の吉野雅邦受刑者です。Aを通じて知り合った連合赤軍の元メンバーから、刑の確定から40年近くが過ぎた彼を仮釈放させてほしいと懇請されたのでした。
吉野受刑者の両親はすでに亡くなり、1歳年長の兄は重度の知的障害のため都内の障害者施設で暮らしており、そのため私が彼の身元引受人となりました。2~3ケ月に1回程度面会に赴き、1ヶ月に3通ほどの手紙を交換し合あううちに、彼が一途で誠実な人物であることを知りました。逮捕されたとき23歳だった紅顔の青年も今や74歳の白皙で穏やかな風貌の高齢者となり、しきりに罪を悔んでいます。
吉野受刑者については、こんなエピソードがあります。彼はリンチ殺人やあさま山荘に立てこもっての銃撃戦などで、自らの子どもを身ごもっていた恋人を含む計17人の死に関与したとして、殺人、殺人未遂、死体遺棄、強盗傷人、住居侵入、監禁などの罪に問われました。検察側は死刑を求刑しましたが、第一審の石丸俊彦裁判長(故人)は、彼の犯行の重大さは指摘しつつも、組織内での地位や力関係などを考慮し、無期懲役を言い渡しました。そして「被告人は生き続けて、その全存在をかけて罪を償ってほしい」と直接語りかけました。
石丸さんは退官後も服役中の吉野に対して、「貴兄の日々を祈っています 勇気を出してください」「明日に備えて生き続けてください」「君と社会で会えると信じ、祈っています」といった手紙を何通も出し、2007年に82歳で亡くなるまで諭し続けました。さらには「出所した暁にはこれを身につけて社会復帰して欲しい」と、妻を通じて愛用の腕時計を贈っています。
私は吉野受刑者との交流を重ねるうち、この石丸さんの気持ちが分かるような気がしてきました。彼は真っすぐに走った結果、あの事件を起こしてしまったのです。しかし、今はその非を十分に悟り、改悛の情は十分です。真面目に刑務作業に励み、反則行動もなく、ひたすら改善更生の途を歩んでいます。そして仮釈放で出所できたなら、被害者遺族を訪ね歩きたいと真剣な眼差しで訴えます。しかし今のままでは、その贖罪の機会も与えられていないのです。
さらに健康状態にも懸念があります。昨年10月にうっ血性心不全を発症し、東京都昭島市にある東日本成人矯正医療センターに入院したのです。4ヶ月後軽快した段階で、もとの刑務所に戻って軽作業に従事していますが、依然めまい、たちくらみなどが続いており、心配な状況にあります。
私は、刑事施設の長や所轄地方更生保護委員会委員長あてに仮釈放の促進をお願いする上申書を何度か提出してみましたが、残念ながら特段の反応はありません。長引く拘束によって心が折れないようにと、励まし続けるばかりです。
無期懲役の終身刑化
吉野受刑者の例を見ても分かるように、近年、無期懲役が終身刑化する傾向にあることが懸念されます。
刑法28条には「無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」という文言がありますが実際には、仮釈放の門戸は非常に狭いのです。法務省によると、2020年中の新規仮釈放者は、無期受刑者1744人中8人、わずか0.4%です。その8人の新規仮釈放者の平均受刑期間は37年6カ月です。
私が法務省保護局総務課長だった1981年は1年で67人が仮釈放されていました。80年代では模範囚であれば18年ほどで多くが仮釈放されるのが普通でしたが、90年代以降は、社会の厳罰化志向が強まり、無期刑受刑者の仮釈放の萎縮化・消極化の傾向が顕著であります。
このような傾向は、人間の人格形成の無限の可能性を否定するもので、あるべき刑事政策の姿にはほど遠いように思えてなりません。
このような無期刑受刑者の仮釈放の萎縮化、消極化に拍車をかけているのは、検察庁と法務省が出した二つの通達の存在です。
一つは1999年に最高検次長検事名で出された「マル特無期通達」と呼ばれている通達です。これは、検察官が「動機や結果が死刑事件に準ずるぐらい悪質」と判断したものを「マル特無期事件」と位置づけ、ほかの無期受刑者より長期間服役させる手続を設けたものです。
もう一つは2009年の法務省保護局長通達で、長期刑受刑者の仮釈放審理に当たって、検察官の意見を聞き、かつ被害者等については面接調査をすることなどを定めたものです。現在、検察官と被害者等が仮釈放に理解のある意見を述べることはほとんど期待できないので、仮釈放の許可を得るまでの道程は気が遠くなるなるほど険しいと言わざるを得ません。
このように検察庁・法務省は法律ではなく、内部通達による運用で、無期刑を秘かに終身刑化しています。二つの通達は、動機・結果の悪質性や危険性など客観的事情に重点を置き過ぎており、刑事収容施設法や更生保護法などが志向する対象者の改善更生という社会復帰の基本理念に逆行しているように思われてなりません。
一方で、刑罰から懲役と禁錮をなくし、新たに改善更生を目的とする拘禁刑を設けるなど、刑法が一部改正になりました。このように「懲らしめ」から「立ち直り」に軸足を置いた刑罰の大転換が行われることになったことは朗報です。
改善更生の実を挙げている吉野受刑者の「立ち直り」には、施設内処遇よりも社会内処遇がより適切だと思われます。刑法改正は3年以内の施行と見られますが、吉野受刑者に残された日々は決して多くありません。
どんな罪を犯した人でも、やがては本人の気づきと周囲の支えによって、変わり得る。私はそう信じて、「寛容と共生」の社会をつくるため、引き続き吉野受刑者に寄り添っていきたいと考えています。
*
ふるはた・つねお 1933年長野県飯田市生まれ。早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了(民事法学専攻)。1960年検事に任官。1993年最高検公判部長を最後に退官し、公証人を経て2003年弁護士。現在、更生保護法人「更新会」理事長を務めるかたわら、受刑者の「寄り添い弁護士」活動を提唱、実践している。元早稲田大学法学部非常勤講師(刑事法)。2018年に受刑者の改善更生のための活動により第9回作田明賞の優秀賞を受賞。