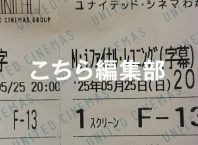はじめに
中東の衛星テレビ「アルジャジーラ」などによると、イスラエル軍は11月20日、パレスチナ自治区ガザ地区の北部ベイトラヒアにある「インドネシア病院」を攻撃し、12人が死亡、数十人が負傷したという。先に攻撃したガザ地区の「シファ病院」同様、病院敷地内にイスラム組織ハマスの地下トンネルがあるというのが理由だが、確固たる証拠は示されていない。ガザ地区ではジェノサイドと言わざるをえない攻撃のニュースが届く。
その地に立ったことがなく、専門的知識のない国や地域の人々に思いをはせるとき、できる限り現実に近づくための手掛かりになるのが、そこに暮らす人々がつむぐ物語だ。戦火のパレスチナ、ジェノサイドが続くガザ地区のニュースに接しながら、作家たちがどのような想像力を働かせて現実に抗してきたか。これまで紹介してきた作品を振り返りたい。
兵士の心の外傷
イスラエルのアリ・フォルマン監督のアニメーション映画『戦場でワルツを』(2008年イスラエル・フランス・ドイツ・米国製作)は、動画と写真をコラージュしたような作品である。
アリ・フォルマン監督の分身である主人公の記憶を遡る物語だ。
1982年、イスラエル軍が隣国、レバノンに侵攻。PLO(パレスチナ解放機構)の拠点がある西ベイルートを攻撃する。駐車している乗用車を次々に踏み潰し、住宅の一角や入口を破壊しながら我が物顔で進むイスラエル軍の戦車は、私たちがニュースで見る映像よりもリアルに迫ってくる。
この作戦に参加していたアリには、なぜか侵攻時の記憶が欠落していた。その空白を埋めるべく、彼はテルアビブに住む当時の戦友や従軍レポーター、さらにはオランダでビジネスを成功させたかつての仲間を訪ね歩く。彼らの記憶のピースを組み合わせていくことで見えてきたのは、内戦下のレバノンで行われていたパレスチナ人非戦闘員の殺害である。そのときの衝撃に耐えられず、アリの脳がおぞましい記憶を消し去ろうとした(無意識の防衛本能)のだろう。
本作品の原題「Waltz with Bashir」のBashirとは、レバノンの親イスラエル派、ファランヘ党の党首、バシール・ジェマイエルのことだ。イスラエルはバシールに軍事的な肩入れをし、レバノンをイスラエルの友好国にしようと画策する。しかし、バシールは暗殺。その報復としてファランヘ党がパレスチナ難民の大量虐殺を行うのを、イスラエル軍は間接的に支援したのである。
自分も虐殺に加担したことを認識したアリの記憶は、最後に、実写フィルムとして映し出される。瓦礫と化したレバノンのパレスチナ人難民キャンプで折り重なるように横たわる死体の数々……。今回の侵攻作戦に加わった兵士たちにも同じような心の外傷に苦しむ者が出るに違いない。
インティファーダもパレスチナ自治政府もなかった時代
『シュクラーン ぼくの友だち』(ドリット・オルガッド/鈴木出版)は、ユダヤ人のガブリエルとパレスチナ人のハミッドという12歳の少年の交流を描いた小説だ。舞台は1977年のイスラエル。インティファーダ(パレスチナ人の反イスラエル抵抗運動)も、パレスチナ自治政府もなかった時代である
ハミッドは学校に通っていない。将来の夢は医者になることだが、家が貧しいため、ユダヤ人の所有する果樹園などで働いている。
「ぼくらみたいにユダヤ人に雇われてユダヤ人の町や村で働くアラブ人は、たくさんいるけど、その逆はないってことさ」とハミッドは言う。だが、ガブリエルには、その意味がわからない。彼自身、両親、妹とともにアルゼンチンから移住して間もなかった。「子どもたちの将来を考えれば、キリスト教社会のマイノリティとして生きるよりも、同じユダヤ人の国で暮らす方がいい」という父親の判断で、ブエノスアイレスからテルアビブにきたばかりだったのである。
ガブリエルが最初に直面したのはユダヤ人からの執拗ないじめだった。イスラエルの公用語であるヘブライ語が満足に話せないガブリエルは、彼が住む団地の子どもたちの格好の標的だった。
アルゼンチンでは、こんなひどいめに遭うことはなかった――ガブリエルはすっかり塞ぎ込んでしまう。そんな彼の心を開かせたのが、団地近所の果樹園で働くハミッドだったのである。
当初、ガブリエルの両親はアラブ人少年を警戒した。「(息子には)ユダヤ人と仲良くなるのが先ではないか」とも思った。だが、勉強に意欲をもつ、まじめなハミッドとガブリエルの家族は互いに親しみを深めていく。その後、物語は爆弾テロを巡って緊張した展開になるのだが、自身も幼少時にヒトラー政権下のドイツから、イスラエル建国前のパレスチナに移住した著者オルガッドは、この物語に「パレスチナ人との共存」というメッセージを込めたのだと思う。
「シュクラーン」はガブリエルが初めて覚えたアラビア語だ。ハミッドから教えてもらった。意味は「ありがとう」である。
無国籍であるということ
イスラエルとシリアの国境に位置するゴラン高原はそもそもシリアの領土であるが、1967年の第三次中東戦争(イスラエルによる6日間の電撃作戦から「6日間戦争」とも呼ばれる)時にイスラエルに占領された。そこにはイスラエルへの帰属を拒み、パスポートには「無国籍」と記されているアラブ人が住んでいる。映画『シリアの花嫁』(2004年イスラエル・フランス・ドイツ製作/エラン・リクリス監督)はそうした無国籍一家の次女、モナが、シリアの首都ダマスカスでコメディ俳優として活躍するシリア人男性のもとへ嫁ぐまでを描く。
イスラエルとシリアは6日間戦争以降、国交を断絶している。ゆえにイスラエル占領地域に住む「無国籍」者がいったんシリア側に入れば、シリア国籍を取得することになるので、イスラエル側は帰還を認めない。モナが結婚してダマスカスに住むことは、二度と家族に会えなくなることを意味していた。
モナの父親は親シリアの立場からゴラン高原のシリアへの返還を主張し、イスラエルの警察に逮捕された経験がある。結婚式の日でも監視の対象だ。そうした政治状況に加え、モナの父と長男の不和といった家族の問題も絡みあう。本来はおめでたい席のはずなのに、人々の表情には悲しみの色が濃くなっていく。
それに追い討ちをかけるのがイスラエル・シリア双方の国境警備官の官僚主義的な対応だ。ゴラン高原が自国の領土であることを出張して譲らぬ両国によって、新婦とその家族は国境の緩衝地帯に留め置かれてしまうのである。事態を打開しようと国境を何度も往復する国際赤十字のフランス人女性も最後にはギブアップ。誰もが結婚式をあきらめかけた。
そのとき、花嫁は一人、国境を渡っていく。乾いた大地に設置された鉄条網、柵、壁。それら人為的につくられた境界線を越える純白のウェディングドレス――忘れられないラストシーンである。
人間への愛おしさを踏みにじるものは何か
イスラエルと国交をもつ数少ないアラブの国のひとつ、エジプトのアレクサンドリア警察音楽隊一行がイスラエルのバスステーションから目的地へ向かうところから映画『迷子の警察音楽隊』(2007年イスラエル・フランス製作/エラン・コリリン監督)は始まる。
音楽隊がイスラエルを訪れたのは、ある小さな町に開設されたアラブ文化センターの記念式典で演奏をするためであった。しかし、町の名前を一字間違えたばかりに、一行はホテルもない田舎町にたどり着いてしまう。
その日のバスは運行していない。さて、どうするか。
救いの手を差し伸べたのは、その町で小さな食堂を経営するユダヤ人のディナだった。彼女は8人の楽団員を自宅とレストラン、そして失業中の常連客の家に分けて泊まれるようにする。常連客の家では妻の誕生パーティが準備されていた。そこへアラブの楽団員3人が泊まりにくる。妻には面白いわけがない。ただでさえ家庭にいづらい夫は、なんとか場を盛り上げようとするが、やればやるほど、ドツボにはまる。若い楽団員は夜、イスラエルの若者と一緒に地元のディスコへ出かけ、若者に口説きのテクニックを指南したりする。
この作品でアラブとイスラエルの間の長年にわたる対立が示唆されるシーンはほんの一瞬だ。全編にわたり、一生懸命な登場人物たちのずっこけぶりは微笑ましく、「私はオマー・シャリフ(アラブ系の俳優)に憧れていた」と言う時のディナの笑顔、音楽の素晴らしさを語る生真面目な団長の額の皺に政治や宗教の違いを越えた人間らしさを感じる。そして見終わった後、人間がとても愛おしくなる。
そんな思いを容赦なく踏みにじっていく。それが戦争だ。
(芳地隆之)