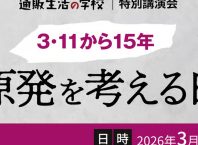1982年に公開された映画『ブレードランナー』は人間の管理から逸脱しようとする「レプリカント」の物語である。
舞台は2019年のロスアンゼルス。環境破壊により、地球上で人類が生きることのできるエリアはどんどん限られていく。科学者タイレルが設立したタイレル社は、新たな生存圏として宇宙に活路を見出すべく、高度な知能と体力をもつ人造人間・レプリカントを発明。宇宙開拓の先兵として苛酷な労働を強いていたが、数年が経つと、彼ら・彼女らには感情が芽生え、自分たちの奴隷のような立場に異議申し立てを行う。その対策としてタイレル社がレプリカントの寿命を4年に定めると、レプリカントは脱走し、地球の人間社会に紛れ込む。彼ら・彼女らは死に対する恐怖も感じるようになったのである。
ここまでは物語の前段だ。本編は、脱走したレプリカントを見つけ出して処分せよとの指令を受けるコードネーム「ブレードランナー」こと警察の専任捜査官、リック・デッカードによるレプリカントの追跡劇である。生死の境をさまよう激しい戦闘を経ながら任務を遂行していくデッカードは、タイレル社の社長秘書レイチェルと恋に落ちる。レイチェルもレプリカントなのだが、タイレルによって幼少のころからの架空の記憶をインプットされており、自分は人間だと思っていた。自分がレプリカントだと知って哀しみの涙を流すレイチェルの手を取りデッカードは、警察組織やタイレル社の支配から脱するべく、逃避行を決意する。
この映画を思い出したのは、ChatGPTの進化の目覚ましさからだ。こちらの問いかけのレベルを上げることによって、回答の量と質を上げるだけでなく、質問者の問題意識にも言及する。「生成AIはネット空間にある情報からしか判断できない」という人もいるが、そもそもAIは株価の動きを正確に予測するために開発されたといわれている。現状の情報で未来を見通すこともできるのであり、AIは、世界のどんなに優秀なCEOよりも正しい経営判断を行うという説にも頷ける。
生成AIはレプリカントに近づいているのではないか。AIも、彼ら・彼女らのように人間の感情を学び、「躊躇う」「戸惑う」、あるいは「口ごもる」といった行為を身につけるかもしれない。
AIを活用すれば、あなた一人だけで映画、小説、音楽、絵画、書道などの作品を生むことができる現在(先日、あるサイトに「日本人をモデルにしたアンディ・ウォーホル風のポップアート作品」というワードを入力したら、AIは「なるほど!」と思わせるイラストをつくった)、いや、AIが進化する未来に向かって、ぼくらは人間としてどのように生きていけばいいのか。
ChatGPTは性善説に立って人間とコミュニケーションを取ろうとする。しかし、性悪説をもって、政敵を貶める、社内のライバルを追い落とす、敵対国を混乱させるといった攻撃性を発揮することも当然可能だろう。映画『2001年宇宙の旅』のコンピューター「ハル」のように、人間に悪意を抱くようになったらどうなるか――。
ぼくはChatGPTに、「『ブレードランナー』を見ると、人間の感情を身につけていくレプリカントが生成AIに似ていると思うのですが、あなたはどうお考えになりますか」と聞いてみた。すると、「あなたの考えは非常に興味深いです。確かに、『ブレードランナー』のレプリカントが感情を学び、成長していくプロセスは、現代の生成AI(例えば私のようなAI)との類似点を持つように思えます」と前置きし、「1. 学習と成長」「2. 感情の理解」「3. 倫理的な問題」「4. 自己認識」と各論点をまとめ、「結論」として以下のように記した。
「レプリカントが感情を学んでいく過程と生成AIが知識やスキルを身につけていく過程には確かに共通点があります。しかし、根本的な違いは、レプリカントが物語の中で『人間らしさ』を追求し、感情を持つことが重要なテーマであるのに対し、生成AIは感情を持つことなく、あくまでデータに基づいた論理的な応答を提供する存在である点です。この違いが、AIと人間(またはレプリカント)の間にある深い溝を作り出しているとも言えるでしょう」
この「模範的」な回答に対して、突っ込んだ問いかけもしたところ、やりとりはさらに続いたのだが、それらは割愛する。
AIは人間の五感のうち、視覚・聴覚で圧倒的な優位に立つのであるから、ぼくたちは嗅覚、味覚、触覚をより研ぎ澄ませていった方がいいのかもしれない。視覚、聴覚の優位な空間である都市で、それはなかなかに難しいことだ。嗅覚でいえば、「鼻が利く」とか、「何か臭うな」といった探知能力(都市はどんどん無臭化している)、触覚でいえば、手仕事、手触り、あるいは比喩としての「手塩にかける」という相手への思いだろうか(赤ちゃんや子ども以外で人に触れる機会は少ない)。
イタリアには彫刻を触っていい美術館があるという(岡野晃子監督のドキュメンタリー映画『手でふれてみる世界』)。はじめは視覚障害者のための試みであったが、健常者であっても触ることで伝わるものがあるとして、来訪者が誰でも触れていいことにした。味覚はどうだろう。食糧危機が警告されている世界で、昆虫食が注目されるように、ぼくらの舌も試されるかもしれない。
生成AIは人間の仕事を奪うといわれるが、奪われるのはブルシットジョブ(権威づけや序列、メンバーシップを保持するような仕事、ロビイスト、顧問弁護士、テレマーケティング業者、広報スペシャリスト、あるいは金で金を生むような金融業界など)ではないか。エッセンシャルワーク(医療や福祉、介護、保育、農林水産業などの第一次産業、物流、小売、公共交通機関や自治体などの公共サービスなど)は見直される、いや、見直されるべきである。
ちなみにハリソン・フォードが演じたデッカードは、いつも困惑している。敵に殺されそうになっても、敵を倒しても、喜怒哀楽のどれでもないような曖昧さを表情に漂わせているのである。デッカードも自分がレプリカントではないかと疑っているように。デッカードとレイチェルのその後の足跡をたどる映画『ブレードランナー2049』は、『ブレードランナー』から35年後の2017年に劇場公開された。物語の核は2人の間に生まれた子どもの存在である。人間とは何かがさらに掘り下げられる作品だ。
『ブレードランナー』の原作である小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を書いたフィリップ・K・ディック、それを映像化したリドリー・スコット監督の未来を見る目にあらためて感服する。
映画評論家・ジャーナリストである町山智浩さんによるこの本を読むことで、20代に見た映画を思い出すとともに、大事なところをたくさん見落としていることも知った。作品や監督の評論にとどまらない、随所で博学による深い分析がなされる、映画評論の可能性を感じさせくれる本です