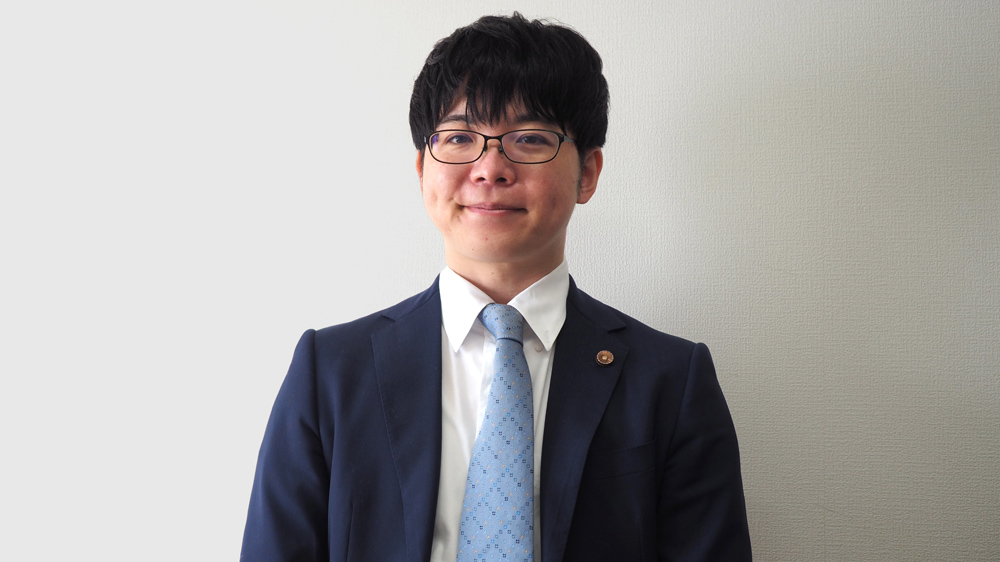今年10月、事件発生から58年が経つ「袴田事件」の再審無罪が確定しました。さらに、1986年に福井県で起こった中学生殺人事件でも再審開始が決定するなど、「冤罪」をめぐるニュースが続いています。人の一生を大きく変えてしまう冤罪は、なぜ起こるのか。どうすれば防げるのか。元裁判官で、冤罪について研究を続ける弁護士、西愛礼さんにお話を伺いました。
過去の事件から学ばなければ、また同じことが起こる
──西さんは、過去の冤罪事件について学び将来の冤罪防止につなげようとする「冤罪学」を提唱、今年12月には初めての一般書である『冤罪 なぜ人は間違えるのか』(インターナショナル新書)を上梓されました。そもそも、冤罪の問題に取り組もうと思われたきっかけは何だったのでしょうか?
西 裁判官時代、私は6人の被告人に対する無罪判決に関わった経験があります。その1件目の無罪判決を宣告したときに、ふと頭に浮かんだのが「この事件のことは、被告人本人と関係者しか知らないんだな」ということでした。
つまり、小さな事件なのでメディアも傍聴に来ていないしニュースにもならない、おそらく判例集にさえ載らない。そうすると、「無実の人が起訴されてしまった」という事実があるにもかかわらず、また同じような間違いが起きてしまう可能性があるんじゃないかと思ったんですね。
それで、裁判官室に戻ってから先輩裁判官に「こういう無罪判決の後に、なぜ誤って起訴されたかについて検証などはしないんですか?」と尋ねてみたのですが、色よい返事はもらえませんでした。もやもやした気持ちは残ったものの、まだ裁判官になって2〜3年目のときでしたし、冤罪の根本的な原因を解消するなんていう大きな課題に一人で取り組むのは難しいだろうという思いもあって、結局は尻込みしてしまったんです。
しかしその後、裁判官をやめて弁護士になった後に、ある一つの無罪判決に関わることになりました。
──ご著書の中で詳しく書かれている「プレサンス元社長冤罪事件」ですね。大手不動産会社「プレサンスコーポレーション」の社長であった山岸忍さんが、業務上横領罪の共犯として逮捕・起訴されたものの、2021年に地裁で無罪判決が出されました。
西 私はその弁護団の一員に加わっていたのですが、自分が一度尻込みして身を引いてしまった「冤罪」という問題が、めぐりめぐって目の前の人──山岸さんを苦しめていると感じずにはいられませんでした。それに、この事件も困難の末に無罪判決が取れたわけで、難しい問題だからとあきらめてはいけない、今こそ行動を起こさなくてはとも感じました。それで無罪判決の後、山岸さんに「私は、二度とこうした冤罪事件が起きないようにしたいと思います」と言ったら、山岸さんも「それは私の願いでもあります」と言ってくれたんです。
──それが「冤罪学」のスタートになったのですね。
西 冤罪を防がなくてはならないというのは、誰もが分かっていることです。でも、どうして冤罪が生まれるのか、どうすれば防げるのかを体系的に学ぶことが、当時の日本では難しいように感じました。
そこで、まずは刑事司法に携わる人たちが冤罪について学ぶことができるよう、世界中の冤罪に関する知識を集約・体系化した専門書『冤罪学 冤罪に学ぶ原因と再発防止』を出版。それを題材に、「冤罪を学び、冤罪に学ぶ」というスローガンを掲げ、過去の冤罪から教訓を得て将来の冤罪を防ぐための取り組みを進めてきました。「冤罪学」を学術的に確立させるため国内外の学会などでの発表を重ねるとともに、一般の人たちにも知ってもらうための講演会なども積極的に行っているところです。
冤罪は「この世における最大の理不尽」
──冤罪というと私たちは、犯人とされた人が有罪判決を受けて何年も服役しているケース、とりわけ今年無罪が確定した「袴田事件」のように、死刑判決があったような大事件を思い浮かべがちです。でも、実際にはそれだけを指す言葉ではないのですね。
西 実は「冤罪」という言葉は法律用語ではなく、法律家の中でもどこまでを冤罪と呼ぶかは意見が分かれるところがあります。ただ、法的な規定がない以上、国語辞典に定義を求めるしかないだろうというのが私の考えです。
国語辞典を引くと、冤罪とは「罪がないのに疑われ、また罰せられること」とあります。そこから考えても、有罪判決を受けたケースばかりでなく、一審で無罪判決が出たり、また不起訴になったりしたケースもやはり冤罪と呼ぶべきだと思います。
──事実、有罪判決にはならなくても、疑いをかけられた時点でその人の生活、人生には大きな影響がありますよね。
西 そのとおりです。また、冤罪が起こるのは殺人罪のような重い罪ばかりではありません。私が弁護を担当した中にも、スナックでの酔っ払いの喧嘩を止めに入った人が暴行の犯人だと疑われて逮捕されてしまったという事件があり、求刑は1年6月でした。結局は目撃証言が誤っていた可能性が認められて無罪となったのですが、私は自分だって喧嘩を止めに入って暴行犯人と間違えられてしまうかもしれないし、私だって暴行犯人を見間違えてしまうかもしれないと感じました。
殺人などの重大犯罪以外の冤罪事件はなかなか報道もされないので、「こういう『身近な』冤罪もあるんだよ」ということをもっと広めていく必要を感じています。
──ご著書の中で、冤罪とは「この世における最大の理不尽」だと書かれています。
西 冤罪被害者は、いわれのない罪を突然かぶせられる、それも自分が信頼していたはずの国から疑いをかけられるわけです。相手は国家権力で抗うことさえ容易ではなく、「悪魔の証明」という言葉があるように、「やっていない」ことを証明するのは非常に難しい。周りからも「そんな犯罪をするような人だったなんて」と失望されたりして、どんどん悪い方向に進んでいくことになります。
結局、その人が罪になるようなことは何もしていなかったとしても、巻き込まれただけでさまざまな被害が生じるし、後で冤罪だと明らかになっても奪われた時間は戻ってきません。ましてや死刑冤罪ともなれば、やってもいないことで国家によって命を奪われてしまうわけで、理不尽としか言いようがないと思います。
加えて、国家は正義の名の下で「悪人」を処罰して治安を維持するはずの存在ですが、冤罪の場合はその国家が無実の人を「合法的に」処罰し、それによって「見せかけの治安」を維持していることになってしまう。国家が無辜の市民を食い物にしているともいえる構図で、あまりに不健全だと言わざるを得ません。
さらに、冤罪が起こるということは、真犯人が見逃されてしまうことにもつながります。刑罰を逃れた真犯人は、それを成功体験として同じような犯罪を繰り返すかもしれない。そして、その被害者には誰もがなる可能性があります。こうしたさまざまな意味において「理不尽」なのが冤罪だと思うのです。
目指すのは「冤罪の原因を解き明かし、再発を防ぐ」こと
──そんな「最大の理不尽」が、なぜ起こってしまうのでしょうか。
西 人は必ず間違う生き物であり、人が人を裁く以上、必ず間違いは生じます。それは検察官や裁判官がどんなに優秀でも、彼らがどんなに努力したとしても絶対に避けられません。それでも、その「人は誰でも間違える」ことを前提にしたシステムを作ることで、冤罪を起きづらくすることはできるはずだと思います。
そのためにはまず、「間違う生き物」である人間を研究することで、人間はなぜ間違うのか、どんなときに間違いやすいのかといったことを明らかにする必要がある。「冤罪学」では、法律だけではなく認知心理学などの手法も取り入れることで、できるだけ客観的、科学的に「間違いが起こるメカニズム」を分析しようとしています。
──ご著書の中では、冤罪を「責任追及」ではなく「原因追究」の観点で見る、とも書かれていました。
西 もちろん、国家権力が健全さを保つ上で国民からの監視は重要ですし、誤りや不正行為に対する批判は必要です。ただ、これまでの議論はその批判が批判で終わってしまって、冤罪の原因検証や再発防止につながる学びになっていなかったところがあるのではないかと思います。
たとえば、袴田事件の無罪判決においては、捜査機関による「証拠の捏造」が認定されました。これについて、取調べをした当時の静岡県警・静岡地検や、その警察官・検察官個人を批判する声があります。それは一面で必要なことかもしれませんが、一方で「当時の静岡県警」だけの話にしてしまうと、そこから再発防止につながる学びは生まれないと思うのです。
米国の犯罪学者であるクレッシーは、不正行為は「動機」「機会」「正当化」の三つの要素が揃ったときに起こるという「不正のトライアングル」理論を提唱しています。袴田事件においても、「今のままでは有罪立証が難しい、でも『犯人』を逃がすわけにはいかない」という「動機」、やろうと思えば証拠の捏造ができてしまう「機会」、そして一家4人を惨殺した犯人に比べれば、証拠の捏造なんて大したことはない、犯人を捕まえるためにはやむを得ないと考える「正当化」、三つの要素が揃っていたのだと思うのです。
──それは、「当時の静岡県警」だけとは限らないかもしれない……。
西 そうなんです。現代の全国の捜査官にも、おそらく同じ要素が揃いうる可能性はあるでしょう。だから、捏造の当事者を処罰したり、当時の捜査官を批判したりするだけで終わってしまっては意味がない。今後、捜査の中でそうした「三要素が揃う」状態を防ぐにはどうしたらいいかを検証し──たとえば、一度押収した証拠品の管理を厳重にして「機会」をなくすなどの防止策が考えられるかもしれません──現代にも通じる教訓を導き出す必要があるのだと思います。
それに、これから冤罪を防ぐためのシステム作りを進めていくためには、法曹三者をはじめとするあらゆる人たちの協働が不可欠です。それなのに、批判だけをしていてはどんどん協働は遠のいていく。その意味でも、誰かの責任を追及することに注力するよりも、冤罪の原因を解き明かし、未来の冤罪を防ぐことを目指したいと考えています。
まずは「過去の冤罪事件の検証」から
──では、その「人は間違う」ことを前提とした、冤罪を防ぐためのシステム作りに向けて、まずどこから始める必要があるでしょうか。
西 たくさんありますが、やはりまずは過去の冤罪事件の検証だと思います。たとえば台湾では2023年12月に刑事補償法が改正され、無罪判決を受けた者への補償が決定された場合は、司法院が誤判の原因を調査・分析するという条文が加えられました。日本でも、そうした冤罪検証機関を作って、冤罪の原因の検証や教訓化を進める必要があるのではないでしょうか。
少なくとも、先ほど話に出た袴田事件とプレサンス元社長冤罪事件、そして化学メーカーの社長らが機械輸出をめぐって冤罪に巻き込まれた「大川原化工機事件」。直近だとこの三つの事件は、絶対に検証しないといけないと考えています。
──なぜですか?
西 袴田事件は、一歩間違えたら死刑が執行されていたかもしれず、しかも証拠の捏造がすでに認定されている事件です。また、プレサンス元社長冤罪事件では無罪判決後、威迫的な取調べをした特捜部の担当検察官を被告人とする刑事裁判が開かれることが決定しています。そして大川原化工機事件では、逮捕・勾留されたうちの一人が、病気治療の必要性があったにもかかわらず保釈が認められず亡くなられました。無罪判決後に提起された国家賠償訴訟では、捜査や公訴提起の違法性が認められ、国と東京都に賠償を命じる判決が出されています(2022年、東京地裁)。
国家が無実の人を罪に問うておきながらその検証すら行わないということは、国家が自分たちの誤りと向き合っていないということでもあります。まずは国家が「過ちを犯した」と認めることが、冤罪防止に向けた出発点になるのではないでしょうか。
──次の冤罪防止のために過去の事件を検証することは、検察官や裁判官にとっても、安心して仕事ができる環境づくりにつながるようにも思います。
西 海外には、検察内部で誤判についての検証を行い、誤判の可能性が認められれば検察自身が再審請求をするというシステムを設けている国もあります。そういう国では、検察官も公益の代表者として「冤罪救済の一翼を担う」という意識があるのでしょうが、日本にはそういったシステムがありません。これも国が誤りを認められない原因の一つになっているように思います。
──「検証」が出発点だとしたら、次のステップとしてはやはり法改正でしょうか。「再審」についての刑事訴訟法の条文、いわゆる「再審法」の不十分さは、多くの人が指摘しているところです。
西 そうですね。袴田事件でも、「5点の衣類」のカラー写真などの証拠開示がされたことが再審開始につながった(※)わけで、証拠開示の制度化は重要だと思います。その他、再審が認められるための厳しすぎる基準を今よりも緩やかにするなどの改正も求められるでしょう。
それとともに、早急になんとかしなくてはいけないと考えているのは「人質司法」の解消です。
※証拠開示〜再審開始につながった……現状の再審法には、再審における証拠開示についての規定がない。このため、弁護側が無罪証明のために検察が所有する証拠の開示を求めても、開示されるかどうかは裁判所の裁量に委ねられている。袴田事件でも再審請求の当初、検察は弁護側の証拠開示要求を拒んでいた
──自白をせず、無罪を主張している人ほど長期の身体拘束が認められてしまうという問題ですね。被告人自身が「人質」にされて自白を強要されているようなものだとして、国際的な批判も受けています。
西 先ほど挙げた三つの事件でも、人質司法によって長期の身体拘束と執拗な取り調べがなされたことは共通しています。無実の人が無実を主張するのは当たり前なのに、それによって身体拘束が長引くというのは、これもまた非常に理不尽ですよね。おそらく、実際には無実なのに人質司法によって罪を認めてしまった、「埋もれた冤罪」も世の中には数多くあるのだろうと思います。
もちろん、検察や裁判官の立場に立てば、そこに自白強要の意図はなく、「協力者と口裏合わせをするかもしれない」など、勾留の要件を定めた刑事訴訟法60条1項の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるというだけのことなのでしょう。でも、全体を俯瞰して見れば、証拠隠滅の可能性があるとして身体拘束をすればするほど、虚偽自白が生まれたり証人尋問を放棄せざるを得なくなったりしてあるべき証拠関係が歪んでいくのであって、自白の有無で身体拘束に差を付ける現行の法律解釈には弊害があります。今、贈賄罪で逮捕・起訴された出版社の元会長が、人質司法によって受けた苦痛に対する損害賠償を国に求めた「角川人質司法違憲訴訟」の弁護団としても活動しているのですが、このような取り組みをきっかけに状況を変えていきたいと考えています。
──冒頭、「冤罪学」を一般の人たちにも広げていきたいとおっしゃいました。法曹関係者ではない一般の市民に、冤罪をなくすためにできることはありますか。
西 冤罪をなくしていくには、一般の市民も含めたすべての人の協力が絶対に必要です。だからまずは、冤罪という問題があることを知ってほしい。たくさんの人に関心を持ってもらうことが、システムの改善につながるからです。新刊の『冤罪』も、一人でも多くの人にこの問題を知ってほしいという思いで書きました。また、身近なところで言えば、事件や刑事裁判に関するメディア報道に接するときに、「逮捕イコール有罪ではない」ということを意識してもらうのも大事だと思います。
それから、私も運営に関わっているのですが、「えん罪のない世界」を目指して活動する「イノセンス・プロジェクト・ジャパン」という冤罪救済団体があり、冤罪当事者の支援・救済活動に取り組んでいます。参加している弁護士は全員無給のボランティアですが、証拠鑑定などの費用もかかりますので、ぜひ活動を支えるサポーターになっていただけるとうれしいです。
(取材・構成/仲藤里美)
オンライン署名 ‐ 裁判で無実を訴えるほど勾留される「人質司法」を終わらせよう ‐ change.org

*
にし・よしゆき 1991年、鹿児島市生まれ。裁判官を経て弁護士に転身。後藤・しんゆう法律事務所(大阪弁護士会)所属。プレサンス元社長冤罪事件弁護団、角川人質司法違憲訴訟弁護団、日弁連再審法改正実現本部委員などを務める。イノセンス・プロジェクト・ジャパン、刑法学会・法と心理学会所属。守屋研究奨励賞・季刊刑事弁護新人賞。著書に『冤罪学 冤罪に学ぶ原因と再発防止』(日本評論社)、『冤罪 なぜ人は間違えるのか』(インターナショナル新書)がある。