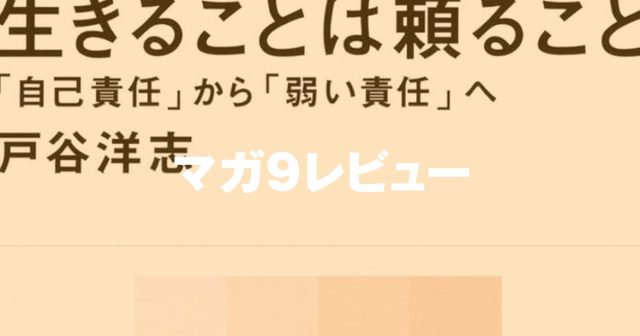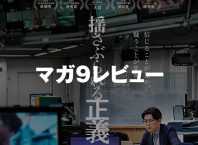日本では子どもに「人に迷惑をかけないように」と教えるけれど、インドでは「誰しも人に迷惑をかけないと生きられないのだから、他の人の迷惑も受け入れるようにしなさい」と教える。本当なのかどうか分からないけれど、どこかで聞いたことのあるそんな話を思い出した。
いつからか、いろんな場面でよく耳にするようになった言葉「自己責任」。子どもを持ったことも、離婚したことも、高い収入を得られないような仕事に就いたのも、危ない場所に出かけていったのも、十分な保険を掛けていなかったのも、すべて自分で選んだこと。だから、そのために生じた問題は、自分で解決するのが当たり前で、人に頼るなんて無責任だ──。
そこまで極端ではないにしても、「自分で決めて行動したのだから」自分で責任を持たなくてはならない、という発想は、多くの人の中に根深く存在しているのではないか。生活に困窮しても、あるいは育児や介護で追いつめられても外に助けを求めず(求めることができず)、最悪の結果に至ってしまうといった事件が過去に何度も起こっているのも、それと無関係ではないように思う。
本書で著者は、何人もの哲学者たちの思想を手がかりにしながら、そうした「自己責任論」の構造を解き明かし、それに代わるもう一つの「責任概念」を提示しようとする。
自己責任論の前提となっているのは、人間とはどこまでも自律的な存在であり、他者から影響を受けることなく自分の意志で行動することができる(少なくともそうあろうとすべきだ)という、「強い」人間観だといえる。しかし、こうした「強い責任」概念は、人が一人で抱えきれない責任を抱えざるを得なくなったとき、その人を壊してしまうことにもなりかねない(先に挙げたような事件が、まさにそうだといえるだろう)。
著者がそれに代わるものとして提示するのは、人を「一人では生きることができず、他人を頼らなければならず、傷つきやすさを抱えた」、つまりは「弱い」存在として見なす「弱い責任」概念だ。人間は、例外なく誰もが「弱い」のだから、責任を果たすためにこそ他者を頼らなくてはならない。そこに、「強い責任」からの根本的な視点の転換がある。
この転換は、社会全体がどうあるべきかということにも大きな影響を与える。「強い責任」に基づくならば、他者を頼ることは基本的に「よくない」行為であり、「社会に頼る」ための制度──すなわち社会保障も、最低限に抑えるべきだということになる(つまりは、新自由主義的な社会になる)。一方、「弱い責任」の考え方に立てば、他者を頼ることは当たり前、むしろ責任を果たすために推奨されるべき行為なのだから、誰もが安心して「頼れる」制度を整備しようということになるだろう。「責任」をどう考えるかは、私たちがどんな社会を生きたいかを考えることでもあるのだ。
著者は「はじめに」の締めくくりに、こう書いている。〈仕事・家事・育児を抱え込み、壊れそうになりながら日々を生き抜いている人は、その責任を果たすために、他者の手を借りるべきなのだ。それは恥ずかしいことではない。責任の主体として、誇り高く、胸を張って生きるべきである。〉
わたしは、誰に対してもそう声をかけられるような社会に生きたいと思う。本書は、そのぼんやりとした願いを、理論で下支えしてくれる。自己責任論や新自由主義に少しでも違和感を抱いた人に、ぜひ一読をおすすめしたい。
(西村リユ)
*