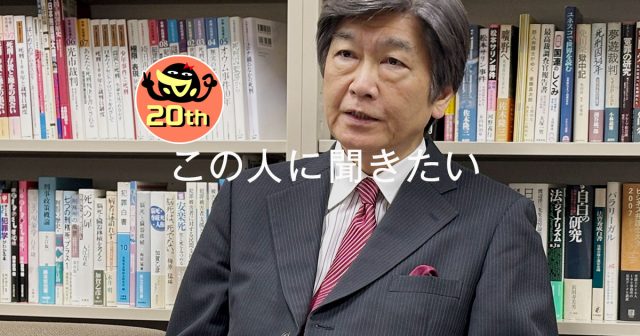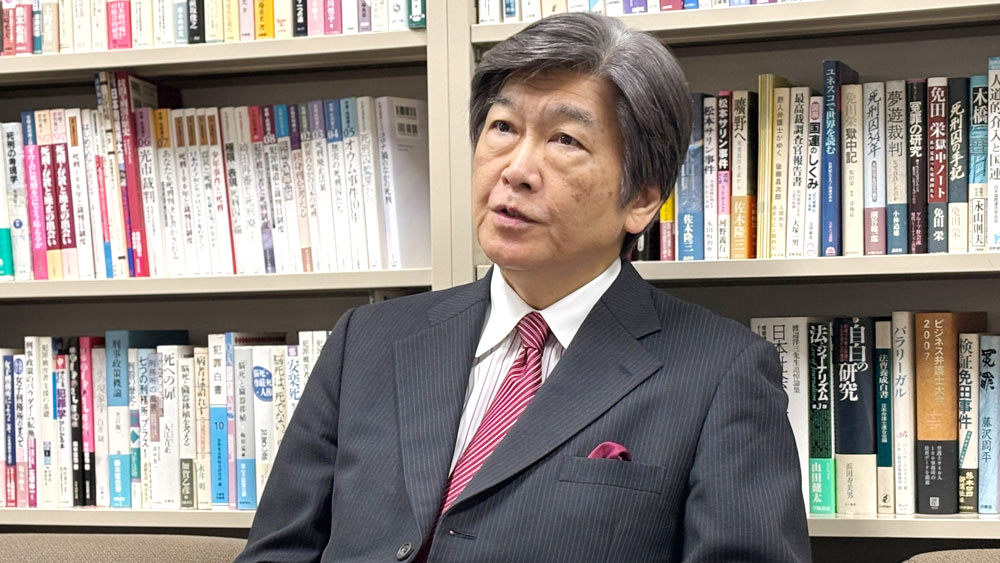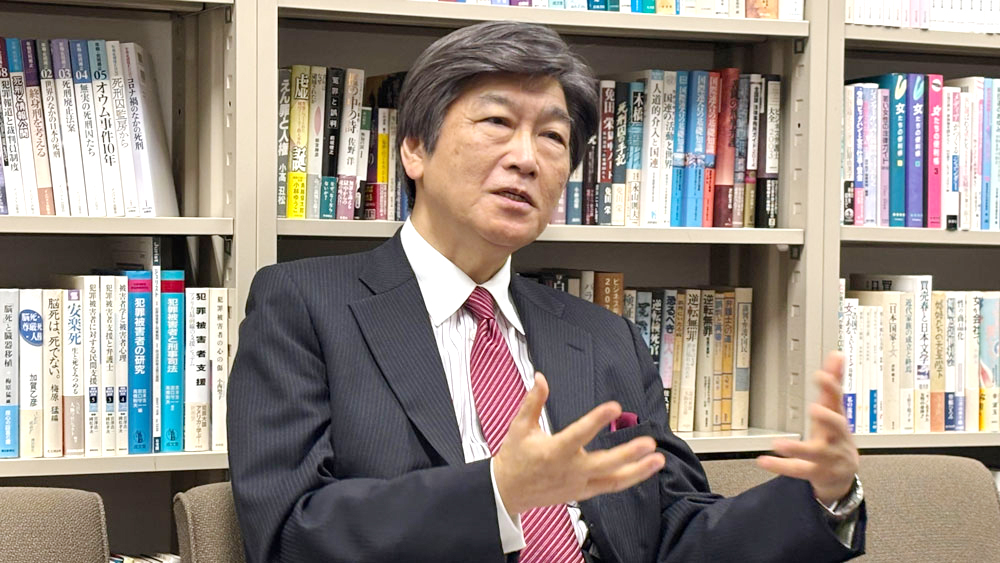「憲法と社会問題を考えるウェブマガジン」として「マガジン9」が創刊したのは2005年3月、自民党を中心に9条改憲への動きが強まっていた時期でした。そこから20年の間に、憲法をめぐる状況は、そして政治や社会のあり方はどう変わってきたのでしょうか。マガジン9創刊号から登場いただいている、「憲法の伝道師」こと伊藤真さんに振り返っていただきました。
憲法が「骨抜き」にされてきた20年
── マガジン9の創刊から、今年でちょうど20年が経ちます。「憲法」というキーワードから見たとき、どんな20年だったといえるでしょうか。
伊藤 振り返ると、戦争や紛争、災害というさまざまな危機が、目に見える具体的なかたちで私たちの前に現れてきた時期だったと感じます。
2005年から少し遡りますが、01年にNY同時多発テロ事件を発端とするアフガニスタン戦争が勃発、03年にはイラク戦争が始まります。2010年代に入って、11年に東日本大震災と福島第一原発事故。そして20年には新型コロナウイルスの感染拡大があり、22年2月にロシアのウクライナ侵攻、23年10月にはイスラエルによるガザ侵攻が起こりました。
そして、こうしたさまざまな危機に呼応するようにして、国内では明文改憲に向けた動きが絶えず続いてきました。05年には「自民党新憲法草案」が発表され、07年に憲法改正手続法(国民投票法)が成立。さらに、12年には国防軍の創設などを含む「自民党憲法改正草案」が、18年には9条への自衛隊明記や緊急事態条項創設などの「自民党改憲4項目」が発表されました。
特に第二次以降の安倍政権は9条改憲をかなり前のめりで進めようとしていましたし、その後も22年ごろには憲法審査会で国会議員の任期延長について議論が進むなど、明文改憲に向けた動きは依然として続いてきました。
── 一時は衆参両院で「改憲勢力が(改憲国民投票の国会発議に必要な)3分の2を超えた」ともいわれましたね。実際には、現在まで国会発議が行われることはありませんでしたが……。
伊藤 明文改憲を実現させるのは、実際上はそれだけ難しいということでしょう。代わって近年幅を利かせてきたのが、いわゆる解釈改憲、あるいは国会無視によって、本来憲法上は許されないような政策を押し通す、力による政治です。
13年に、当時副総理兼財務・金融相だった麻生太郎氏が「ドイツのワイマール憲法も、国民が気付かないうちにいつの間にかナチス憲法に変わっていた。あの手口に学んだらどうか」と発言したことが象徴的です。その言葉のとおり、真正面から改憲を議論せずに、しかし実質的には憲法を骨抜きにしてしまうような動きが次々に起こってきました。
── 14年7月に閣議決定された集団的自衛権行使容認と、翌年の安全保障法制成立がまず思い浮かびます。
伊藤 それだけではありません。13年12月には特定秘密保護法の強行採決がありましたし、16年には盗聴法(通信傍受法)拡大の閣議決定、17年には「共謀罪」法が閣議決定されました。さらに17年9月には、野党による臨時国会召集要求を内閣が拒否。そして岸田政権下の2022年12月には、敵基地攻撃能力の保有などを認める安保三文書が閣議決定されました。まさに麻生氏が口にしたように、「国民が気付かないうちに」憲法が実質的に変わっていた、という状態を目指して、さまざまな策が採られてきたといえるでしょう。
中でも、集団的自衛権の行使容認と安保法制の成立は、この国のかたちを大きく変えたと思います。さらにそこから、自衛隊と米軍との軍事一体化も急速に進められてきました。そのように9条がどんどん「骨抜き」にされ、際限ない軍備拡張の競争に一歩を踏み出して、「平和憲法の国」から戦争ができる「普通の国」に変わろうとしている。それが今の日本の姿なんだろうと思います。
高まった人権意識、変わり始めた司法
伊藤 一方で私は、この20年の間にはいい変化もあったと考えています。
──どんなことでしょうか。
伊藤 国民の憲法や人権などに対する意識が、以前よりもかなり高まってきたと感じることです。
#MeTooやBLM(Black Lives Matter)運動のような国際的な潮流の影響もあると思いますが、特に若い世代を中心に、多様性に対する理解が相当に進みました。気候変動など環境問題への関心も高まりましたし、「ビジネスと人権」という考え方も広まって、企業経営の上でも人権を無視できなくなってきている。もちろん選択的夫婦別姓や同性婚に対する社会の見方も、少し前とは大きく変わりました。憲法の根本的な価値である「個人の尊重」への理解が、少しずつ進んできていると言い換えてもいいかもしれません。
── たしかに、SDGsやLGBTQ、DEIといった言葉がメディアなどで取り上げられることも珍しくなくなりました。
伊藤 また、昨年に再審無罪判決が出された袴田事件などを通じて、冤罪や再審法、人質司法といった刑事手続きにおける人権問題に対する関心も、以前よりは高まっていると感じています。警察や検察、国家権力というのは信頼の対象ではなく、常に監視し、批判しなければいけないものだということを理解する人たちが、少しずつではありますが増えてきたのではないでしょうか。
第3代アメリカ大統領のトーマス・ジェファーソンが「信頼は常に専制の親である。自由な政府は、国民の信頼ではなく猜疑に基づいて建設される」と言っているように、国家権力は信頼の対象ではなく監視批判の対象だというのは、立憲主義の考え方そのものでもあります。そのことを、少なからぬ人たちが理解しつつあるように感じるのです。
そして、こうした国民の意識の変化を受けて、司法の場にも変化が現れてきていると思います。
── 昨年から今年にかけても、同性婚を認めない民法は違憲だとする判決が各地の高等裁判所で相次ぎましたね。
伊藤 23年には最高裁判所でも、経済産業省のトランスジェンダーの職員に対するトイレ使用制限を違法とする判決や、トランスジェンダーの性別変更における生殖不能要件は違憲とする判決が出されました。翌24年の旧優生保護法を違憲として国に賠償を命じた判決もそうですが、個人の尊重や幸福追求権を定めた憲法13条を根拠とした違憲判決を、最高裁が出すようになっている。これは少し前までは、まったくなかったことです。
また、私が関わった裁判では23年11月、いったん内定していた映画への助成金を、日本芸術文化振興会(国の外郭団体)が出演者の薬物事件を理由に不交付としたのは違法だとする最高裁判決が出ました。これなども、憲法21条に定められた表現の自由がどれほど大切なものかを、明確に示してくれた判決だと思います。
同性婚訴訟の判決も含め、国民の人権、特にジェンダー平等や多様性に関して、司法が国民の声を吸い上げ、それを判決に反映させるという大きな流れができ始めているように感じます。これも、この20年の変化として評価していいところではないでしょうか。
── 一方で、伊藤先生も関わっておられる安保法制違憲訴訟や「一人一票」実現訴訟(※)、また沖縄・辺野古の米軍基地建設をめぐる訴訟、選択的夫婦別姓についての訴訟など、司法が明確な判断を示さず、及び腰になっているように見えるケースもあります。何が違うのでしょう?
(※)「一人一票」実現訴訟:選挙区の区割りによって一票の価値に大きな格差があることは憲法に規定されている国民主権原理に反するとして、選挙の無効・やり直しを求め全国で弁護士らが起こしている訴訟
伊藤 たしかに、直接的に政治に関わる問題、政府にとって都合の悪い問題に対しては、なかなか司法も明確に「憲法違反だ」と言ってくれないのが現状です。「一人一票」実現訴訟についても、一人一票が本来当然の原則であり、一票に2倍以上の格差があるということは一人の人が2票持っているのと同じだから許されないという議論であったはずが、「2倍をわずかに超える程度だから許容範囲だ」という話にすり替えられてしまっている。国会での選挙制度改革は遅々として進まず、司法もそこにメスを入れようとしないという状況が続いているわけです。
あともう一つは、国民があまり関心を持っていない問題には司法も積極的に踏み込まないという面もあるのではないかと思います。辺野古基地建設をめぐる訴訟では沖縄県敗訴の判決が続きましたが、そこには「本土」の人間の沖縄に対する視線、つまりは無関心さが反映されているところがあるのではないでしょうか。
政府が臨時国会召集要求に応じなかったのは憲法違反だとして国が訴えられた裁判も、最高裁は憲法判断を示さず上告を退けましたが、これも国民やメディアの関心が高いとは言えない問題ですね。安保法制違憲訴訟で憲法判断が回避され続けていることにしても、成立前のような「反対」の声の盛り上がりが、国民の間からもはや失われてしまっていることが影響しているのではないかと思います。
── 逆にいえば、国民の関心が高まれば、司法の判断が変わってくる可能性もあるということですか。
伊藤 もちろんです。特に最高裁は、国民の意識変化に敏感に反応して対応する組織ですから、時代が変わった、国民の意識が変わったということになれば、昔の判決にいつまでもしがみつくことはありません。たとえば13年に違憲判決が出た婚外子の相続差別問題(※)なども、長い間「違憲ではない」として放置されていた問題が、国民世論の変化を受けて「違憲だ」と判断されるに至ったわけです。
選択的夫婦別姓にしても、21年に最高裁で示された判断は「(婚姻にあたって同姓を義務づける民法は)違憲とはいえない」でしたが、今後世の中の「夫婦別姓が認められないとあまりにも不都合が大きい」という声がもっと大きくなれば、次は違う判断へと動いていく可能性はあるし、そうならないといけないと思います。
※婚外子の相続差別問題:結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分は法律婚による子(嫡出子)の半分とされていた民法の規定について、最高裁は13年9月、法の下の平等に反しており違憲とする判決を出した。1995年には同様の問題について最高裁で合憲判決が出ていた
「いい方向への変化」を加速させるには
── 20年の間に、いい方向への変化もあり、そうではない変化もあったということですね。
伊藤 そうです。大事なのは、その「いい方向への変化」をもっと加速させていくこと。そして悪い方向への変化に呑み込まれないようにすることだと思います。
── そのために、たとえばどんなことが必要だと思われますか。
伊藤 まずは、日本という国が今どういう方向に向かおうとしているのか、事実をしっかりと認識することだと思います。
9条に関していえば、軍事力増強や日米同盟強化を主張する政治家たちは、「抑止力を高めることが日本の安全を守ること」だとは言っても、その抑止が破れたときの話には触れようとしません。抑止とは「戦争する能力と意思がある」ことを相手に見せつけることで成立するものですから、抑止が破れるということはすなわち戦争になるということ。そのとき食糧もエネルギーも外国に依存しているこの国で、国民の生命や財産がどれほど甚大な被害を受けるのかといった議論はほとんどなされてこなかったように思います。「軍事力増強」を支持する人たちもまた、「戦争になれば、自分も巻き込まれて死ぬかもしれない」という現実を、どこまで想像できているのでしょうか。
「日米の軍事一体化によって安全が高まる」ような言説も当然のように語られることがありますが、これもあまりにも「同盟のジレンマ」を軽視した見方だと思います。
── 同盟相手に見棄てられるリスクを恐れて同盟を強化すればするほど、相手国の戦争に巻き込まれるリスクが高まってしまうという「ジレンマ」ですね。
伊藤 今の日本はまさにそこに陥っているように思います。「いざというときにアメリカに守ってもらう」ために、軍事面における日米一体化を進めようとして、結果的にアメリカの戦争に巻き込まれるリスクを自ら高めてしまっているのではないかと感じるのです。
そうした事実をしっかりと見据えた上で、危機の時代だからこそ「軍事力を増強しないと危ない」といった煽りに乗せられてしまうのではなく、9条や憲法前文の理念に立ち返ってみる。そうして「本当に軍事力に頼るだけでいいのだろうか、アメリカ一辺倒の外交政策でいいんだろうか」ということを、改めて考えてみる必要があるんだと思います。
それと同時に、先ほども触れた多様性や個人の尊重への理解を深め、自分と異なる考えを持つ他者とどううまく共存していくかを考えることも必要でしょう。エコーチェンバーやフィルターバブルといった言葉があるように、現代はSNSなどの発達によってかえって自分と異なる多様な意見に触れにくくなってしまっている。だからこそ、意識して多様な意見に触れ、違いを認め合いながら自分でしっかりと考えて主体的に行動する、おかしいと思ったことがあればきちんと声をあげるという、一人ひとりの心構えがこれまで以上に問われる時代になっているんだと思います。
その意味で、教育も重要だと考えています。
── 教育ですか。
伊藤 人権や憲法への意識は以前よりも高まっていると言いましたが、その一方で主権者教育や人権教育という面については、まだまだと言わざるを得ないと思います。
よく講演などでご紹介するのですが、NHK放送文化研究所が5年ごとに実施している世論調査によると、「思っていることを世間に発表する(表現の自由)」ことを憲法上の権利だと正しく認識している人は、2018年の調査で3割を切っています。しかも、過去の調査と比較するとその割合が徐々に減少している。一方、権利ではなく義務であるはずの「税金を納める」行為については、2018年の調査で「国民の権利」だと回答した人が4割以上。こちらは過去の調査より増加しています。つまり、権利と義務の区別がついていなかったり、どうでもいいと思っていたりする人たちがどんどん増えているのが、日本の実態なのです。
多くの人たちが、国家の権利や義務、立憲主義といった国家と国民の関係の本質についてほとんど教わることがないまま大人になっている。これは本当に、根深い問題だと思います。
── 戦後80年を迎え、若い世代への戦争体験の継承も課題だと言われますね。
伊藤 でも私は、戦争を知らない世代が増えるのはいいことだと思っています。それだけ長い間、日本は戦争をしてこなかったということなのですから。いずれは、今の私たちが「昔、元寇っていうのがあったらしいよ」と話すくらいの感覚で(笑)、「昔、日本って戦争してたことあったらしいよ」というふうに話せるようになればいいなと思います。
もちろん、本当にそうなっていくためには、まだ直接戦争体験を聞くことができた私たちが「絶対に戦争はやってはならない」ということを、しっかりと次の世代に伝えていく必要があるでしょう。憲法前文には「われらとわれらの子孫のために」この憲法を確定する、という一節があります。先の大戦で戦火を逃れて生き延びた人たちは、自分たちのためだけでなく子孫のためにもこの憲法を作った。そのことを今、もう一度思い起こしてみる必要があるのではないでしょうか。
(取材・構成/仲藤里美)
*
いとう・まこと 「伊藤塾」塾長、弁護士、法学館憲法研究所所長。司法試験合格後、真の法律家の育成を目指し、司法試験の受験指導にあたる。日本国憲法の理念を伝える伝道師として、講演・執筆活動を精力的に行う。日弁連憲法問題対策副本部長、安保法制違憲訴訟全国ネットワーク代表、弁護士として「1人1票実現運動と裁判」にも取り組む。『安保法制違憲訴訟』(寺井一弘氏との共著、日本評論社)、『9条の挑戦 非軍事中立戦略のリアリズム』(神原元氏、布施祐仁氏との共著、大月書店)など著書多数。