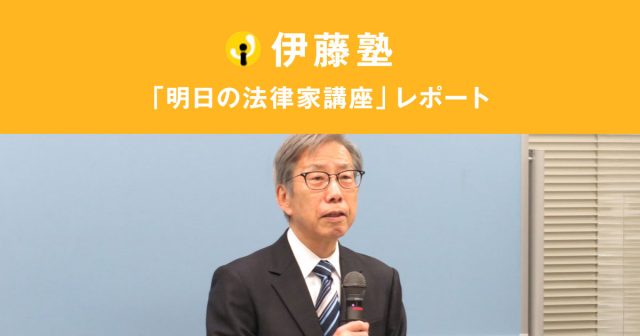同性どうしの結婚が認められていないことが憲法に違反するか否かを争う同性婚訴訟については、今日多くの裁判所で違憲ないし違憲状態であるという判断が出ています。ただ、その判断の根拠を憲法のどの条文に求めるかという点についてはバラバラで、この問題の憲法判断のアプローチの難しさを示しています。そこで今講座では、同性婚法制度化の障壁は何か、「憲法24条の婚姻には同性婚も含む」とする憲法解釈は可能なのかについて、元最高裁判事の千葉勝美弁護士にお話しいただきました。[2025年3月25日@東京校]
同性婚ができないことで生じる問題とは
今日、同性婚の法制化は世界的な潮流となっていますが、日本ではいまだに実現していません。その理由の最たるものは「かつての同性愛についての理解」にあるのではないでしょうか。かつて同性愛は「治療の対象となる精神疾患」であるという誤解、「性の秩序を乱す忌み嫌うべきもの」という偏見が広がっており、同性愛の意味や本質、価値についての正しい理解が欠如していました。
そうした認識を前提に、明治民法では、婚姻は「男女における精神的肉体的な結びつきにより永続的な共同生活を目的とする道徳上及び風俗上の要求に合致した社会的結合関係」であるとされていました。昭和22年に改正された現在の民法でも、婚姻は「男女の精神的肉体的結合」とされ、同性婚が法制度として認められる余地はありませんでした。
しかし1973年以降、アメリカの精神医学会や世界保健機構などによって誤解や偏見は否定され、同性愛は精神疾患ではないという認識が広まりました。その結果今日では、ほとんどの場合、性的指向は人生の初期あるいは出生前に決定されており、本人の意思により選択、変更しうるものではないこと、異性に向くことが多いが、およそ10%弱の人は同性に向くということが分かってきました。
では、日本で同性どうしが結婚できないことで、どのような問題が生じているのでしょう。婚姻によって保障される法的利益について考えてみます。一つは遺産相続などに代表される経済的利益で、およそ30程度あると言われています。また、結婚していれば配偶者と実子ないし養子の共同親権を持つことができる、配偶者に対する重要な医療行為に同意できるなどの社会的利益もあります。
もう一つ忘れてならないのは精神的利益です。「精神的・肉体的結合」という婚姻制度における当事者としての人格的で根源的な永続性のある結びつきの喜び、日々の精神的な充実感、相互の助け合いによる一種の運命共同体的な安心感、相互の心からの尊敬と信頼関係の素晴らしさ──そうした婚姻の精神的利益を、同性愛者というだけで享受できない状態に置かれている。これは深刻な問題です。憲法13条の幸福追求権など人格的生存権に必要な基本的権利が認められていない状態、すなわち個人の尊厳が損なわれている状態に置かれていると言えるのです。
個人主義的自由権思想の広がりとともに
今日の婚姻制度は異性婚を前提にしています。これは社会の多数派によって構築され、広く政治的、社会的、歴史的、伝統的に承認され親しまれてきた制度です。それを変えるとなると、違和感、抵抗感、拒否感が出てくるのは当然のことです。婚姻は「子を産み育てること」が目的の一つなのだから、自然妊娠が期待できない同性カップルは当てはまらないのではないか──。従来の結婚観からすれば、そう考える人がいても不思議なことではありません。
しかし、近代社会の到来と共に、個人の自由を尊重すべきという個人主義的自由権思想が世界的に広がってきました。その流れの中で同性愛者を含む性的マイノリティの人々は、従前の社会の多数派が作った社会制度に縛られることなく、自分自身の感覚、指向、価値観に従って生きていきたいと声を上げるようになってきたのです。
性的マイノリティの人々は少数派であっても厳然と存在し、多くの「普通の人々」と同じように暮らしています。好きな人と結婚して、経済的社会的精神的な利益を得て、共に安心して生きていきたいと願うのは当然のことです。彼らを婚姻によるかけがえのない個人の尊厳の喜びを奪われた状態、すなわち憲法13条、14条が謳う基本的人権が損なわれた状態に放置しておいていいはずはありません。
たとえ少数者の権利の問題であっても、それが憲法的な価値のある人権である場合は、社会全体で保障する。それこそが法の支配が貫かれた価値ある社会です。今日同性婚法制化を支持する世論は、「賛成」「どちらかといえば賛成」を合わせて7割に達しています。この現状はまさに個人主義的な自由権思想が社会に支持されていることの証左です。新しい風はすでに私たちの日常に吹いているのです。
政治的社会的閉塞状況を、司法が克服する
同性婚の法制化は立法がやるべきことであり、立法府もその必要性や合理性については十分に理解しているはずです。ただ立法は選挙を意識するがゆえに、従前の社会制度を支えてきた多数派の利益や価値観を揺るがすような新しい制度にはなかなか踏み出せない。
政治的社会的に、動かなければと分かっているけれど動けない。これを私は「政治的社会的閉塞状況」と呼んでいます。現時点での立法府の党派的な状況を見ますと、この閉塞状況が急に解消することは期待できそうにありません。ならば多数決原理が支配する立法でなく、法原理機関である司法に委ねようではないかということで、同性婚法制化について国民の意識は、立法から司法へシフトしてきているように思われます。
そうであれば、司法が性的少数者の問題に前向きに対処し、彼らの人権を保障するという新しい価値観を示したとしても、社会的政治的に大きな分断を生じさせる状況にはならないのではないか。国民はむしろそれを期待しているのではないか、そんな気がします。
こうした政治的社会的閉塞状況を司法が克服した例はアメリカにあります。例えば2015年6月26日に言い渡されたアメリカ連邦最高裁でのオバーゲフェル判決。アメリカは建国以来、婚姻制度が州ごとに違っていたのですが、この判決によって「同性婚は憲法上の権利だ」と初めて全州で認められました。
あるいは1953年から69年にかけて連邦最高裁長官を務めたアール・ウォーレンが、人種分離教育を違憲とする判決や、選挙における一票の較差を否定する判決などを次々に出し、「ウォーレン・コートの平等主義革命」と呼ばれた司法の決断も歴史的な出来事でした。当時のアメリカは政治的、経済的、文化的にも未曾有の繁栄を謳歌していたにもかかわらず、人種差別や投票価値較差など自由主義陣営のリーダーとしては恥ずべき問題を抱え、政治的社会的閉塞状況に陥っていました。その解決を司法に委ねようという国民の期待を読みとった司法が積極的な判決を出したと言えるのではないでしょうか。
日本にも同様の例はあります。例えば1976年(昭和51年)4月14日、衆議院議員選挙の選挙区での投票価値の較差が選挙無効事由となるとした最高裁定数訴訟判決大法廷判決です。
定数訴訟判決の出た昭和51年といえば、高度経済成長を経験し、国民所得は向上し、一億総中流といわれた時代です。各人の価値観やライフスタイルが多様化し、それを実現させたいという意欲が高まっていました。
他方で、公害や交通事故の増大、都市と地方の格差拡大、ロッキード事件をはじめとする政治の腐敗など政治的社会的な問題が噴出し、国民の多くが自分の価値観や問題意識、意見が適切に政治に反映されていないという閉塞感が蔓延していました。そうした政治的社会的閉塞状況を背景とし、政治的思惑とは離れた司法にこそ課題を克服する使命があるとの国民の期待に応える形で、司法が英断を下したのではと、私は考えています。
これらアメリカおよび日本の例は、マイノリティの人々の人権に関わっているなど、多数決原理が支配する立法では救済することが難しい問題でした。それゆえに、法原理機関である司法の思い切った判断が求められた。こうした先例からも、日本における性的少数者の問題、同性婚法制化については、まさに今司法が乗り出して政治的社会的閉塞状況を打破し、彼らの損なわれている尊厳を救済する時が来ていると言っても過言ではないでしょう。まさに「時、きたれり」です。
24条は同性婚を排除していないという憲法解釈を
もう一つ、同性婚法制化の障壁になっているのが憲法24条1項、2項です。24条は婚姻に特化した条文で、明治民法の家制度と決別して「婚姻は両性の合意のみで成立する」と、新しい人権の理念に沿った婚姻制度を謳っています。
その理念自体は素晴らしく、同性婚法制化の壁にはならないのですが、問題は文言です。条文の中にある「両性」とか「夫婦」という文言を辞書的に解釈すれば、男女のカップルすなわち異性婚と解され、我が国の婚姻制度は異性婚であることが憲法秩序であると読めてしまいます。
これを乗り越えるために、個人の幸福追求権を保障している憲法13条や、法の下の平等を謳っている14条で対応すべきという見解があります。ですが13条、14条は適用場面を限定しない一般規定であり、24条は婚姻に特化した特別規定なので、婚姻制度については24条が優先されてしまう。「幸福追求権、法の下の平等はもちろん同性愛者にも認められるべきだが、婚姻については24条で異性同士がするものとされている。だから同性婚を認めないことは13条、14条違反にはならない」というわけです。
ですから24条は異性婚だけでなく同性婚も含む、少なくとも同性婚を排除していないという解釈が、どうしても必要になります。
そこで24条の文言を乗り越え同性婚を含ませるための憲法解釈、アプローチを私なりに考えました。
〈現行憲法制定当時、同性愛は精神疾患であり治療の対象であると誤解されていて、性の秩序を損なうものとの偏見が支配的であった。そのため憲法制定権者には、そもそも「婚姻には同性婚も選択肢としてある」という認識すらなかった。24条の「両性」「夫婦」という文言も、あえて異性どうしという意味合いを込めたものでなく、当時普通に考えられていた「婚姻の当事者」を指す文言として用いられたにすぎない。「両性」「夫婦」はそれぞれ「当事者」「双方」という意味で使用したものであって、婚姻当事者の性についてはそもそも問題意識すらなく、異性同士に限るという趣旨は伺えず、同性婚を排除する意図は全くなかった。〉
このような憲法制定権者の意図に沿った解釈を採ることで、24条に同性婚を含めることは可能になると考えます。
24条は同性婚を排除していない、さらに、同性婚も含んだものであるということが確認できれば、同性婚法制化がなされていないという立法不作為は、個人の尊厳を損ない、13条、14条にも違反するという判断が容易に導かれます。
違憲判決が出ると、国会は同性婚法制化の義務を負うことになりますが、その際に気を付けなくてはいけないのは「同性婚には自然生殖機能がないのだから、異性婚と同じには扱えない。ならば異性婚の例外としての同性婚制度という別枠を作ったらどうか」という話になりかねないことです。しかし、そうした例外的な制度を作って終わりにしてしまったらどうなるか。「同性婚は“普通の結婚”とは違う例外的なもの」と思われて、同性愛者、同性婚に対する差別が広がってしまうのではないでしょうか。
そのように、憲法に同性婚を婚姻だとする規定はないとしてあとは立法裁量に任せてしまうと、なかなか審議が進まなかったり、不十分な制度化に終わったりするおそれがあります。ですからやはり24条の婚姻には同性婚も含まれるという憲法解釈を明確にしておく必要があるのです。
同性愛は、異性愛と変わらない個人の尊厳として守られるべきであり、世論の7割が容認している今、24条の婚姻には同性婚も含まれるという憲法解釈は妥当であり、国民の支持も得られるものと考えます。
そのことをお伝えして、近い将来示されるであろう最高裁大法廷判断への期待をこめたメッセージといたします。
*
ちば・かつみ 1970年東京大学法学部卒業。1972年判事補任官後、東京地裁判事、最高裁秘書課長・広報課長、民事局長・行政局長、最高裁首席調査官等を経て、2009年12月から2016年8月まで最高裁判事。同年10月弁護士登録。著書に『違憲審査~その焦点の定め方』(有斐閣)、『憲法判例と裁判官の視線~その先に見ていた世界』(有斐閣)、『判事がメガネをはずすとき~最高裁判事が見続けてきた世界』(日本評論社)、『同性婚と司法』(岩波新書)など。