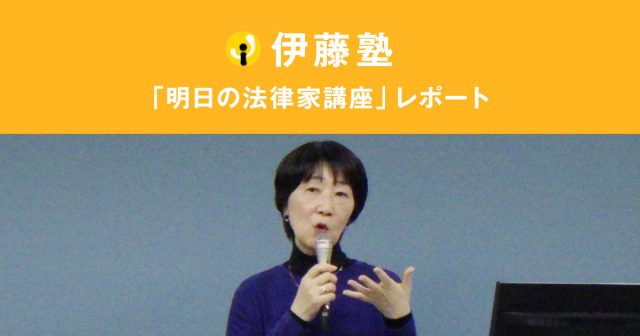米軍が長期にわたって駐留している沖縄では、米兵による性暴力事件が後を絶ちません。しかも近年、日本政府は事件を把握していたにもかかわらず沖縄県には知らされず、公表もされていなかったケースが相次いで明らかになり、問題になっています。軍隊の駐留と性暴力との間にはどのような関係があるのか? ジェンダーの視点から軍隊の長期駐留の問題について研究を続ける秋林こずえさんにお話しいただきました。[2025年1月25日@東京本校]
紛争の戦略・戦術としての性暴力
本日のテーマは「軍隊と性暴力」ですが、そのお話に入る前に、「紛争下の性暴力」について国際社会がどのように認識しているのかを見ておきたいと思います。国連は紛争下の性暴力防止を重要な課題と位置づけており、その定義も「紛争に直接・間接に関連して、女性・男性・女児・男児に対して行われる強姦、性奴隷、強制売春、強制妊娠、強制中絶、強制不妊、強制結婚やそれらと同等に重篤な性暴力」と、かなり広く捉えられるようになっています。
重要なのは、紛争下の性暴力とは「防ぐことが可能」で、「国際人権法や国際刑事法で処罰できる」ものであり、根絶を目指すべきだと考えられていることです。そして、紛争下の性暴力がなくならない根本の原因には、きちんと処罰されてこなかったこと、つまり不処罰の問題があると指摘されています。
さらにもう一つ、「恥じるべきは加害者であり、被害者ではない」という点も強調されています。紛争時に限らず性暴力の被害者は、「逃げようと思えば逃げられたのではないか」「自分から進んで応じたのではないか」などと言われることがよくあります。そうではなく、「問題にすべきは被害者でなく加害者だ」ということを、繰り返し言わねばならないと考えられているのです。
2010年には国連の中に「紛争下の性暴力担当事務総長特別代表事務所」が開設され、毎年、安全保障理事会に報告書を出しています。日本政府もこの問題を非常に重視しており、特別代表事務所に対して、多額の資金を拠出しています。
隠蔽される米軍の性暴力──沖縄の事例から
一方で、日本政府は国内、具体的には沖縄で起きている米軍による性犯罪には全く冷淡です。2023年12月からの1年間で、沖縄では米兵による性犯罪が5件起きていたにもかかわらず、沖縄県には知らされず隠蔽されていたことが昨年、明らかになりました。
その一つが、2023年12月、嘉手納基地所属の空軍伍長が16歳未満の少女を自宅に誘拐し性的暴行を加えた事件です。被害者の家族の通報により沖縄県警が米軍に容疑者を照会、空軍嘉手納基地内で任意捜査。2024年3月27日に起訴され、身柄は日本側に引き渡されましたが、那覇地裁の決定により保釈されました。事件から半年過ぎた6月25日、沖縄の放送局が裁判期日表を調べていて偶然この事件を見つけ、報道しました。沖縄県はその報道で初めて事件を知ることとなりました。
この事件について、林芳正官房長官は6月27日の記者会見で「被害者の名誉、プライバシーに配慮して公表しなかった」と述べています。この「被害者の名誉」とはどういう事でしょうか。性暴力の被害にあったことと被害者の名誉は、どう関係するのでしょうか。先ほども強調したように、恥ずべきは加害者であって被害者ではない。「被害者の名誉」を隠蔽の口実にさせてはなりません。また宮川学・外務省沖縄大使は「政治問題化を懸念して公表しなかった」とも述べています。
その後、7月に行われた第1回公判で被告は「(16歳未満ではなく)18歳と確認した、合意があった」と無罪を主張。そのため第2回公判で被害者の少女が出廷して証言することになりました。当時のことを微に入り細に入り繰り返し聞かれ、加害者がいる法廷で衝立越しに5時間も証言することを余儀なくされたのです。そこで彼女は自分が16歳未満であることを伝え、「やめて」「ストップ」と不同意の意思をはっきり示したと証言しました。被告は第3回公判でその証言を「作り話だ」と否定しましたが、12月13日に懲役5年の有罪判決が出ました。
軍事優先のための隠蔽
沖縄の「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会(行動する女たちの会)」では米兵による女性への性犯罪を調べ、記録する活動を1996年から続けていて、私も参加しています。その記録から、2021年までは県内で起きた事件は容疑者が逮捕された時点で公表されていたけれど、2023年からは公表されていないことがわかりました。
最近の政治の動きを見てみると、2024年4月には岸田文雄首相(当時)が訪米、「日米同盟の新たな高みに」と同盟強化をうたった共同声明を出しています。沖縄での事件のことには全く触れていません。
琉球弧(南西諸島)の軍事要塞化も背景にあるでしょう。5月17日にはエマニュエル駐日アメリカ大使が与那国島と石垣島を訪問、与那国町長と面会、その町政を評価しました。辺野古の新基地建設をめぐって国と対立している沖縄県を飛び越して、自衛隊の駐屯に積極的な与那国町長と直接会い、軍事強化を推し進める一方、自分の国の軍隊の構成員による性暴力に関して、まったく触れもしなかったのです。
また同年6月23日、沖縄「慰霊の日」の式典には岸田首相(当時)と上川陽子外相(当時)も出席しています。この1ヶ月ほど前の5月26日にも米海兵隊員による女性に対する性的暴行事件が起きていたのですが、ここでも何も言っていません。
これらの事実を顧みると、林官房長官の発言にある「被害者のプライバシー保護」のために公表しなかったというのは言い訳で、日米同盟の維持、軍事強化を優先したというのが本当のところでしょう。
こうした米兵による性暴力と、それを隠蔽する日本政府に対して、沖縄では抗議の声が高まっています。2024年12月22日、沖縄市で大規模な抗議集会が開かれ、約2500名が参加しました。また性暴力の被害者が声を上げ、それに連帯する人々が花を持って集まる「フラワーデモ」も、継続的に行われています。
また、このような沖縄における性犯罪の隠蔽、不処罰の原因の一つとして指摘されるのが日米地位協定です。アメリカは駐留米軍を守ることを目的に、軍隊を置いている約100の国・地域と地位協定を結んでおり、日米の地位協定は1960年に締結されました。その17条に刑事裁判権についての定めがあり、公務中の犯罪に関しては米軍、公務外であれば日本側に一次裁判権があると明記されています。
ところが、実はそれとは別に、地位協定の前身である「日米行政協定」の時代から引き継がれている「密約」があったこと、それによって「著しく重要な場合以外は日本は一次裁判権を行使しない」と合意されていたこともすでに明らかにされています。さらに、米軍の裁判権を最大限に行使するために「日本側が不起訴にする」「米軍に捜査させる」などのさまざまな戦略がとられてきたという研究論文もあります。
実際に、過去の米兵による性暴力事件を見ても、不起訴になったケースや、日本側が米軍基地内で任意捜査をしたものの、どのくらいきちんと捜査されたのかよく分からないケースがいくつもあります。日米地位協定の条文を見るだけでなく、実際にそれがどう運用されているのか、されていないのかに注目すると、日米の力関係が見えてきます。そして軍事力強化が性暴力被害者の被害からの回復や尊厳よりも優先されてきたこともわかるのではないでしょうか。
軍隊は構造的な暴力
沖縄における軍隊の駐留は、米軍だけの問題ではありません。アジア・太平洋戦争末期、日本軍は本土防衛のための沖縄戦に備えて1944年から沖縄駐留を始め、それ以降だけでも140箇所以上の「慰安所」を作ったことがさまざまな資料から明らかになっています。
そしてアジア・太平洋戦争が終わると、沖縄はすぐに米国の直接占領下に置かれますが、ここから1950年代にかけては、本当に多くの米兵による性暴力事件が起こりました。水汲みの途中、畑での農作業中など、日々の暮らしの中で、いつでもどこでも誰もが無差別に襲われる危険があるという状況だったのです。
その後、ベトナム戦争が始まると、ベトナムに派兵された米兵が数ヶ月の休暇、レスト&リクリエーション(R&R)を沖縄で過ごすことになりました。その結果、基地の周辺には性産業のお店が急増して、そこで働く女性たちへの暴力が頻発します。
1972年の復帰後、施政権が日本に移っても基地はそのまま、性暴力事件が起きる構造、特に「訴えても加害者は捕まらない」「捕まっても処罰されない」という構造は引き継がれました。むしろ、被害は基地周辺から全島へと広がっているのが現状です。先にご紹介した「行動する女たちの会」の記録によると、1945年4月から2021年12月までの米軍による性暴力被害者はおよそ950人となっていますが、これは氷山の一角にすぎません。
「行動する女たちの会」では「軍隊とは何か」ということについても、ジェンダーの視点から分析してきました。兵士たちはなぜ性犯罪を起こすのかという根本的な問いに対しては、軍隊、そして駐留軍という視点を持つことで、より構造的な問題が見えてくるのではないかという考えからです。
そこから見えてきたのは、ジェンダーの視点に立ったとき「軍隊とは構造的な暴力である」ということでした。
軍隊では、兵士たちが人を殺すことができるようになるために「敵は同じ人間ではない」という考えを叩き込みます。さらに「暴力を使ってでも国を、仲間を守るのが兵士の役割であり、それができてこそ一人前の男だ」と、「男らしさ」を暴力と結び付け、過剰に強調する。それが自分の中の「女らしさ」──「女々しさ」を否定する行為としての性暴力とつながっているのではないかと私たちは考えています。性暴力は、性欲の発露といった生理現象の問題ではなく、暴力によって女性(あるいは自分より弱い立場の男性)を支配し、従属させようとする行為だからです。
そうした性差別が、軍隊という組織のみならず、軍事力を重視する「軍事主義」のイデオロギーを支えているのではないか。私たちはそう考えています。
韓国、フィリピンなど海外との連帯
「行動する女たちの会」は、韓国、フィリピン、ハワイ、グアム、プエルトリコなど米軍基地のある国と地域、そしてアメリカなど海外の女性たちと連帯し、「軍事主義を許さない国際女性ネットワーク(International Women’s Network Against Militarism、IWNAM)」を作っています。
IWNAMで活動する女性たちのグループは、それぞれの国・地域で米軍が駐留していることでどのような性犯罪、性売買が起きているか明らかにし、被害者たちの救済、生活支援活動などを行ってきました。
例えば韓国。在韓米軍基地周辺には朝鮮戦争時から続く「基地村」があり、性売買が行われてきました。1970年代、アメリカはニクソン・ドクトリンにより在韓米軍の撤退、削減に乗り出しましたが、それに対して韓国政府は、基地村で働く女性たちの性病管理を強化することで引き止めを図りました。「基地村」の衛生状態を改善しますから、安心して駐留してください、出て行かないでくださいというわけです。
こうして「基地村」は米韓両国の思惑で温存されました。そこで働く女性たちは性暴力被害に遭ったり、世間から疎まれたり、尊厳を踏み躙られ続けてきたのです。それに対して2014年、「基地村」で働いた122名の女性たちが「基地村米軍慰安婦女性国家損害賠償請求訴訟」を起こします。2022年、最高裁判所は基地村の運営管理、性売買の正当化、助長などに韓国政府が関与していたとして、国家の責任を認めました。
また、フィリピンには1992年までアジア最大と言われる米軍基地があり、その周辺では性売買が盛んに行われていました。米軍の撤退後も米軍艦が合同演習のために帰港したり、大勢の米兵がそこで休暇を過ごしたりしているため、性売買はなくならず、米兵による性犯罪、性暴力も後を絶ちません。その背景には地位協定の定めなどによって、加害者が逮捕、処罰されないという根本的な問題があります。
性暴力は、米軍内部でも起きています。1990年代頃からそうした事件が明るみに出たり、告発されたりするようになってきたことを受け、2005年、米国防総省に性暴力予防対策局が設置されました。どのような事件がどれくらい起きたか、議会に毎年、報告されています。直近の2024年5月に出た報告書では、被害報告があったものだけで8515件の性暴力事件が起こっていたと報告されています。
フェミニズムから考える安全保障とは、平和とは
私はフェミニズムを「ジェンダー平等の達成を目指す思想」あるいは「女性や女性が担っている役割が平等に扱われることを求める思想」と捉えています。「女々しい」という言葉を侮辱語にしない考え方と言ってもいいでしょう。
私がアメリカの大学院で師事したベティ・リアドン博士は、フェミニズムの視点から平和運動、平和教育を研究する第一人者でした。今日の話のまとめとして、彼女の視点を紹介してみます。
⑴性暴力とは暴力で脅かし、従属を強いる行為である。
⑵軍隊による性暴力は、組織に内在するミソジニー、覇権的な男性性、暴力的な男性性の絶対的な優位が根底にあることで起きる。
⑶軍隊がなければ安全でないという「軍事主義」は、国家の軍事優先、軍事支配を正当化する。
⑷戦争を前提とする社会構造すなわち「戦争システム」があるかぎり戦争はなくならない。
⑸戦争システムを支えているのは、家父長制すなわち権威主義、差別、強制力によって支えられる競争的社会秩序であり、武力や暴力で物事を解決するという思想である。
⑹戦争システムは、男性が優位で女性は劣るとするジェンダー秩序、性差別によって支えられている。
このようなリアドンの分析をもとに、リアドンとも繋がりが深いIWNAMは安全保障とは何かを問い直し、安全保障の脱軍事化、脱植民地化を模索、フェミニストが構想する安全保障を次のように提唱しています。
⑴人間だけでなく全ての生命を持続させる環境作りを最優先する。
⑵衣食住、医療、教育など基本的なニーズを充足させる。
⑶人々の尊厳、個人のアイデンティティ、文化的アイデンティティを尊重する。
例えばハワイやグアムでは、地域住民にとって重要な文化的聖地や生活に必須の水源がある土地に軍事施設が作られています。そのようなことがあってはならないということです。
⑷民族の主権を尊重する。
例えば沖縄の人々の「ノー」という意思を無視して軍事基地が作られていますが、沖縄の主権は尊重されねばなりません。
⑸人災を起こさない。
地震や台風などは人間の力では防げないけれど、その予防対策、起こった後のことについては政策で対処できます。そうした政策を取ることが安全保障なのです。
日々の生活の安寧を大切にし、紛争・軍隊がない社会を目指す。平和の実現のためにもジェンダー平等を目指す──フェミニスト平和運動を世界中に広げる活動を続けていきます。
*
あきばやし・こずえ 同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授。1992年日本女子大学文学部卒業後、㈱日産化学工業に勤務。その後、2002年にコロンビア大学教育大学院で教育学博士号を取得。お茶の水女子大学ジェンダー研究センター研究機関研究員、立命館大学国際関係学部助(准)教授を経て、2014年より現職。婦人国際平和自由連盟(WILPF)日本支部国際担当理事、WILPF国際本部国際会長、日本平和学会理事などを務め、2016年からWomen Cross DMZ Steering Committee member, International Advisory Board memberなどでも活動。主な著書に川崎哲・青井未帆編著『戦争ではなく平和の準備を』(地平社)、富坂キリスト教センター編『沖縄にみる性暴力と軍事主義』(御茶の水書房)など。