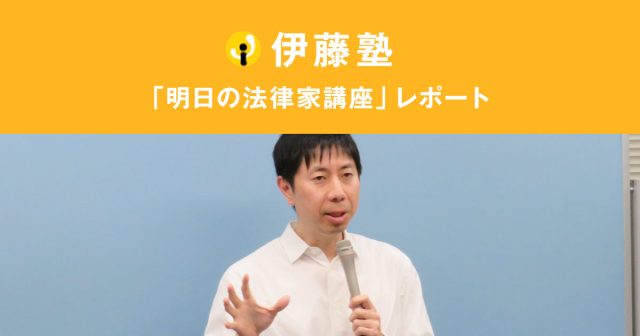社会課題の解決を究極的な目的として、国や地方公共団体を相手に起こす「公共訴訟」がいま注目を集めています。公共訴訟の果たす役割や意義、そして、社会を変える公共訴訟を支えるために立ち上がったウェブプラットフォーム「CALL4」についてお話しいただきました。[2月15日(土)@東京校]
社会課題の解決を目指す「公共訴訟」
「公共訴訟」とは何かをシンプルな言葉で説明すると「身の周りで起きている“おかしなこと”をなくすためにする裁判」のことです。
イメージしやすいよう例を挙げてお話ししましょう。1950年代に東京の空を撮った写真がありますが、薄く曇っていて遠くがほとんど見えません。このときと比べると、自動車排出ガスによる大気汚染は右肩下がりで減ってきました。実は、いま東京の空はこの70年間で一番きれいな状態なのです。その背景には「東京大気汚染訴訟」という公共訴訟がありました。
この訴訟は、ぜんそく患者やその親などが、首都高速道路公団や自動車メーカー、規制を担当する東京都などを相手に起こしたものです。裁判は数十年かかり結果的には和解で終わりましたが、裁判になったことで自動車メーカーでの取り組みが進み、汚染物質規制の仕組みが整えられ、東京の空気はどんどんきれいになっていったのです。そして、それをいま私たちが享受しているわけです。
一般的に、日本では原告となる人の権利実現のためでなければ訴訟を起こせないとされています。しかし、原告である自分たちのためだけではなく、同じような状況にある人たちのことまで考え、社会課題の解決を目指して行われる訴訟があります。それが「公共訴訟」と呼ばれ、いま注目を集めています。
たとえば法律上の性別を変えるための手術強要は憲法違反と訴えた「オペなしで!戸籍上も『俺』になりたい裁判」や、立候補年齢(被選挙権)の引き下げを求める裁判、同性婚の実現を求める「MARRIAGE FOR ALL JAPAN」裁判など、さまざまな公共訴訟があります。
たった一人の原告でも制度を変えられる
公共訴訟の意義としては、「少数者の人権侵害の是正」「バグ取り」「フォーラムの形成」の3つが挙げられます。
「少数者の人権侵害の是正」は、たとえば性的マイノリティの人々の権利侵害に対する訴訟などに当てはまります。日本の立法府の意思決定は民主主義によるものとされていますが、実際には多数者が決めるような仕組みになっています。選挙で多数の票をとった人が政治家になり、最終的にはそうした政治家の多数決によって法律は決められていきます。少数者の代理をする議員がいないわけではありませんが、大きな枠組みで見ると、多数者のための政治になっているのが現状です。
しかし裁判の場合は、少数であっても、たとえ一人であっても、原告となって訴訟を起こすことができます。最高裁によって原告の権利侵害が認められ、権利侵害をしている法律が違憲だと判断されれば、裁判所は国会に「その法律を変えなさい」と命じることができる。これは、とても大きな力です。
何十年も選挙での投票を通じた意思表示だけでは変わらなかった制度を、たった一人の原告が公共訴訟を起こすことで変えられるかもしれないのです。
法律が利益を正しく代弁しているか問う
ところで、ここで一つ付け加えておきますが「逆さま民主主義」という言葉があります。これは慶応義塾大学の山本龍彦先生の言葉です。山本先生は、法律のなかには必ずしも多数派の意見によってではなく、一部の人たちの利権のためだけに作られている法律もたくさんあるのではないかと指摘しています。
その一つの例として、1975年に出された薬局の距離制限を定めた薬事法に対する最高裁の違憲判決があります。薬事法には薬局同士を近くに作ってはいけないという距離制限がありました。しかし、その距離制限が法律に導入された議論の過程を見てみると、薬局業界の族議員のような人が主導したことがわかります。新しい薬局が出てくるのを防ぎ、既存の薬局の利益を守るために距離制限がつくられたのです。
そう考えると、公共訴訟には少数派の権利を守るだけでなく、立法が正しく多くの人たちの利益を代弁してないときに、それを正して実現させる機能もあるのではないでしょうか。
いま国会で議論されている選択的夫婦別姓制度にも同じことが言えそうです。世論では賛成のほうが多いにもかかわらず、誰が選択的夫婦別姓制度の実現を止めているのか。一部の宗教右派の影響を受けた議員の人たちが実現したくないだけではないのでしょうか。それを司法は正すべきだという声も上がっています。
公共訴訟による「バグ取り」の機能
2つ目の「バグ取り」ですが、エンジニアがコードを書いてプログラムをつくるときに、どうしても「バグ」と呼ばれる予期しない欠陥や不具合が出てくるものです。ですから、実際にプログラムを動かしてみてバグが見つかれば、そのバグを取って修正・改善していきます。ところが、日本の立法手続きの場合は、一旦法律ができてしまうと修正したり、変えたりするのはとても大変です。たとえバグがわかっても、なかなか修正されません。
有名な公共訴訟のひとつに、元ハンセン病患者たちが起こした国家賠償請求訴訟があります。2001年、この訴訟によって熊本地裁はハンセン病患者の強制隔離を定めた「らい予防法」は違憲であるという判断を出しました。そこには、ハンセン病の感染力が低いこと、薬で治る病気ということが判明したあとも、「らい予防法」が廃止されるまで国が強制隔離政策を進めてきたという問題がありました。このように「この法律は間違っている」とわかっていても修正されないときに、公共訴訟による「バグ取り」の機能が大切になってきます。
「この法律はおかしいのではないか、不平等ではないか」と、真っ先に気づくのは、その法律に関係する当事者です。最も影響を受ける人が「これはおかしい」と伝え、異議申し立てという形をとることで修正していく機能が公共訴訟にはあるのです。
裁判になることで問題を知ってもらう
3つ目の「フォーラムの形成」も重要です。
公共訴訟で大事なのは、必ずしも勝ち負けではありません。たとえば中国残留邦人による国家賠償請求裁判は、地裁、高裁、最高裁と原告が敗訴したものの、結果的に新しい支援法制定につながりました。公共訴訟を起こすことで、その問題が社会の大きなアジェンダになるという側面もあるのです。
ソフトウェア開発会社「サイボウズ」社長の青野慶久さんは、2018年に夫婦別姓婚についての裁判を起こしました。その青野さんは「裁判ってメディアですね」と言っていました。2〜3ヶ月に1回期日があり、その度にマスコミの人たちが来て夫婦別姓について報道してくれる。公共訴訟を起こすことで、今まで関心がなかった人々にも問題を知ってもらうことができます。
いま行われている、立候補年齢の引き下げを求める裁判もそうです。公職選挙法は70年間変わっていません。選挙権は20歳から18歳に引き下げられましたが、いまだに立候補年齢は制限され、衆議院議員や都道府県議会議員、市区町村長・議会議員は25歳以上、参議院議員や都道府県知事は30歳以上という決まりがあります。さまざまな分野で若く優秀な人が活躍しているのに、なぜか政治家にはなれないのです。
いま私たちが起こしている公共訴訟には、ほかにも母体保護法の不妊手術禁止規定をめぐる裁判があります。不妊手術が原則禁止されているのは、世界ではほぼ日本だけ。ほかの国では最もメジャーな避妊手段として不妊手術があるのですが、なぜか日本では原則禁止されていて、受けるには厳しい要件が課されています。富国強兵の時代に作られた法律が変わっていないのです。
公共訴訟を起こすことによって、「こんなおかしな法律がまだあるんですよ」ということが報道されて、それがイシューとして設定され、言論フォーラムの形成につながるのです。
権利に気づき、アイデンティティを回復する
公共訴訟の過程では、社会から否定され続けてきた人たちが変わっていく様子を目の当たりすることも多くあります。裁判を通じて自分自身の否定されてきた権利に気づき、アイデンティティを回復していくという大きな意義も公共訴訟にはあります。
先週、私はほとんど寝られなかったのですが、それはレイシャルプロファイリング裁判の書面の期限があったからでした。これは外国にルーツを持つ人たちが、不審事由がないにもかかわらず繰り返し職務質問をされるという問題です。
民間調査会社に依頼した調査結果によると、日本の警察から職務質問を受けた経験がある外国籍の人の割合は、日本国籍者の5.6倍でした(日本人回答者のうち、9割以上が「日本以外の国に民族的ルーツはない」と回答)。
このレイシャルプロファイリング訴訟には、ミックスルーツをもつ子どもを連れたお母さんが傍聴に来ています。たとえばアフリカルーツの見た目をもつ子どもは、日本で生まれ育ったにもかかわらず、小学生のときから友達の前で呼び止められて所持品検査をされるという経験をしています。「なんで自分だけそういう目に遭うのだろう」と子どもはずっと感じているのです。お母さんは子どもを傍聴に連れてくることで、「それは、あなたのせいじゃない。間違っている行為で、憲法上も禁止されているんだよ」と伝えたいのだと仰っていました。
日本で法令違憲判決を勝ち取る難しさ
日本では戦後からいままでに、最高裁による法令違憲判決が13件出ています。2022年には、在外国民審査についての最高裁の違憲判決が出ましたが、私はこの原告かつ代理人でした。米国留学中に国民審査ができなかった経験からスタートした裁判で、これが戦後11件目の違憲判決となりました。しかし、戦後約80年の間に、たったの十数件です。同じくらいの期間にアメリカでは州レベルで約800件、連邦レベルでは約150件、ドイツでは1000件以上の法令違憲判決が出ています。なぜ、こんなに少ないのか。日本では法令違憲判決を勝ち取ることは本当にうんざりするくらい大変なのです。
公共訴訟のしんどさを示す一つの例として、私が取り組んだ「スラジュさん事件」についてお話しします。2010年、ガーナからの移民として来日したアブバカル・スラジュさんが強制送還の過程で亡くなった事件です。スラジュさんには日本人の妻がいましたが在留資格を認められず、入管の施設に収容されます。
そしてある日突然、入管が彼を飛行機に乗せて強制帰国させようとするのです。入管職員は嫌がるスラジュさんを6人がかりで手錠・足錠して、猿轡(さるぐつわ)をかませてバスに乗せ、空港まで連れて行きまました。訴訟を起こしたときに証拠としてビデオ映像が出てきましたが、スラジュさんが「帰りたくない」「痛い」と言っている途中で映像は切られています。
証拠開示を巡る抗告審で再現写真が出てきたのですが、その写真を見るとスラジュさんは入管職員たちに座席に押さえつけられていて、そこでスラジュさんは動かなくなり、意識を失ってそのまま亡くなってしまいました。これに対して入管は、スラジュさんは心臓の奇病で死んだという調査結果を出し、入管職員の責任はないと判断したのです。それだけの制圧を受けるなかで意識を失ったのに、そんな馬鹿な話を一体誰が信じるのかと思いますよね。しかし、法医学会の理事長が奇病だという意見を書き、入管職員は不起訴になりました。
そこで、このまま放っておくわけにいかないと、私を含む6人の弁護士で弁護団を組んで国家賠償請求訴訟を起こしたわけです。ご遺族には裁判費用を出す余裕はなかったので、6人の弁護士に払われるお金はほぼありませんでした。さらに、協力してくれる医師を探したのですが、法医学会の理事長が奇病という意見書を書いていることもあったのか、日本の医師は誰も協力してくれません。私たちは反論のために慣れない外国語の医学文献を自分たちで調べて、徹夜で翻訳して裁判所に提出しなくてはいけませんでした。
そうやって一審では勝ったのですが、国は控訴しました。そして、東京高裁がスラジュさんは心臓の奇病により亡くなったという判断をしたことで、我々は負けてしまいました。
弁護士を辞めて留学した米国での衝撃
5年半かけて報酬もなく裁判をしたのに、誰もがおかしいと思うようなことが事実として確定してしまった。「もう疲れた」と思い、この裁判を機に私は弁護士を辞めることにしました。米国に留学して、司法は忘れてソーシャルワークの勉強をすることにしたのです。それが2015年のことです。ところが、2016年にトランプ大統領が就任して、いまのように非常に問題のある大統領令を出し始めました。
最初に出した大統領令は、イスラム圏7カ国からの米国入国禁止でした。これにより各地の空港などで大混乱が起きました。私はそのニュースをテレビで見ていたのですが、「この大統領令をどう思いますか?」という街頭インタビューに対して、中年の男性が「でも、まだ裁判所があるよね」と答えたことに、とてもびっくりしました。日本では誰も司法にそんな期待はしていないからです。
その後、SNS上で「司法を支えよう」という呼びかけが始まり、数時間で日本円にして億単位の寄付金が集まり、その日のうちにACLU(米自由人権協会)という弁護士団体が連邦裁判所に大統領令を一時停止する仮処分をかけました。ACLUを含めた百数十人の弁護士が寄付で得た資金をもとに全米各地の空港に行き、大統領令の影響を受けた人たちに聞き取りをして陳述書を作っていました。その夜、連邦裁判所から出てきたACLU弁護士が「たったいま、裁判官はトランプ大統領の大統領令を差し止めました」と言うと、ウォーッという地鳴りのような歓声が周囲から上がったのです。
その様子を見たとき、私は体を動かすことができないぐらいの衝撃を受けました。日本にいるとき、自分は過労で倒れるくらい全力で頑張ってきたつもりでしたが、ACLUのように誰かに資金をくれと言ったことも、誰かに裁判資料の翻訳を手伝ってほしいと言ったこともなかったと気づいたのです。「まだ、できることがあるのではないか」。そう思って日本に帰国して立ち上げたのが「CALL4」でした。
「市民の力」と結びつけるプラットフォーム
これまで日本では、弁護士たちがほかの仕事で稼いだお金を投入して、睡眠時間を削りながら公共訴訟を担当してきました。「CALL4」は、そうした弁護団や当事者の人たちを市民と結びつけることで、公共訴訟の力をもっと発揮できるようにするためのウェブプラットフォームです。
英熟語の「CALL FOR」には「こういう人いませんか?」と呼びかける意味があります。そして、「司法」、「立法」、「行政」に「市民の力」という第4の力を結びつけることで何か変わるのではないかという思いも「CALL4」の名前には込めています。
CALL4の運営は、弁護士、ロースクール生、修習生、高校生、社会人など、多様な人たちに支えられています。マーケティングや広報のプロたちもボランティアでかかわり、公共訴訟を知ってもらうために動画や漫画、コラム、イベント開催といった、さまざまな形での発信をしています。
CALL4の提供しているサービスのメインは公共訴訟のための資金を募るクラウドファンディングです。クラウドファンディングの仕組みは無料で提供していますが、その代わりの条件として必ず訴訟資料をアップしてほしいとお願いしています。なぜかというと、訴訟資料を公開するということが、この社会で科学的な議論を促進することにつながると考えているからです。これまで日本ではほぼ判決しか公表されてきませんでした。
しかし、とくに公共訴訟が扱う事件では、判決だけでなく議論の過程が重要だと思っています。みんなにとって大切なことを、どう話し合って決めていくのか──その過程を見せたいという思いから、誰でも訴訟資料を見られる仕組みにしました。これらの訴訟資料はマスコミの方たちも参考にされていますし、学校の授業でも使われているようです。
また、クラウドファンディングで寄付をした人たちが寄せてくれる応援のコメントも、原告や弁護団の大きな支えになっています。日本には「声を上げる人が嫌い」という風潮が強く、誰かが何かに異議申し立てをすることに対してバッシングが起きやすいのですが、CALL4を通じて「同じ気持ちだよ」と応援してくれる人たちが可視化されることで、原告や弁護団が力づけられるという意義もあるのです。
公共訴訟の専門家チーム「LEDGE」
最後に、新しく立ち上げた「LEDGE」という団体についてもお話ししたいと思います。
CALL4ではクラウドファンディングを通じてさまざまな弁護団を支援していますが、裁判費用はまかなえても人件費まではなかなか出ないのが現状です。そうしたなかで公共訴訟を担当するのはあまりに大変なので、一人の弁護士が一生のうちに公共訴訟を数件担当するだけで精一杯。日本には、公共訴訟を専門にしているフルタイムの弁護士はいませんでした。一方、先ほどお話した米国のACLUには年間予算が500億円くらいあり、公共訴訟を専門にしている数百人もの弁護士たちが働いていて、本部はマンハッタンの一等地のビルにあります。
こうした日本の状況を変えるため、公共訴訟を支える専門家チームをつくろうと設立したのが一般社団法人LEDGEです。LEDGEのメンバーには、弁護士だけでなく、リサーチャーやキャンペーンを起こして世論をつくっていくキャンペーナーなどもいます。一般的には訴訟は法律相談などから始まりますが、LEDGEの場合は「いまの社会ではここを変えないとダメだよね」というイシューを最初に特定し、そこから原告と弁護士、資金などを集めて社会にインパクトを与える公共訴訟をプロデュースするという、ちょっと珍しい流れをとっています。
LEDGEに所属する公共訴訟専門の弁護士やリサーチャーの雇用は、支えてくれる人たちからの寄付で実現しています。社会を変えていくことは原告たちだけの問題ではありません。少数精鋭のメンバーで公共訴訟を起こし、社会を変えていく。そのことに価値があると感じて協力してくださる人たちの力を借りながら、これから活動を広げていきたいと思っています。
*
たにぐち・もとき 認定NPO法人CALL4共同代表、LEDGEディレクター。弁護士・ソーシャルワーカー・アクティビスト。京都大学総合人間学部卒業。2005年弁護士登録。2015年、フルブライト奨学生としてミシンガン大学ソーシャルワーク大学院に留学し、コミュニティ・オーガナイジングを学ぶ。2018年帰国し、日本での弁護士活動を再開。2019年、社会問題の解決を目指す訴訟(公共訴訟)に特化した支援ウェブプラットフォーム「CALL4(コールフォー)」を立ち上げ、以後運営団体の代表を務める。2023年、公共訴訟専門家集団「LEDGE」を立ち上げ、以後ディレクターを務める。司法アクセスについての問題意識を持ち、都市型公設事務所・法テラスなどにて、貧困・高齢、障害・移民の分野などに関する事件や刑事弁護など、広く公益分野を中心とした弁護士活動を行う。日本評論社「法律時報」編集委員。