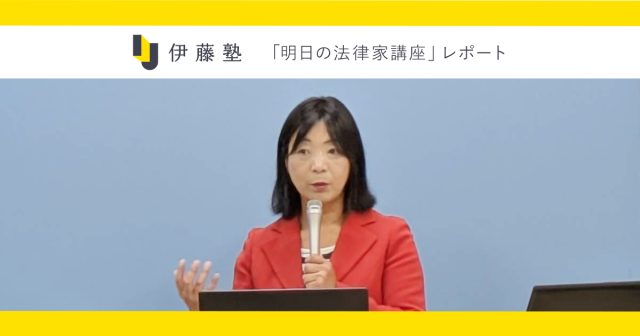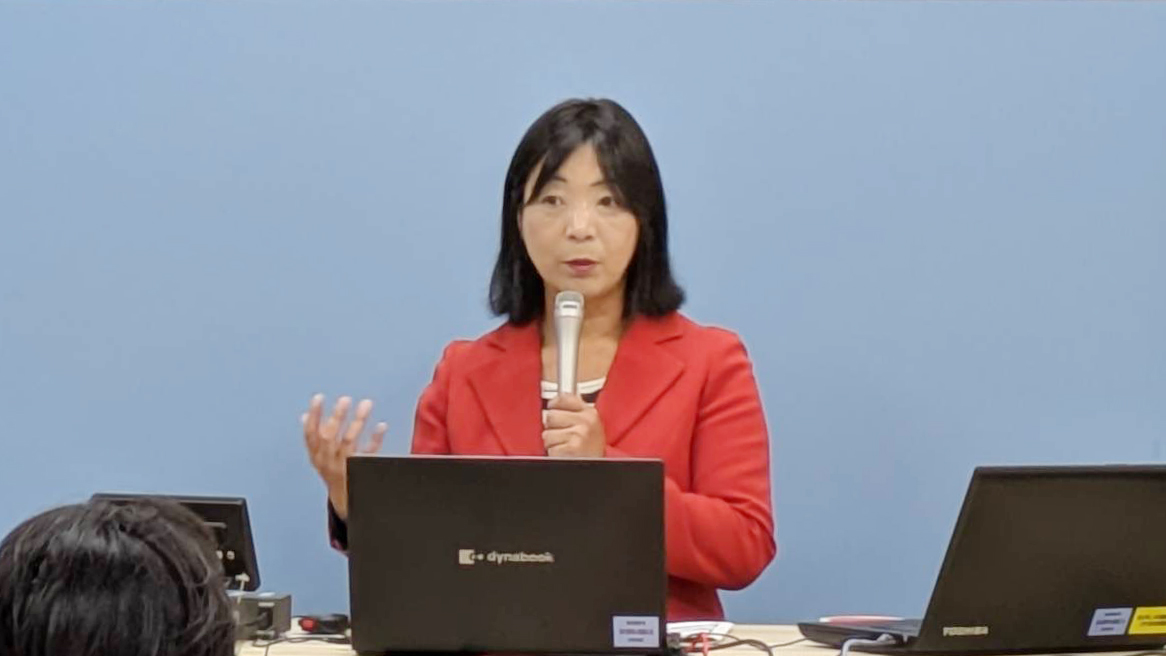近年、「ビジネスと人権」という考え方が注目を集めています。国家だけでなく企業にもまた、すべての人権を尊重し、侵害が起こらないように配慮する責任がある──。こうした考え方はどのように生まれてきたのか。そして、社会にどのような変化をもたらす可能性があるのか。長年国際人権団体で活動してきた弁護士の伊藤和子さんによる講演です。[2025年5月31日@東京本校]
国境を越えて人権を守る
弁護士としての仕事の傍ら、国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ(HRN)」で発足時から活動し、現在は副理事長を務めています。
もともと、弁護士になろうと思ったのは、自分が「理不尽だ」と感じることに対して声をあげて変化を起こせる人間になりたかったからです。たとえば、私が社会に出た当時、すでに男女雇用機会均等法はありましたが、企業に入った友人たちはさまざまな女性差別に直面していました。そうした「理不尽」を、法律という手段を使えば何らかの形で解決できるのではないか、人の役に立てるのではないかと考え、弁護士の道を選んだのです。
さらにその後、1995年に中国・北京で開かれた女性会議で、貧困や紛争に苦しむ世界中の女性たちの声を聞いたことを一つのきっかけに、世界で起きている人権侵害をなくすために貢献できる弁護士になりたい、と考えるようになりました。そして、まずはそのための基盤をつくろうと、2004年に米国留学。国際NGOの活動や国連インターンなどを経験しました。
そこで、国境を越えて人権問題に取り組んでいる人が世界にはたくさんいることを知りました。そして、日本に同じような団体がないのなら自分がつくればいいと考え、帰国後の2006年、仲間の法律家や研究者、ジャーナリストや市民とともにHRNを立ち上げたのです。日本を拠点とするものとしては初の国際人権NGOでした。現在は、国境を越えて世界で起きている人権侵害に立ち向かうこと、国際的な人権基準をさらに向上させていくこと、日本をはじめ活動拠点にしている地域と国際的な人権基準とのギャップを埋めていくこと、という3つのミッションを掲げて活動しています。
具体的な活動としては、まず事実調査。人権侵害の多くは、誰も知らないところで隠れて起こります。だからこそ継続してしまうし、注目を集めることもないわけです。そうした隠された人権侵害に光を当てるために、調査を重ねて報告書を作成し、事実を可視化していくという活動をしています。
それから、当事者に代わって政府や企業に働きかけをすることで人権状況に変化をもたらす、アドボカシー活動。政府に法律の策定を提言することもありますし、国や企業が動かない場合には国連に働きかけをするときもあります。
そして3つ目の活動の柱がエンパワメントです。人権侵害を受けている人の中には、そもそも教育機会が奪われていて、人権とは何かさえ知らずにいる人が少なくありません。そうした人たちに向けての教育支援とともに、日本国内でも人権についての理解を高めてもらうために、さまざまなセミナーなどを開催しています。
国連「ビジネスと人権」指導原則とは
さまざまな人権問題の中でも、私たちが特に注力している分野がいくつかあります。武力紛争下の人権侵害、女性や子どもの権利、人権活動家の権利、そして今日お話しする「ビジネスと人権」もその一つです。
ビジネスと人権について考える上で非常に重要なのが、2011年に国連人権理事会において満場一致で採択された「国連ビジネスと人権に関する指導原則(以下指導原則)」です。この原則ができるまでは、人権を守る義務を負うとされているのはあくまで政府であり、企業が人権に対して何らかの責任を果たすべきなのかどうかは明確ではありませんでした。
しかし、特に冷戦終結後、多国籍企業が人権を侵害したにもかかわらず、その責任を取らないというケースが世界中で頻発します。社会や環境に対する影響力が地球規模で増している大きな企業であれば、予算規模も雇用している人数も、小さな国よりもはるかに多いことも珍しくない。その実態に即して、国家だけでなく企業にも人権尊重を求めるべきではないかという声が高まってきました。そうした中で生まれてきたのが指導原則です。
ただし、この指導原則では、国家が人権保護の「義務を負う」のに対し、企業は義務ではなく人権尊重の「責任を負う」という言い方になっています。そもそも条約でも国内法でもないので、違反したとしても特に罰則はありません。それでも、企業には人権を守る社会的な責任があると、この原則によって定められた意味は大きかったと思います。
指導原則は、国家の人権保護義務、企業の人権尊重責任、救済へのアクセスという3つの柱から成り立っていますが、ここでは主に後の2つについてお話ししたいと思います。
「企業の人権尊重責任」は、原則の11〜24に定められています。重要なのが、原則12にある〈人権を尊重する企業の責任は、国際的に認められた人権に拠って〉いるという文言です。つまり、日本の企業であっても日本における人権理解では足りず、世界人権宣言を起点に、国連のさまざまな人権条約や宣言によって確立されてきた国際的な人権基準に基づいた人権尊重が求められるということになります。
また、原則13は企業に対し、〈自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり、助長することを回避し、そのような影響が生じた場合にはこれに対処する〉こと、さらには〈たとえその影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように努める〉ことを求めています。
つまり、直接的な自分たちの行為だけでなく、取引によってつながっている範囲、すなわちバリューチェーン全体において、人権侵害が起きていないかどうかを見て、対処していく責任が企業にはあるということです。たとえば自分たちの会社の製品を製造している工場で労働者の人権は保障されているか。その原材料を生産している場所で環境破壊が起こっていたり、児童労働が起こっていたりしないか……。
これらがバリューチェーンの「上流」だとすると、「下流」の問題もあります。製品を売るショップの販売員や配達員の人権状況はどうか。広告に差別的なメッセージは含まれていないか。製品が最終的に武器に用いられて、紛争地で人の命を奪うようなことはないか。さらには、イスラエルやミャンマーなど人権侵害について国際的に非難されている国と連携してのビジネスを行っていないかどうかなども問われます。「自分たちが直接人権侵害をしていなければいい」のではなく、非常に広範な責任が定められていることがわかるでしょう。
「救済へのアクセス」も、単に被害救済システム──たとえば相談窓口を社内に設けるなど──をつくればいいというものではありません。誰でもアクセスが可能である、透明性がある、対応が公平であるなど、さまざまな要件を満たす必要があります。さらに言えば、そうした要件を形式的には満たしていても、それを運用する人たちに人権感覚が不足していては、公平な判断ができないということもあり得る。人権について、特に国際的な人権基準を、会社としてしっかり学んでおく必要もあるわけです。
バングラデシュのビル倒壊事件から見えてきたこと
HRNが「ビジネスと人権」に関する活動に本格的に取り組むようになったきっかけの一つが2013年、バングラデシュで起こったビル倒壊事件です。首都ダッカ近郊にあった商業ビル「ラナ・プラザ」が突如崩壊し、1000人以上が死亡。2500人以上が重軽傷を負うという事態になりました。
ラナ・プラザは古いビルでしたが、テナントには洋服の縫製工場が入っており、ミシンなどの重い機械がたくさん置かれていました。事故が起こる前日には建物に亀裂が入っているのも見つかっており、工場で働く人たちからは「危ないから出社したくない」という声もあがっていたそうです。しかし、ビルのオーナーも工場経営者もそれを無視し、当日も工場では通常どおりミシンが回っていた。そこで突然建物が崩れ落ちて、大勢の人たちが亡くなってしまったわけです。
事故の後、私も調査のため現地を訪れて事故の被害者の話を聞いたのですが、中には児童労働の被害者でもあったまだ10代の少女──けがで足がほとんど動かなくなってしまったと言っていました──や、妊娠中にもかかわらず毎日朝7時から夜10時すぎまで、週7日間働かされていたという女性などもいました。
それまで、HRNでは主に武力紛争下の人権問題を扱っていたので、私自身も「人の命が奪われる=戦争」という感覚がありました。ところが、ここでは戦争ではなくビジネスによって、1000人以上の人たちが犠牲になり、さらに多くの人たちが重いけがを負っている。これは労働問題であるだけでなく人権問題だと、認識を新たにせざるを得ませんでした。
この事件はCNNなどでも大きく報道され、世界各地で「バングラデシュはなんて労働環境のひどい国なんだ」という声が上がりました。しかし、状況が明らかになるにつれそうした声は小さくなっていきます。
なぜなら、ラナ・プラザの縫製工場でつくられていたのは、バングラデシュの人々向けの洋服ではなく、ベネトンやZARAといった、世界に名だたるファッションブランドの洋服だったことが分かったからです。人件費の安い国で、しかも安全対策などにかけるべきコストも省いて「とにかく安くやってくれ」という形で委託をしていたんですね。バリューチェーンの末端で起きた事故だったわけで、企業が指導原則を守って責任を果たしていれば、こんな事故は起きなかったかもしれません。
さらに、ビルのオーナーや工場経営者は逮捕され服役したものの、破産してしまったので賠償金の支払いはできませんでした。一方、縫製の委託元であるファッションブランド各社も当初、「雇用関係がないから賠償義務はない」といって支払いを拒否します。たしかに法的な責任を問うことは難しかったのですが、指導原則に照らせばやはり何らかの責任を果たすべきだという声があがり、賠償を求める世界的なキャンペーンが立ち上がりました。そして最終的に委託元のブランド各社が、国際労働機関が支援している基金に寄付をするという形で、補償を行うことになります。
日本企業の現状は?
ラナ・プラザの事件では、委託元のブランドの中に日本企業はありませんでした。では日本企業はクリーンで何も問題がないのかといえば、もちろんそんなことはありません。HRNでは2014年に、香港と中国の団体と協働で、ユニクロの委託先である中国の工場の潜入調査を行いました。調査員が4カ月間、実際に工場で働きながら写真を撮ったり、労働者にインタビューしたりして、労働状況の調査をしたのです。
結果、非常に問題があることが分かりました。労働法規に反する長時間労働、残業なしには生活できないレベルの低賃金、劣悪・危険な作業環境。工場の中の室温は37〜38度もあり、上半身裸で汗だくになりながら働いている人もいました。さらには、染織の過程で出る有害物質の管理が十分にできておらず、工場中にその物質の臭いが充満している。床には汚水が流れていて漏電のリスクもあり、実際に感電して亡くなった人がいたことも報告されていました(ユニクロ側は否定)。
また、品質のよくない製品に関してはユニクロから工場へ返品されるのですが、その返品による損金は「罰金」として労働者の賃金から差し引かれることになっていました。しかも、こうしたさまざまな問題に対して、労働組合を通じた是正の仕組みがないという問題もあったのです。
翌年、記者会見でこの調査結果を発表したところ、かなり大きな反響がありました。それを受け、ユニクロの親会社であるファーストリテイリングはおおよその事実を認めて改善を約束、アクションプランを公表することになります。
こう見てくると、やはり多くの人が関心を持つことは大事だと思います。指導原則そのものは十分な規範ではないかもしれないけれど、それに基づいて調査をし、事実が明らかにされることによって、消費者やメディア、投資家などからのプレッシャーが強まり、企業が変わっていくわけです。
経営の根幹に人権を位置づける
ビジネスと人権に関わる取り組みを始めた当初は、私たちも企業から敵視されることが多かったのですが、徐々に時代は変わってきています。特に海外では、企業に人権を守るための仕組みを持つことを義務づける法律を策定するなど、企業の「責任」を「義務」化し、指導原則を実効性があるものにしていこうという動きが活発化しているのです。
これを受けて、日本でも政府が2020年に「ビジネスと人権」に関する国内行動計画を採択、2022年には経産省が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を公表しました。これらを参照しながら、人権方針を定めたり、人権についての取り組みを進めたりする企業が増えてきています。
しかし、取り組みと現実のギャップは、いまだ大きいです。例えば、著名な国際団体は日本の食品・飲料品産業のバリューチェーン上で、児童労働や強制労働、人身取引などの「現代奴隷」といわれる問題が起こっていると警告しています。実際、外国人技能実習生に対する奴隷的な取り扱いは深刻で、性加害やパワーハラスメントなどの人権侵害も多数起こっていますし、中国の新疆ウイグル自治区における少数民族への強制収容と結びついた、強制労働とも深く関係するビジネスと、多数の日本企業が取引関係を継続していることが問題視されているなど、さまざまな問題があります。
また、国内でいえば、ここ数年ではジャニーズ事務所性加害問題、そしてフジテレビ問題など、エンターテイメント業界における性加害が明るみに出ました。2023年には、国連人権理事会の「ビジネスと人権」ワーキンググループが来日し、ジャニーズ性加害問題の被害者に聞き取りを行いました。ジャニーズ事務所だけの問題ではなく、メディアもまた性加害のもみ消しに加担し、スポンサー企業も取引関係がある関連企業としての責任を果たしていなかったことが指摘されています。
メディアをはじめとする関連企業が見て見ぬふりを続けた背景には、今日お話ししてきた指導原則をはじめ「ビジネスと人権」についての理解が不足していて、自分たちが責任を果たすべきだという認識がなかったことがあると思います。それだけでなく人権問題を「遠い国の問題」というイメージでとらえていて、自分たちの足元の問題だという意識がなかったこと、女性や子どもが性的な被害から守られる権利、同意のない性行為を強要されないことが基本的人権である、という理解が欠如していたこと。この3つが、おそらくは大きかったのではないでしょうか。人権とは何か、を企業が十分に理解すること、そのために従業員などの権利を有する人々、特に声を上げにくい立場の人の声に耳を傾けることが必要です。
また、フジテレビ問題についていえば、実はフジテレビには人権方針がすでにあり、コンプライアンス部門もあり、人権についての研修も行われていたし、苦情申し立て窓口もきちんと設けられていました。にもかかわらず、それが機能せず、人権感覚の乏しい少数の壮年男性からなる経営幹部が情報を独占してトップダウンで方針を決め、被害者を追いつめる結果になってしまった。ここから見えてくるのは、指導原則に基づいて人権方針を制定している、相談窓口をつくっているというだけでは、意味がないということです。これはフジテレビだけの問題ではありませんが、経営の根幹の重要課題として人権を位置づけること、そして被害に遭った当事者などの声を聞きながら取り組みを進めていくことが重要なのだと思います。
今年の2月に、『ビジネスと人権──人を大切にしない社会を変える』(岩波新書)という本を出版しました。今の日本社会は、人を大切にしない社会だと思っています。そして、そんな社会に未来はありません。そうした状況を変え、自分や大切な人を守るために非常に役立つ「ツール」となる「ビジネスと人権」という考え方を一人でも多くの人に知ってもらいたい。それによって、この世界をより生きやすい場所に変えていくきっかけがつくれればと考えています。
*
いとう・かずこ 弁護士、ミモザの森法律事務所代表、ヒューマンライツ・ナウ副理事長。1994年に弁護士登録。2004年、ニューヨーク大学ロースクール客員研究員を経て、2006年に国際人権NGOヒューマンライツ・ナウの立ち上げに関わり、2022年まで事務局長を務める。2023年、ビジネスと人権に関する研究について早稲田大学から法学博士号を授与される。著書に『ビジネスと人権──人を大切にしない社会を変える』(岩波新書)、『人権は国境を越えて』(岩波ジュニア新書)など。日弁連両性の平等に関する委員会委員。WWF ジャパン評議員、慶應義塾大学ロースクール講師。