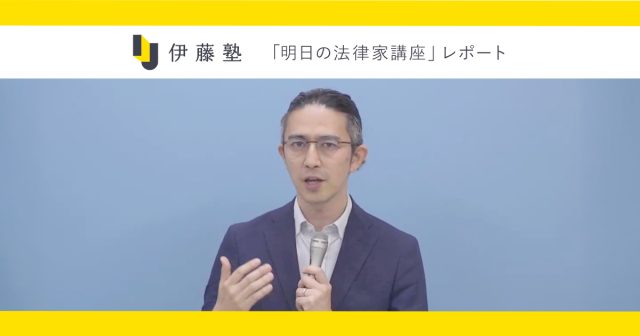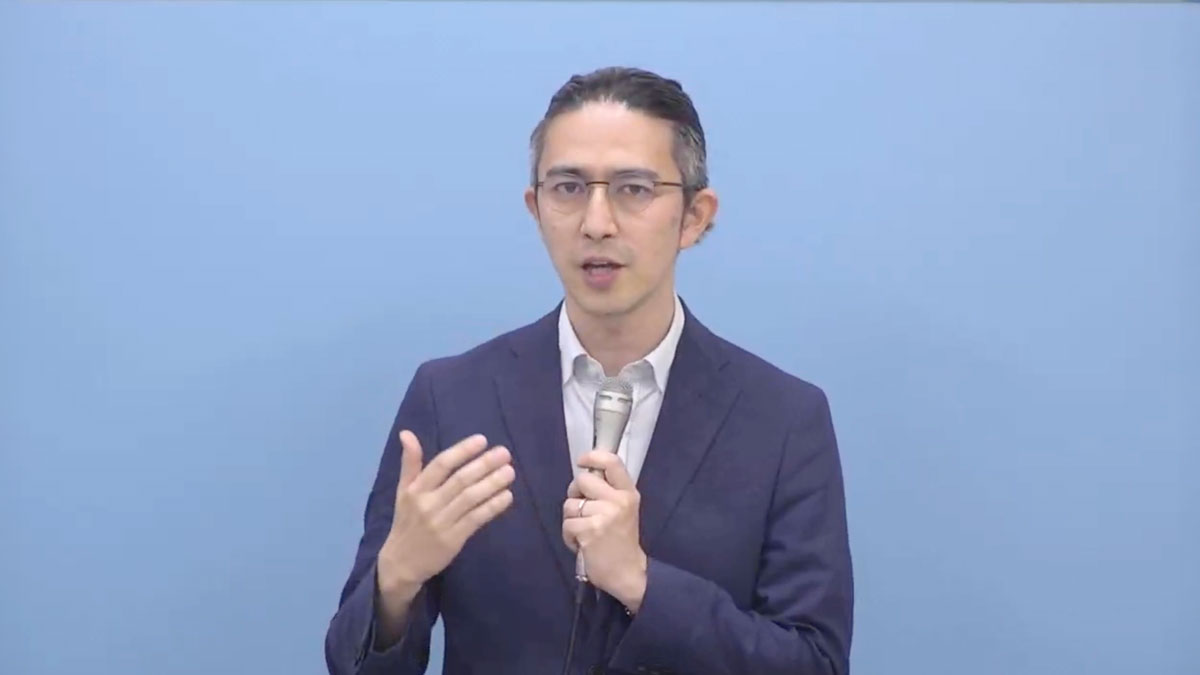2024年の大規模な民法改正で、非婚・離婚時の共同親権が導入されました。立法時には反対の声も多く上がりましたが、中でも「非合意強制型の共同親権」は、父母の人権、子どもの権利の観点から重大な問題を含んでいると指摘されています。どのような問題が考えられるのか、憲法学者の木村草太さんによる講演です。[2025年6月25日@東京本校]
親権とは何か
今日は「家裁における子どもの人権」ということで、2024年に成立した令和6年民法改正と「子どもの親権」の問題を主軸にお話ししていきたいと思います。
未成年の子どもが生活していくには、進学や医療、住む場所などについて法的な決定を支援する人、それから同居して食事などの世話をする人が必要となります。日本法では、この法的な決定をする権利(法的決定権)と、日常の世話をする権利(身上監護権)をあわせて親権と呼んでいます。
そして、父母が何らかの理由で別居する事態になったときには、この法的決定権と身上監護権は別個に考える必要があります。というのは、法的決定は親が別居していても共同で行うことがあり得るのに対し、監護は子どもと一緒に住んでいる側の親が中心になり、完全に共同で行うのは難しいからです。場合によっては、離婚後に親権は父親が持ちつつ、身上監護は母親が子どもと同居して行うといったことも行われてきました。
この「親権」についての規定が大きく変わったのが、令和6年民法改正の特徴です。
改正前の民法では、父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行使する、つまり共同親権。そして非婚・離婚の場合には法的決定権は父母のいずれか片方が持ち、身上監護権はそれとは別に協議で決めるというかたちが取られていました。法的決定権については、別居・離婚していて協力関係にないような父母が共同で行使すると、決定に時間がかかるなど適時適切な決定ができず子どもの利益にならないので、父母どちらかが単独で行使する。一方、身上監護権については、たとえば父母が数ヶ月ごとに交代で同居する、普段は母親と住んでいるけれど週末は父親と過ごすなど、いろいろなやり方が考えられるので、協議で決めるということになっていたわけです。
それが今回の民法改正によって、離婚・非婚の場合には、父母が協議して単独親権か共同親権かを選べることになりました(819条)。もともと、事実婚のカップルなど「法律上の結婚はしていないけれど、協力して子育てをしている」人たちもいるわけで、父母が合意した上での共同親権はあってもいいのではないかという議論はあったのですが、ここで重要なポイントになるのは819条にある、家庭裁判所が〈父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる〉という文言です(819条5)。
つまり、両親が「共同親権にしよう」と合意しなくても、裁判所が共同親権を要請することがあり得るということ。これが「非合意強制型」の共同親権です。
DV被害と共同親権
この非合意強制型の共同親権で問題になるのは、まず先に触れたように、父母が協力関係にないため、子どもに関して「適時適切な決定ができない」ということ。そしてもう一つが、DV(家庭内暴力)や虐待の道具として使われてしまう可能性があることです。
DVや虐待の加害者が共同親権を持った場合、被害者側が加害者と会わないようにしていても、加害者は「この書類にサインが欲しかったら会いに来い」などと言えてしまいます。つまり、加害の継続のために親権が利用されてしまうわけです。事実、すでに離婚後共同親権を導入している国々では、DV加害者が共同親権を使って被害者とのコンタクトを継続しようとすることが大きな問題となっています。
では、このDVや虐待の問題について、改正法はどう考慮しているのか。819条7には、〈父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき〉、また〈父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ〉などがあるときは共同親権にせず、父母いずれかの単独親権にしなくてはならないと書かれています。
この条文は、ないよりはましだとは思いますし、国会での答弁などを聞いていると、立法担当者はDVや虐待の問題はこの条文で抑え込めると考えていたようです。しかし、それはDVや虐待の問題を正しく理解しているとは到底言い難いと思います。
なぜか。〈おそれがあるとき〉ということは、その「おそれ」を裁判所がきちんと認定してくれなければ、この条文は機能しないわけです。ところが、DVや虐待は物的証拠のない場合が多い。結果、認定から洩れるケースが大量に出てくることになりかねません。
また、あくまで将来に向けた〈おそれがあるとき〉であって、過去にDVや虐待があった場合に排除するという条文にはなっていないことも問題です。つまり、過去に何をやっていても、今暴力が起こっていなければ、「反省しているから大丈夫」「DVのおそれはない」と認定される可能性がある。事実、私が調べたアメリカの例では、7年前に「顔を殴る」という暴力があったにもかかわらず、今は暴力をふるっていないからDVはないと認定されたケースがありました。こうした事例を知っていれば、この条文で安心できるはずがないことは明らかだと思います。
立法にあたっては、法務大臣の諮問機関である法制審議会の家族部会で議論が行われましたが、最後の要綱案採決では3人の委員が反対しました。通常は全会一致が原則なので、異例のことです。3人はいずれも、DVや虐待についての専門家や、シングルマザー支援団体の方でした。逆にいえば、こうした問題の専門家ではない人たちの票によって要綱案が承認され、立法に至ったということです。
「人格を尊重し協力する」とは?
共同親権に関わる、他の条文についても見ていきましょう。
817条の12には〈父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない〉とあります。これも、使い方によっては非常に危険な条文です。
DVなどの加害から逃げてきたことを指して、「相手の人格を尊重していない」と認定する裁判官が出てくるかもしれないからです。あるいは、被害者が加害者に対して「あなたには子どもとは会わせられません」「もうあなたとは話し合いができません」と言ったりすれば、「民法上の尊重義務に反している」という判断をされる危険性もあるでしょう。
次に、親権の行使方法を定めているのが824条の2です。ここには、共同親権であっても父母のいずれかが単独で親権を行使できる場合がいくつか挙げられています。
たとえば〈子の利益のため急迫の事情があるとき〉。子どもが急な病気になって病院に行かなくてはならないときに、どの病院に連れて行くかを決定する、といったことが考えられますね。それから、それほど重要ではない〈監護及び教育に関する日常の行為〉に関しても、単独で親権が行使できると定められています。
一見、特に問題のない条文のように見えますが、父母が協力関係にあっての共同親権ではなく、非合意型の共同親権──父母が対立関係にあって合意していないのに、裁判所が共同親権にしなさいと定めた場合──を考えるとどうでしょうか。実は、一方が単独で親権を行使した後、それをもう一方の親がキャンセルすることも条文上はできてしまうという問題があるのです。
たとえば、子どもが学校のプールの授業に参加していいかどうかを決めるのは、もちろん「日常の行為」です。そこで、同居している母親が判断してプールカードの「参加する」に○を付けたとします。これは、単独での有効な親権行使ですね。
ところが一方で、別居している父親が学校に電話して「子どもをプールに入れないでください」と言ったら、こちらも単独での親権行使として有効になってしまう。さらに、母親が再度「プールに入れてください」と言えばこれも有効、父親がまた「入れないで」と言えばこれも有効……と、永遠にループすることになるのです。そして、学校はどちらに従っても、親権を侵害したとして、極端な場合は損害賠償を請求される恐れがあります。本来は、「単独で親権を行使できるけれど、こういう場合はこちらが優先しますよ」と書いておく必要があったのです。
この問題については国会でも指摘され、当時の小泉龍司法務大臣が答弁に立ちました。ところが答弁の内容「同じ問題は婚姻中の共同親権でも起きます」というもの。つまり、新しく問題が増えるのではなく「今起きている問題がもっと増えるだけだからいいでしょ」というわけで、めちゃくちゃだと思いました。
このような雑な条文が入っていることを見ても、共同親権に関する立法は、まったく練られていない形で進められたことが明らかだと思います。
非合意強制型共同親権は、本当に必要なのか?
本来、共同親権というのは基本的に父母の間に協力関係がないと成り立ち得ないものです。それを、合意できないのに裁判所が「共同親権にしなさい」と決める非合意強制型共同親権には、明らかに無理があるといえます。
立法にあたっては、法制審議会家族部会で、「こういうケースに対応するために非合意強制型の共同親権が必要だ」という意見がいくつか述べられています。しかし、そのどれも、「たしかに必要だ」というケースとは言えませんでした。
たとえば、「離婚後、子どもの監護や教育には関わりたくないと言っている人に、子育てに関与させるため」に非合意強制型の共同親権が必要だという意見がありました。しかし、「関わりたくない」と言っている人に親権を持たせても、きちんと話し合いができるわけはありませんし、そもそもそれだけ無関心な人に医療や教育に関する決定をさせるというのは、明らかに子どもへの人権侵害です。
あるいは、子どもと同居している親が精神的な疾患を持っており単独では十分な親権行使ができない場合に、非合意強制型の共同親権が必要だという意見も出ていました。これも、そもそも精神疾患に対する差別的な感情が含まれているのでは? という危惧を置いても、非常に変な話です。同居親が精神疾患のため子どもに関する適切な親権行使ができないのであれば、必要なのは共同親権ではなく親権者の変更でしょう。共同親権にしてしまうと、その「適切な判断ができない」同居親の同意がないと、親権を行使できないことになってしまいます。
法務省も、非合意強制型の共同親権が必要なケースをいくつか挙げています。たとえば、同居親と子の関係が必ずしも良好でない、同居親による子の養育に不安があるなどのケース。つまり、同居親による法的決定、監護では十分に行き届かない場合に、共同親権が必要だというわけです。
しかし、共同親権というのは同居親をサポートしてくれる仕組みではなく、あくまで「別居親の同意がないと法的決定ができないようにする」というものです。つまり、同居親の立場に立てば、子どもについてさまざまな決定をしなくてはいけない場面で、別居親との調整・連絡という負担が生じることになります。シングル家庭にとってもっとも貴重な資源である「時間」を削られるわけで、それが果たして子どものためになるのでしょうか。
また、父母間の感情と親子関係とを切り分けて十分に協力ができるケース、最初は対立していたけれど家裁で話し合いを重ねる中で共同行使ができる関係になっていったケースなども挙げられていますが、これも共同親権の強制が必要なケースとしては極めて不適切です。むしろ、協力関係にあるのなら合意ができるはずですし、合意できないのであれば「十分な協力関係がある」とは言えないでしょう。
何のために非合意強制型の共同親権が必要だったのか。このように、法制審議会や法務省の説明を聞いてもさっぱり分からないと言わざるを得ません。
パブリックコメントから見えてくるもの
法律というのは、条文を読んで理解すればいいというものではありません。その法律のもとで何が起きているのかは、現場の声を聞かないと見えてこないことがあります。
そこで、その「現場の声」の一つとして、令和6年民法改正の中間試案に寄せられたパブリックコメント(パブコメ)の分析を行いました。一般には概要版しか発表されていないのですが、情報公開請求をかけてすべてのコメントを開示してもらいました。
それによると、寄せられたコメントは約8000件、うち約6000件が共同親権導入に反対するコメントでした。こちらは内容も極めて一貫していて、特に多かったのは、DV事案の当事者からの「DV加害者である相手方が共同親権を申し立てて来たら困る」という声、「それから今は同居親の単独でうまくやれているのに、共同親権にされると別居親との調整に余計な手間がかかるようになって困る」という声でした。
一方、共同親権導入を求めるコメントは約2000件、うち700件が自分自身や周りの人が単独親権で困ったので共同親権を導入してほしいという、自分の具体的体験を語るものでした。ただ、ここにも法制審議会や法務省が挙げていた「共同親権が必要なケース」に当てはまるもの──子どもに無関心な親に関わりを持たせたいとか、同居親に精神疾患があって単独親権では心配だとか──はほぼゼロ。ほとんどが、相手親による子どもの「連れ去り」を主張するものでした。
連れ去りとは、「ある日家に帰ったら子どもとパートナーが家からいなくなっていた」というもの。見方を変えれば「子連れ別居」なのですが、特徴的だったのは、元パートナーとの共同生活が破綻したことへの反省の言葉がほとんど見られないことでした。むしろ、相手を非常に苛烈に攻撃するものが多い。元パートナーは精神病だ、浮気していた、虚偽DVを主張された……もし本当にそうなら、どうしてそんな相手とまた共同親権で子育てをしたいのかという疑問が浮かびますし、ここまで攻撃的だと、仮に言っていることが本当でも共同親権は無理だろうと思わざるを得ないようなコメントが大半でした。
つまり、このパブコメの内容からは、共同親権が立法されたときに、一番それが使われる可能性が高いのは、法制審議会や法務省が挙げたようなケースではなく、別居親が同居親に対して極めて攻撃的な態度を取っている事例だということが見えてきます。法務省ももちろんパブコメの内容は知っているはずなのに、なぜそのことを堂々と言わなかったのか。いかに誠実さに欠ける態度のまま立法がなされたかということだと思います。
そもそも、この「連れ去り」を主張する人たちが非常に攻撃的な態度を取るということは、極めて大きな問題となっています。共同親権導入に反対する情報発信を行っていた弁護士に対してもSNS上での誹謗中傷などが起こっており、日弁連がそれに対して抗議声明を出さざるを得ないほどでした。
おそらく、DVや虐待の加害者にとっては、「自分が支配しているこの家庭はとてもうまくいっていた」という感覚なのでしょう。でも、被害者からすれば同じ家庭の中にいても見えているものが全然違う。加害者から見れば「まったく家庭に問題がなかったのに、相手が突然錯乱して出ていった」であるケースも、被害者からすれば「突然ではなく、暴力や抑圧の蓄積がずっとあって、それについに耐えられなくなって逃げた」ということになるのです。これに対して加害者側は、非常に強い被害者意識、そして攻撃性を持つのだと思います。
共同親権の強制は、憲法24条違反の可能性
すでに共同親権を導入している諸外国では、深刻な問題がいろいろと起こっています。
まず、共同親権の導入を主張する人たちによって、「シングル家庭では子どもはまともに育たない、お父さんとお母さん、両方との十分な接触が必要だ」「共同親権や共同監護を拒絶することは子の利益を害する」というイデオロギーが広められ、それによって配偶者のDVや虐待を主張しづらくなっているそうです。ドイツでは1997年に離婚後共同親権が原則化されたのですが、そのドイツの弁護士が著書の中で「クライアントが配偶者によるDVを主張したいと言っても、よほどの証拠がない限りはかえって不利になるからやめたほうがいいとアドバイスせざるを得ない」と書いているのを読んだことがあります。
また、適時適切な法的決定ができなくなるという話はすでに触れましたが、それを利用して、たとえば別居親の反対で子どもが希望する学校に行けないというような、離婚後の虐待の道具として共同親権が使われるケースも非常に数多く起きているそうです。こうしたことも、本来は立法の前に前提として議論すべきだったと思います。
さらに、日本ではこの問題は、憲法24条とも関連して考える必要があります。24条は、婚姻は〈両性の合意のみに基いて〉成立する、と定めていますが、これは戦前の旧民法で、戸主が強い権利を持つ「家制度」が採用されていたことと深く関係しています。家制度の呪縛から個人を解放し、男女平等を実現するため、戸主の意思とは関係なく「当事者が合意をしさえすれば婚姻は実現する」という条文が入れられたのです。
ところが非合意強制型の共同親権というのは、その「当事者の合意」なしに、離婚後も婚姻時並みの親密な話し合いを要求する制度です。つまりは、婚姻を合意なしに強制しているのに等しく、憲法24条1項違反の可能性があるのではないでしょうか。
そう考えると、共同親権に関する法律はすでに成立してしまっていますが、双方の合意と協力がなければ裁判所は共同親権を命じることはできない、積極的かつ真摯な思いと父母の主観的客観的な協力関係がない場合は、共同親権は子どもの利益を害すると考えて単独親権にしなくてはならない。そういうふうに合憲解釈をして運用していく必要があるのではないでしょうか。子どもの人権を守るために何が必要か、ぜひ考えてみていただきたいと思います。
*
きむら・そうた 東京都立大学法学部教授。2003年、東京大学法学部卒業。同年、同大学法学政治学研究科助手。2006年、首都大学東京(現東京都立大学)准教授。2016年より現職。2024年より、日本学術会議・子どもの権利保障分科会委員(連携会員)。主な著書に『憲法』(東大出版会)、『子どもの人権を守るために』(編著、晶文社)、『「差別」のしくみ』(朝日新聞出版)、『離婚後の共同親権とは何か』第2章(梶村太市 長谷川京子 吉田容子 編著/日本評論社)、『離婚後の子どもをどう守るか』第3章―1(梶村太市 長谷川京子 吉田容子 編著/日本評論社)など。