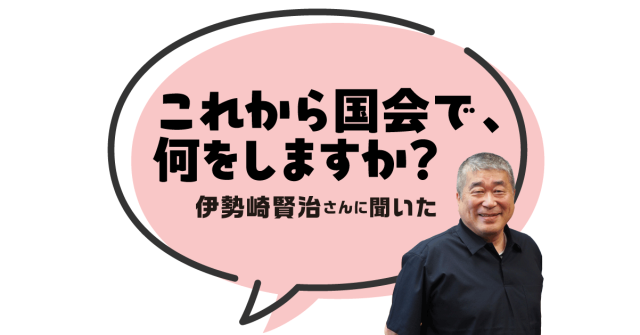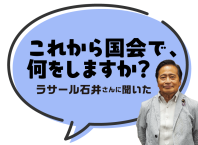夏の参院選から2カ月が経ちました。選挙後は「参政党の躍進」ばかりが取り上げられがちでしたが、もちろんそれだけが結果ではありません。当選した顔ぶれの中でもとりわけ気になったのは、活躍してきた分野は違えど、ともにまったく違う世界から「新人議員」として政治の世界へ飛び込んだ、ラサール石井さんと伊勢崎賢治さん。お2人に、立候補を決意した理由や、国会で何をやろうとしているのかについてお聞きしました。
日米地位協定を「対等」に。憲法9条を、より9条にする
伊勢崎賢治さん(れいわ新選組)/取材日:2025年8月21日
*
◆ 無力感が立候補を後押しした
──伊勢崎さんはかつて国連やNGOでシエラレオネやアフガニスタンの紛争解決・平和構築に携わられ、近年はその経験を生かして研究者として活動してこられました。今回、政治の世界に飛び込もうと思われたのはどうしてですか?
伊勢崎 これまでにも僕は学者の立場から、日米地位協定や日本の国際貢献などについて発言し、政府への働きかけを続けてきました。国会議員に超党派議連を結成してもらい、一緒に活動したことも何度もあります。
昨年5月には、イスラエルによるパレスチナのガザでの虐殺になんとかブレーキをかけたいと、衆議院議員の阿部知子さんらに呼びかけて超党派の「人道外交議員連盟」を立ち上げてもらいました。その議連を通じて、UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)への資金拠出凍結解除(※)を政府に働きかけたり、ガザから重傷患者2名を自衛隊機で日本へ移送し、自衛隊の中央病院に受け入れたりといった取り組みを進めてきました。重傷患者については、さらに数名を受け入れようと動いているところです。
ただ、それくらいではガザの状況はまったく変わりません。虐殺は止まらず、大勢の人たちが餓死にまで追い込まれている。一滴の水を必死で砂漠に落としているような無力感がありました。
※UNRWAへの資金凍結解除……UNRWAはパレスチナ難民への人道支援を行う国連機関。2024年、UNRWAの一部職員がイスラム組織ハマスのイスラエル攻撃に関与したとの疑惑が持ち上がったことから、米国やカナダ、欧州諸国の一部などがUNRWAへの資金拠出を一次停止。パレスチナへの人道支援継続が危ぶまれた。日本政府は24年1月に拠出を停止、同4月に再開した
──その「無力感」が立候補を後押ししたのでしょうか。
伊勢崎 そうですね。こうなったら、政治家になって自分で直接物事を動かしていくしかないのかもしれないと考えるようになりました。そこでちょうど「立候補しないか」と声をかけていただいて……という流れです。
──当選後すぐ、国会での質疑にも立たれましたが、議員になったことでの変化は感じていますか。
伊勢崎 やはり、これまでは議員を通してしかできなかったことが、自分で直接できるというのは大きいと感じますね。何か調べたいと思ったときにも、調査室や法制局の優秀なスタッフにすぐお願いできるし(笑)。
また、ここ1年ほどガザの問題で協力してもらおうと、中東諸国の大使館に足しげく通って関係性を作っていたのですが、そこでも当選後、たくさんの方が「期待していますよ」と声をかけてくれました。先日も、僕の国会での質疑を聞いたといって、イラン大使館から連絡があったし、期待と影響力の大きさを感じますね。
──国会質疑では石破総理に対し、「パレスチナの国家承認」を求める場面もありました。
伊勢崎 イスラエル政府に圧力をかけるにはそれしかないと思っています。G7も日本政府も「二国家解決(※)」を言い続けていますが、今の状況でそれだけを言うのは、イスラエルを利することにしかなりません。
国際的にはパレスチナという国家の領土は、今も1967年の国連決議で定められた境界線によって定義されているわけですが、イスラエルはそれを、侵略と入植によって事実上どんどん「再定義」していっているのが現状です。このままいけば、さらなる民族浄化、そしてガザだけではなくヨルダン川西岸地区でも同じことが起こるでしょう。それを止めるには、国際社会が「パレスチナ国家の承認」などで圧力をかけるしかないと考えています。
ただ、人道外交議員連盟でも日本パレスチナ友好議員連盟と共同で「国家承認を求める」要望書を政府に提出したのですが、この要望書に署名してくれた国会議員はわずか191人でした(編集部注:その後さらに増え、9月11日時点では206名に)。衆参あわせて700人以上いるうちの191人ですから、本当に少ないですよね。ガザで何が起きているのか、よく知らない人も多い。この状況をなんとか変えていきたいと思っています。
※二国家解決……国家として独立したパレスチナが、イスラエルと平和的に共存することを目指す考え方
◆ 日米地位協定を「互恵性のある協定」に
──国会質疑では「日米地位協定の改定」にも言及され、「石破総理ともこの問題について議論したことがある」と述べられました。
以前から僕は、日米地位協定を互恵性のある協定にしなくてはならないと言ってきました。互恵性とは「対等である」ということ、互いの軍隊に同じ権利を認め合うということです。
つまり、もし仮に日本の自衛隊がアメリカ本土に駐留した場合に、アメリカが自衛隊に許さないであろうことは、在日米軍にも認めないということ。駐留軍が好き放題できないように互いに縛りをかける、「自由なき駐留」の形をとるわけです。これは、主権国家同士が結ぶ地位協定であれば当たり前のことなのですが、今の日米地位協定はそうなっていません。
──安全基準や環境基準が非常に緩かったり、米軍が関係する事故や事件が起こったときの対応が日本にとって不利な条件になっていたりと、とても「自衛隊がアメリカに駐留したときに認められるのと同じ」とは思えない内容です。
伊勢崎 それを改めて対等にすることで、特にいま沖縄に偏っている重い基地負担を、かなり軽くすることができます。もちろん、米軍絡みの事故や事件がなくなることはないけれど、たとえば米軍の飛行機による騒音などは、基準を厳しくして軽減させることができるでしょう。
同時に、在日米軍基地が他国への攻撃に使われそうになったときに、それを日本が拒否する権利も、地位協定の中で担保する。つまり、「これからアメリカが始める戦争に在日米軍基地は使わせない」と、平時から世界に向けて発信することが、日本の国防にとって重要だと考えています。
ただ、地位協定をそのように改善するためには、まず先に国内法の改正が必須になってきます。
──なぜですか?
伊勢崎 国家が持つ軍事組織同士が対等な関係性を結ぶためには、双方の組織が国際的なルールにきちんと則って統制されている必要があります。その点で、日本の自衛隊の統制には大きな欠損がある。「戦争犯罪を裁く」ための法整備が存在しないのです。
民間人への攻撃をはじめとする戦争犯罪については、現場の実行犯よりもその上官、つまり指揮権、命令権のある人のほうを厳しく罰するというのが国際法の常識です。個人的な利益や恨みが動機となる一般の犯罪とは異なり、戦争犯罪はある政治的な意思のもと、国籍や民族などの属性を標的にする組織的な行為なので、個人よりも指揮・命令系統の責任が重視されるわけですね。
ところが、日本にはそうした特別な法体系──軍法のような──がありませんから、実行犯個人を罰して終わりということになってしまう。それどころか刑法の「国外犯規定(※)」によって、実行犯さえ適切に裁かれない可能性があります。自衛隊は軍隊ではないから「戦争犯罪」を起こすことはあり得ない、だから軍法や軍事法廷は必要ないというロジックがずっと用いられてきたんですね。
でも、そんなロジックは国際的には通用しません。
※国外犯規定……国外で起こった事件についても、殺人など重大な犯罪の場合は日本の法律を適用して処罰できるとする規定。ただし過失犯についての定めがないため過失による行為の場合は適用されない可能性がある
◆ 9条のメッセージを、世界に発信する
──日米地位協定を改定するには、そこを改める必要があるということですか。
伊勢崎 もちろんです。「戦争犯罪をきちんと裁く」というのは、国際法上は当たり前のルールですから、それを欠いたまま「対等な協定にしてくれ」と言っても通用するはずがない。数年前から、法律家や議員とともに「国際刑事法典の制定を国会に求める会」というグループを立ち上げ、研究や国会への働きかけを続けていたのですが、今度は議員として、「戦争犯罪をきちんと裁く」ための仕組み作りに取り組まなくてはならないと考えています。
こういう話をしていると「自衛隊を軍隊と認めるのか」と言われることがあるのですが、これはそういう問題ではありません。自衛隊員だけではなく、自警団などまったくの民間人であっても、きちんとした武器を持っていなくても、「○○人は敵だ」「あいつらをやっつけろ」といった呼び声に煽られて相手を傷つければ、その人たちは「戦力」と見なされ、その行為は戦争犯罪として糾弾される可能性がある。「自衛隊は軍隊かどうか」とは関係なく、そうした行為をしっかりと裁ける仕組みを作らなくてはならないんです。
議員会館の事務所には、国連などで活動していたときの写真も
──具体的には、どのような法改正が必要になるのでしょうか。
伊勢崎 憲法改正が必要だという意見もありますが、先に述べた研究グループで検証した結果、自衛隊法と刑法の一部改正で足るという結論になりました。まずは、それを一刻も早くやるべきだと考えています。
──憲法を変える必要はないと。
伊勢崎 といっても、憲法9条、とりわけ2項に問題がないとは言いません。「戦争犯罪を裁けない」現状を生んだのは、〈陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない〉と謳う9条2項です。先ほども言ったように、一切武装していない人たちであっても国際法上の「戦力」になる場合があって、そこに9条と国際法との齟齬がある。「9条の平和主義を守りたい」と考える人ほど、そのことは認識しておくべきでしょう。この問題から目をそらして、ただ条文を一言一句守ればそれでいいと考える人は、僕は本当の「護憲派」ではないと思っています。
──当選後のインタビューで「9条を、より9条にする」とも発言されていました。
伊勢崎 僕は、内戦終結後間もないアフガニスタンで武装解除に従事したときに9条の威力を実感しました。「平和憲法を持つ、軍事力を行使しない中立的な国」という日本のイメージが、僕の活動を守ってくれたのです。
本当に「9条を守りたい」と考えるのであれば、9条の精神を生かしてどう国際問題を解決に導くか、戦争をやめさせるか、その実践の方法を考えていくべきです。先ほどお話ししたガザの問題もそうだし、たとえば尖閣諸島をめぐる問題も、中国との共同統治を実現するなど武力ではない方法で解決していくことを目指さなくてはならない。僕は、9条がある国が領土をめぐって近隣諸国と対立していること自体が本来はおかしいと考えています。
戦争をすれば、自分たちの国だけではなく、相手の国の人たちも絶対に傷つきます。それを避けるために白旗を揚げて、とにかく戦争をやめようと呼びかける。それはとても勇気ある行為だし、それこそが本当の「9条の心」だと思います。そのメッセージを世界中に発信するとともに、日本を「戦争犯罪を世界でもっとも厳しく裁く国」にしていきたい。それが「9条を、より9条にする」ということです。
*