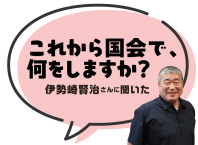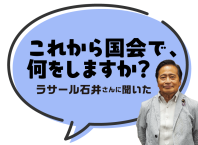はじめに
高市早苗首相は、自民党総裁に選出された際、「私自身もワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てる。働いて、働いて、働いて、働いて、働いていく」と語りました。自民党は7月の参院選公約でも「個人の意欲と能力を最大限いかせる社会を実現する」として「働きたい改革」を掲げ、働き方改革の見直しを検討する方針です。
報道によると人手不足に悩む経済界からの要望を受けてとのことですが、本来、政治家がすべき議論は、日本経済の失われた30年をどう取り戻すのか、ではないでしょうか。日本のGDPは世界4位へと低下し(今年にはインドに抜かれて、5位になるといわれています)、1人当たりのGDP(労働生産性)に至っては40位にまで落ち込んでいます(2000年には2位でした)。再生の鍵が「働きたい改革」だとは思えないのです。
そんな折、香川県三豊市に本社を置く産業機械メーカー、株式会社イナダの稲田覚(さとる)会長に話をお聞きする機会がありました。同社は1918年に創業。農業機械の製造・販売からスタートし、地域に根差した事業を基本としながら、現在はアジア諸国に生産拠点を広げています。2014年12月には、高性能のハイテク膜を使用し、川や池の水を安全な飲み水に変えるアクアキューブを地域企業との共同で開発。災害時に避難所などに生活用水を供給できることから、独立行政法人国際協力機構(JICA)の中小企業海外展開支援事業に採択されました。
日本経済の低迷は、日本という国が人を育てることに重きを置かなくなったからだという稲田会長。その真意と今後の日本のあり方について語っていただきました。
経済とは民のために
世の中がやらなければならないこと
──稲田会長は単に儲けることが経済活動ではないと言われます。
中学校の時、「経済」という言葉の意味がよくわかりませんでした。経験の「経」と済んだ(終わった)の「済」の組み合わせってなんだろうと。それが「経世済民」の略だとわかったのは大学生になってからです。民を救済するために世の中(社会)としてやらなければならないこと。世のため、人のための活動なのだと。
経済活動は利益を増やすことが目的ですが、ここでまた疑問が生まれました。「利益」ってなんだろうと。「利」とはお金を稼ぐことです。がんばっても儲からないことはあります。しかし、その過程で新しい出会いに恵まれたり、それが数年後に儲けにつながったりすることもある。それが「益」です。「利」と「益」は必ずしも同時に生まれるものではありません。「利」はなかったけれど、「益」はあったということもあります。利益=儲けと考えるから、経済が数字だけの世界に見えてしまう。商売は「利」と「益」を目指すから楽しいのです。
──おっしゃることはよくわかりますが、実際に楽しく仕事をしている人は多くないのではないでしょうか。生活のために働いていると割り切っている勤労者がほとんどというか。
それは夢がないからです。「最近の若者は夢をもたない」といった話ではありません。学校で先生が生徒に「夢はかならず叶う」なんて言っても、夢を実現したことのない子どもにはわからないですよね。机上ではなく、実際に経験しなければ。つまり社会人として働くことで夢は実現されるということです。企業であれば、トップが「自分は会社をこうしたいんだ」と方針を立て、社員とともに取り組む。そして、「社長が言っていたことが実現した。自分もできる」と思わせることが次の夢につながります。
──しかし、経営者が近視眼的に「利」を求めていては、難しいのではないでしょうか。
会社の経営状態はいい時もあれば、悪い時もあります。しかし、うまくいかなかったときでも「益」を見出せれば、事業は必ず成功します。目先の「利」を追い求めるだけの企業で人は育ちませんし、人が育たない企業に未来はありません。
ここ30年間の日本経済の停滞は、人が育ってこなかったことに原因があると思います。とりわけ未来のひとづくりのための施策をしてこなかった自民党政権に大きな責任がある。政府は人が本当に楽しく、喜びをもって働けるための制度づくりをしてきませんでした。
株式会社イナダの会長・稲田覚さん
中小企業は大企業の下請けではない
──この間の日本経済にはビッグテック(GAFAM=Google、Apple、Meta(旧Facebook)、Amazon、Microsoftの世界的に圧倒的な影響力を持つ巨大なIT企業群の総称)のような企業が生まれず、自動車産業の「一本足打法」といわれることもあります。同産業がトランプ関税で大騒ぎになったのは、すそ野が広く、影響を受ける会社が多いからではないでしょうか。
日本政府の行う「経済振興」は税制優遇措置や助成金などに限られ、企業が自らの力で立つための支援になっていませんでした。自動車産業においては、親会社、子会社、下請け、孫請けといった上下構造があるかもしれませんが、全産業において大企業の傘下にある中小企業の数は多くありません。日本語の大、中、小は縦のラインと思われがちですが、英語でいうhuge、large、medium、smallはフラットです。私は創業した祖父から「大企業と中小企業では市場が違う」と教わりました。「中小企業は大企業のためにあるのではない。地域の人のためにつくられたのだ」と。
──どういうことでしょうか。
大企業は市場の最大公約数をターゲットにします。マーケティングをして商品を開発し、完成したらコマーシャルで全国に展開する。一方、われわれのような中小企業の機械メーカーは、たとえば農家の困りごとを聞いて、「こういうものをこのくらいの価格で」という要望を受けて製品をつくります。100人に1人が買ってくれるような市場でモノやサービスを提供するのです。「これはたくさん売れる」というようなものを開発しても、大企業の資本力と営業力でシェアを奪われてしまう。だからニッチなものを選別して生き残っていけと祖父は言っていました。それを実践することでお客さんと顔の見える関係を築いていきました。
──大企業や富裕層が潤えば、その恩恵が中小企業や庶民にも及ぶというトリクルダウンの理論は当たらないということですね。
資源のない日本は外国からそれらを買って、加工して売る。貿易立国です。弊社における農業機械のシェアは低下していますが、いまも東南アジア向けの輸出は順調です。当該諸国の農業は日本よりも平均的に30年くらい後を追っています。日本は世界でも卓越した農業技術を発展させてきたので、現地へ行くと「この国の現状は日本の何年前のような段階だな」とわかるのです。それに合わせて製品を供給する。キーになるのはローテクです。
たとえば雨水が流れっぱなしの国の灌漑施設としては水車が適しています。かつてカンボジアで冷蔵庫製造を支援したことがありました。家電ではありません。木製です。中は観音開きの冷蔵室で、上部に氷を入れると冷気が下降していき、室内全体の生鮮食品を一定期間保存できる。この木製冷蔵庫によって、電気の通わない地域の方々の食中毒が減りました。こんな事業を大企業はやりませんよね。でも江戸時代後期から明治、大正、昭和初期までの技術で現在も使えるものがあるのです。自然と調和した知恵と技術を日本人はたくさんもっています。
両国の地方と地方の関係が
国家間同士の対立を抑止する
──お話を聞いていると、同郷の大平正芳元首相のことを思い出します。大平さんは軽武装経済主義を貫き、大蔵官僚時代には、上からの統制をやめ「国家自体の商人化」を図るという考えをまとめています。リーダーシップの名の下、政府に引っ張られて唯々諾々とついていくような国民はたいしたことを成し遂げられないとの確信があったようです(福永文夫著『大平正芳―「戦後保守」とは何か』中公新書より)。
歴代総理の中で一番尊敬できる人でした。彼の政策は、独自の人間観、歴史観、環境への視座、諸外国との共存から生まれたのだと思います。私の母方の祖父、上田義壽は県会議員をしており(後に香川県三豊郡高瀬町=現三豊市=の初代町長を務める)、当時の同県三豊郡和田村の村長をしていた大平正芳の兄である数光氏に「お前んとこの弟、27歳で横浜税務署長をしていたそうだが、帰ってきて国会議員に立候補してくれんか」と相談し、直接本人を説得しに上京しました。昭和27(1952)年のことです。
──大平さんは1962年に池田勇人内閣で外務大臣に就任して以降、1965年の日韓基本条約の締結、1972年の日中国交正常化に尽力しました。石破茂前首相が9月30日に韓国釜山を訪れ、李在明(イ・ジェミョン)大統領と会談した際には、田中角栄、大平正芳に通じる外交理念を感じました。
石破前首相が李大統領との会談で、国家間の関係は時に問題が生じる。そういうときに両国の地方と地方がつながっていることがとても重要だという趣旨の発言をされたことに感銘を受けました。
私は三豊市国際交流協会会長として、同市の姉妹都市である韓国慶尚南道陜川(ハプチョン)郡と行政間・経済青少年交流の活動をしているのですが、姉妹都市という考え方は、1956年に米国のアイゼンハワー大統領が提唱した都市提携運動「People to People Program」(市民から市民への交流計画)から生まれました。アイゼンハワーは、第二次世界大戦において連合軍を指揮した将軍であり、あの戦争を総括するなかで、国と国との関係はときに一部の人間によって暴走するという教訓を得、それを抑止するためにはお互いの国の民間人の交流が必要だとの考えに至ったそうです。
──稲田会長は「交流」とは何かについてもよく言及されます。
行政が国際交流をやろうとすると、たとえば住民向けに外国語の教室を開いたりするところからスタートします。それは交流ではありません。お互いにもっているものをオープンにして、足りないものを補い合うことが経済交流です。日本に住む外国人に私たちが日本語を教え、それによってお互いの理解が深まり、人手が足りない日本の分野で働いてもらう。お互いの利益になるのが国際交流です。
──若い国会議員は在外公館に出るべきと提唱されていますね。
日本の在外公館には外務省だけでなく、各省庁から職員が出向しています。いわば政府の支店です。にもかかわらず、そこに国会議員はいない。彼らが若いころに海外へ留学していれば、相手国のエリートと友人になれるかもしれませんが、誰にでもできることではありません。ならば議員バッジをつけたら日本大使館に駐在し、相手国の政府関係者との人間関係をつくる。いずれ相手が大臣になったら、日本の外交にとっての財産になります。
そして帰国後は地元の選挙区に戻る。そうすれば自治体の長や幹部、経済界の人間がわざわざ東京まで陳情に出向く必要はなくなります。余計なコストもかかりません。当選回数が6~7回になった議員は、政府の中枢で働く可能性が高くなるから首都にいる。つまり国会議員の3分の1は海外、3分の1は地方、3分の1は首都に分かれる。通信手段が発達しているのですから、コミュニケーションも可能ですし、何よりそうした環境が政治家を育てます。冒頭の言葉に倣えば、目先の「利」を追い求めるだけの国で人は育ちませんし、人が育たない国に未来はないのです。
(取材・構成/芳地隆之)
写真は、現在展開中の高麗人参スプラウト事業。稲田氏は高瀬茶業組合(三豊市高瀬町)の統括本部長も務める。県内の茶の栽培面積のうち8割を高瀬町が占めるが、近年は生産者の減少で生産量も減少傾向にあるなか、三豊市と姉妹都市を結ぶ慶尚南道陜川郡から小さな根を輸入。高瀬茶業組合が水耕栽培で育て、三つ葉に似た若芽が育った段階で首都圏のレストランなどに出荷している