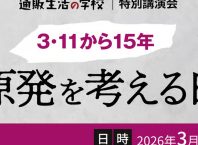マガジン9で、2011年10月から2016年末まで、5年あまりにわたって連載された「原発震災後の半難民生活」が『「旅する蝶」のように ある原発離散家族の物語』のタイトルで書籍化されました(リベルタ出版より)。タイトルにあるように、描かれているのは2011年3月の東日本大震災による福島第一原発事故の後、北関東と沖縄に「離散」して暮らすことになったある家族の物語です。
著者の岩真千さんは、栃木県宇都宮市にある大学の教員。震災時は妻と3歳の娘との3人暮らしで、数カ月後には2人目の子どもが生まれる予定でした。原発事故発生から数日後に、放射能の影響を危惧し、母とその再婚相手を頼って沖縄へと避難。しかし、「帰っても安全」との確証は持てないまま時間が過ぎ、1カ月後には仕事のため家族を残して宇都宮へ戻るという選択をすることになります。自宅に1人暮らし、連休を利用して沖縄の家族に会いに行く、「離散生活」のはじまりでした。
放射能の影響に対する考え方の違い、出産を控え知らない土地に暮らす妻のストレス、地元で親しくしていたはずの知人たちから投げかけられる、「避難した」ことへの心ない言葉…。そうした状況に心身をすり減らす夫婦の間には、次第に激しい言い争いが繰り返されるようになります。
並行して、著者が目を向けるようになったのは、沖縄での滞在中、あちこちに見え隠れする「戦争」の影でした。祖母が問わず語りに口にする戦争の記憶、道路を我が物顔に走る米軍の装甲車や戦闘ヘリの爆音、元米軍基地勤務の義父の何気ない言葉…。かつては自分とは無関係のように見えていたそうした光景を生々しく感じ取りながら、著者は「この国は、昔から今までずっと『戦争中』だったのではないか」とつぶやくのです。
もちろん連載中には毎回読んでいたのですが、書籍としてまとまった形で読むことで、時間の流れ──事故直後の混乱と不安、長引く「離散」への迷いや苛立ち──が、改めてはっきりと感じられました。同時に、東京にいた自分もほんの一端とはいえ経験していたはずの、不安で叫び出しそうだったあの震災直後の空気が、いかに心の中で遠いものになっていたかにも気付かされます。
後書きにはこうあります。
〈原発事故後に起きた出来事の大半が「なかったこと」にされている今日、それだけはさせまい、という一心でした〉
先日も茨城県の原子力施設で作業員が被曝する事故がありましたが、ひたすら原子力推進の方向に突き進む政治を見ていると、事故後に起きた出来事どころか、あの事故そのものを「なかったこと」にしようとしているかのようにも思えます。
本書は「ある原発離散家族の物語」ですが、あの事故で同じように「離散」を経験しなくてはならなかった人たち、「離散」を避けるために避難をあきらめた人たちは、いったいどのくらいいたことか。「離散」にはいたらなくても、さまざまな理由で故郷を離れたまま暮らしている人たちも、まだまだ大勢いることは言うまでもありません。そしてそのそれぞれに、当人たちにしか分からない「物語」があることでしょう。
そうした事実を「なかったこと」にさせないために。本書のページをめくりながら、今はまだ語られていない無数の物語にも、思いを馳せたいと思います。
(西村リユ)
『「旅する蝶」のように ある原発離散家族の物語』(リベルタ出版)