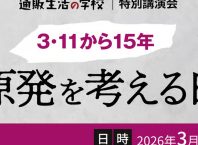相模原市の「津久井やまゆり園」事件から1年。マスコミで再びあの惨劇が語られることとなって、当時の悪寒が生々しく蘇ってきた。あまりにもむごい事件だったからだけではない。被告の男が私たちの意識の奥底に手を突っ込み、ほら、お前にだってあるだろうと、「内なる差別意識」をむんずとつかみ、白日の下にさらしたからだ。その衝撃から私は立ち直ることができないでいる。
思い出すのは数十年前の出来事である。ある公園のトイレの前で車いすにのった一人の男性と遭遇した。脳性麻痺と思われるその男性はトイレに行きたいのだが、トイレの入り口に段差があって車いすでは上がれない、というふうだった。私は車椅子を押して男性用トイレに入った。すると彼は不自由な視線と動作でしきりと訴える。ハッとした。「ズボンのチャックを開けてくれ」といっているのではないか。とっさに「私にはできません、男の人に頼んでください」と言って飛び出した。胸がドキドキして一目散に公園を出た。彼がなにを言いたかったのか、今でもわからない。若かった私は直感的にセクハラだと感じたが、本当に困っていたのかもしれない。親切ぶって途中まで手を貸したものの、勝手な思い込みで逃げたのかもしれない。偽善者の私……。
以来、「“普通”でない人」に対して臆病になった。電車で大声で独り言を言いながらうろうろしている人がいれば、身を固くして目が合わないようにする。さりげなく別の車両に移る。とにかくかかわりたくない。
この「普通でない人」に対する反射的な忌避感は、社会全体にもあると思う。たとえば通り魔的な殺人事件が起こったとする。「容疑者は意味不明なことを言っている……精神科に通院していた……」などと報道されると「そんな人を野放しにしていたのが悪い」「もっと早く施設に収容していれば、事件は防げたのに」と、善男善女は語り合う。コミュニケーションがとれない人を“不審者”とみなして、健全で安全、快適な市民社会から排除しようとする深層心理は、一歩間違えば「内なるウエマツ」に暗転するのではないか。
あの事件の後さまざまなコメントが巷にあふれた。「命の重さは平等だ」「生きる価値のない人などいない」という正論のなかで印象に残ったのは、和光大学名誉教授・最首悟さんの言葉だ。全共闘世代には東大闘争の闘士として知られる学者で、ダウン症で知的障害がある娘と暮らす最首さんは「命は尊いとか、地球より重いといったきれい事はいえない。〈あの子がいなければ〉と〈あの子がいてくれたら〉という相容れない気持ちが表裏一体となり日々過ごしている」と語る。当事者ならではの重い言葉だった。
最首さんはさらに「与死」に言及する。与死は、臓器移植の関連でちらつき始めた議論で、死に生物学的な規定を設けず、国民の合意によって合法的にある一定の状態に達した障害者や高齢者に死を与えようという考え方。2025年には団塊の世代が後期高齢者になり、認知症患者は700万人に達すると予想される。そうなったとき生産能力のない人に、一方的に社会資源を注ぎ続ける余力が、果たしてあるだろうか。「命の選別は許されない」というポリティカルコレクトネスは持ちこたえられるのか。そこに浮上するのは尊厳死、安楽死、そして与死。「超高齢化社会に向かって、社会に冷気が忍び寄っている」と最首さん。
もう一人、胸に突き刺さったのは作家・辺見庸氏の発言。「容疑者は〈生きるに値する存在〉と〈生きるに値しない存在〉を分類した。世間はそれを狂気と断じる。だが大方の人は、彼が死刑になっても当然と、何の疑いもなく思うだろう。あんなやつ、生きるに値しない、と」。辺見氏の指摘にはいつもハッとさせられる。私たちもまた「分類」しているのではないか。
事件の本質とされる優生思想はナチスの専売特許ではない。日本でもつい20年ほど前まで「優生保護法」があった。「悪質な遺伝性疾患の素質を持つもの」に対する不妊手術や、優生学的理由による中絶の法的根拠であり、町の産婦人科の看板としても見慣れた表現だった。今では母体保護法に改正されたが、さらに微妙な「出生前診断」が急速に進化、普及している。当事者の自己決定権は尊重されるべきだし、福祉制度の不備こそが問題だとは思うが、「命の選別」といえなくもない。
私は39歳ではからずも妊娠した。高齢妊娠だからと医師は羊水検査をすすめたし、知人のフランス人女性は「検査をしないなんて信じられない」と肩をすくめた。でも、しなかった。というか思いも及ばなかった。命の選別はいけないとか、頭で考えたわけではない。人智を越えた自然の摂理にただただ圧倒されて、自己決定とか生命倫理なんて小ざかしい知恵は吹っ飛び、あるがままに身を任せるしかなかった。
相模原事件がえぐりだした命の問題は深く、尊厳死も出生前診断も、死刑も、頭で考えてもなかなか答えは出ない。ただそこにある命に素直に向き合いたい。
(板倉久子)