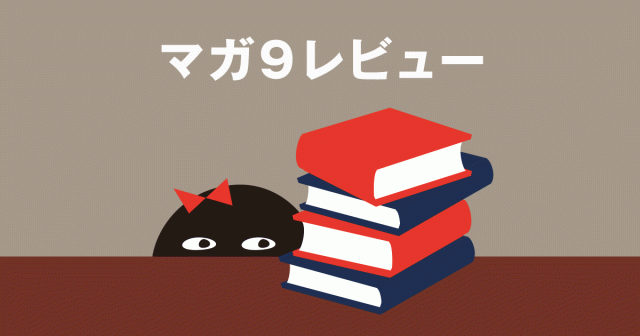原発の闇に光をあてる、読み応え十分の「原発本」
最近、原発に関する報道がめっきり減っているように思う。新聞もTVニュースも「原発再稼働」については小さく報道するが、福島事故の現状や放射性障害、原発そのものやエネルギー政策などについてのニュースはあまり目につかなくなってしまった。
福島事故から6年が経ち、放射能に脅える日々を忘れ、元の「電気生活」に戻ってしまった人たちにとって、原発はもう興味をひかないものになってしまったのかもしれない。
そんな折に出版されたのが本書『日本はなぜ原発を拒めないのか──国家の闇へ』(山岡淳一郎、青灯社、1600円+税)である。
日本という国が、あの巨大事故の後でもなお原発を拒否できないのはなぜか、という根源的な疑問を、著者は徹底的に突きつめていく。
きっかけは「東芝崩壊」だった。巨大企業の東芝が壊れていく過程を克明に追う。そこに見えてくるのは、原発ルネサンスという砂上の楼閣に狂った経済官僚と、目先の利益に踊った企業経営者らの癒着関係だった。国家事業としての原発を企業に肩代わりさせて、政治家や官僚は何を得ようとしたか。
それを裏で支えたのが、カネという接着剤で結びついた「原子力ペンタゴン」と称される者たち。すなわち、政治家・官僚・財界・学界・報道の腐った五角関係だった。著者の筆は、その深い闇に分け入る。正力松太郎を筆頭とする政治家(報道)と電力連合、原発立地を各個撃破していく推進派。
だがその破綻は、福島事故を奇貨として誰の目にも明らかになる。コスト、人事、国際情勢、エネルギー基本計画崩壊…などの面から露わになっていく。
それでもなお、日本が原発を拒否できないのはなぜか。カネにまつわる話はおくとして、根底には右派政治家たちの「核武装への野望」があると、著者は指摘する。それが国際的な孤立を日本にもたらすものだとしても「強い国家」を夢想する政治家たちは、その野望を捨てられない。
しかし、原発拒否の民意はもはや曲げられないと著者は見る。それこそが、被災地のほんとうの「再興」だというのだ。
詳細に調査した資料としても貴重だが、久しぶりに手にしたずっしりと読み応えのある「原発本」である。
(椎野洋二)