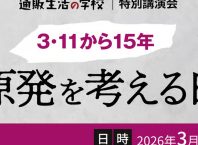今年4月に公開されて大きな話題を呼んでいる、映画『主戦場』。旧日本軍「慰安婦」の問題について、研究者や人権活動家、問題の存在そのものを否定する人など、さまざまな立場の人たちがスクリーン上で「論争」を繰り広げる異色のドキュメンタリーです。
日系アメリカ人のミキ・デザキ監督には、公開前に「この人に聞きたい」に登場いただいています。そのデザキ監督が今月3日、映画に寄せられた批判に対しての「反論」記者会見を開くと聞き、出席してきました。
「反論」の対象はその5日前、5月30日に都内で開かれた記者会見。映画の中に登場している、「慰安婦」問題を否定する立場の論者7名が「学術研究だと聞いたから協力したのであって、商業映画への出演は許諾していない」「事前に映像を見せるという約束が守られなかった」などと主張、映画の上映差し止めを求める抗議声明を発表したのです(記者会見には、「新しい歴史教科書をつくる会」の藤岡信勝会長ら3名のみが出席)。
会見の席で、デザキ監督はこの抗議声明の内容に真っ向から反論。取材時、映画を「大学院の卒業プロジェクトとして制作する」と説明したのは事実ながら、「出来がよければ一般公開も考えている」とも伝えていたこと、一部の出演者の要求に応じ、公開前にそれぞれの出演部分映像を送付したものの何の反応も返ってなかったことなどを、出演者との間に交わした合意書や承諾書を示しながら説明してくれました。
「また、出演者には公開前、計8回行われた試写会の案内も送付しています。もし、その段階で不満の声があれば、合意書に記してあったとおり、映画のクレジット部分に(『出演者からこうした声があった』という)メッセージを加えるつもりでいました。しかし実際には、公開まで何の連絡もなかったのです」
先の藤岡氏らの記者会見では、内容が「フェア」なものになっておらず、「一方的なプロパガンダ映画だ」との主張も展開されました。デザキ氏は、「物事がフェアであるかどうかという判断は常に主観的なものです。もし、映画が彼らの主張に沿った(『慰安婦』問題の存在を否定するような)内容になっていたら、彼らは『これ以上フェアな映画はない』と言っていただろうと確信しています」と指摘した上で、こうも述べました。
「さまざまな意見に耳を傾けた上で、自分なりの結論を映画の中に入れることが、責任を果たすことだと考えました。すべての主張に同等の説得力があるわけではないことを示すのが重要だと思ったのです。私は、どちらの意見に説得力があるかを自分で判断して結論を導いたし、そのプロセスは映画の中で明らかになっています。それを見た上で、観客は私の結論に同意することも、同意しないこともできるのだから、プロパガンダとはいえません。私の出した結論そのものは重要ではなくて、観客自身が映画を見てそれぞれの論点について検証することを推奨しているのです」
また、もっとも考えさせられたのは、デザキ監督の次のような指摘でした。
「彼らがこうして抗議してきたのは、この映画を好きではなく、評判を下げて多くの人に見られないようにしたいと考えているからでしょう。発言した内容について『恥ずかしい』と思っているのかもしれません。しかし、私は彼らの言葉をねじ曲げたり、一部分だけ切り取ったりはしておらず、映画の中で語られていることは、すでにこれまで彼らが話したり、書いたりしてきた内容と変わらない。それなのに、なぜ彼らがこの映画を見てほしくないと思うのか、私には分かりません」
映画『主戦場』の中で、「慰安婦」問題を否定する人たちの口から飛び出す発言の中には、解釈の違いや誤解というレベルではないあまりにもめちゃくちゃな歴史認識に立ったものや、思わず耳を塞ぎたくなるほど差別的なものも少なくありません。けれど、デザキ監督が言うように、実はそうした発言は、過去にも雑誌やインターネットをはじめさまざまな場所ですでに繰り返し語られてきたものでもあります。明らかな嘘も含むそうした言説が、特に大きな問題になることもなく流通してきた(それどころか、ときに日本政府自身がそこに加担してきた)状況の危うさを、改めて思いました。
そうした状況を生み出してきた責任の一端が、「慰安婦」問題を「タブー」としてなかなか扱わず、歴史修正主義の言説のおかしさをきちんと指摘してこなかったメディアにあることは言うまでもありません。立ち見も出るほどの超満員だったこの日の記者会見ですが、これを機に、映画に伴う一連の「騒動」だけではなく、映画の中で語られている内容、そして「慰安婦」問題そのものについても、もっとオープンに報道され、議論されるようになっていってほしい。それでこそ、この映画がつくられ、公開された意味があるのではないか。そんなことを考えました。
(西村リユ)