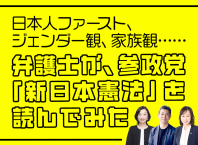新型コロナに振り回されるように過ぎた1年でした。家にいる時間が長かった分、いつもより読書や映画鑑賞をする機会があったという人もいるのではないでしょうか。「STAY HOME」で過ごす年末年始に向けて、マガジン9スタッフがおすすめの書籍や映像作品をリストアップしました。この機会にぜひどうぞ!
なお、今週の「マガジン9」は年末年始合併号となり、来週12月30日(水)の更新はお休みです。次回更新は2012年1月6日(水)予定。今年もたくさんの方に支えていただき、ありがとうございました。来年もどうぞ、よろしくお願いいたします。
-
『風よ あらしよ』(村山由佳著/集英社) -
恋愛小説の名手による、アナキスト伊藤野枝の鮮烈な生涯(仲松亨徳)
村山さんと言えば恋愛小説の名手というイメージが強い。そんな彼女が取り上げたのはアナキストの伊藤野枝。28年の人生で3度の結婚をし、7人の子を産んだ。女性への抑圧が厳しいなか、真っ先に声を上げたひとりである野枝の短くも鮮烈な生涯を描いた長編小説だ。
もっと読む
物語は、関東大震災後、野枝が憲兵に拘束される序章から始まる。一転、第一章からは九州での幼少期が始まり、次第に野枝は成長し、さまざまな人々と関わっていく。その悲惨な最期を読者は知っているわけで、野枝が愛した辻潤や大杉栄との情熱的なラブシーンは、恋愛小説の名手であれば当然の美しさだが、それが実に切ない。激しい野枝に対して男はどれもだらしない。野枝のほうから恋に落ちるのに、その男を踏み台にしてさらに強くなっていく。前述の辻も大杉も、年少の女性である野枝からその強さを「与えられる」対象のようだ。野枝が身を投ずる青鞜などの女性解放運動の面々も、多彩なキャラクターがあり、その活写も楽しい。
本作を一気に読んだが、女性の抑圧、言論弾圧など、100年前のこととは思えない。男社会に異議申し立てした彼女らの運動は、現在のBLM(ブラック・ライブズ・マター)や#MeTooにも通じる「抵抗」とつながっている。
野枝に負けぬほどの熱量が感じられた650ページ超の大作。その陰には膨大な資料収集と緻密な読み込みがあったことだろう。村山さんへの野枝の「憑依」を感じる作品だった。
閉じる
*
-
ドキュメンタリー『13th 憲法修正第13条』(Netflix制作) -
差別はこうして作られる(田端薫)
アメリカの黒人差別って、こんなにも巧みに仕組まれていたのか——。2020年アメリカのみならず全世界を揺さぶったBLM(ブラック・ライブズ・マター)運動の背景が知りたくて、2016年Netflix制作のドキュメンタリー『13th 憲法修正第13条』(現在、youtubeで無料公開中(字幕付き)を視聴して舌を巻いた。そして悟った。黒人差別は、「未だに人々の心に残っている問題」でなく、支配のために必要不可欠な制度として不断にバージョンアップされ、今日に至っているのだ、と。
タイトルになっているアメリカ合衆国憲法修正第13条は、1863年のリンカーン大統領の奴隷解放宣言をうけて65年に発効された条文で、これによりすべてのアメリカ人は奴隷制から解放されるはずだった。だがそこには抜け穴があった。「隷属的労働は禁止、ただし犯罪者はそのかぎりではない」。この例外規定が抜け穴となって、黒人差別は連綿と固定化され、制度化されていくことになる。
もっと読む
奴隷制度から解放されたものの、黒人たちには仕事も住むところもなく、路頭に迷った。そのかれらを徘徊や放浪などのささいな罪で逮捕して刑務所に送り込み、無償で鉄道や道路建設にかり出した。南北戦争で疲弊した経済を立て直すためには必要な仕組みだったのだ。刑務所が奴隷農場の代わりになった。20世紀半ばに公民権運動が起きたときも、この13条の抜け穴が使われた。人口増に伴って急増し始めた犯罪は、公民権運動のせいにされた。「黒人に自由を与えたから、治安が悪くなった」「黒人は野蛮で凶暴だ、犯罪者には厳罰を、刑務所に閉じ込めろ」。人々の恐怖心をあおり、それに「法と秩序」を対置させる支配の構造は、ニクソンからレーガン、さらにはトランプに受け継がれていく。
1980年代に始まった「麻薬戦争」(厳格な麻薬取締法を軸とした麻薬撲滅政策)にも、黒人を刑務所に送り込むための仕掛けがあった。黒人社会に流通する安価な固形コカイン「クラック」に対して、白人たちが使う粉末コカインの100倍の懲役年数が科せられたのだ。大量の黒人が刑務所に収監され、刑務所が満杯になった。
そこに登場したのが民間刑務所だ。犯罪者は増加の一途をたどり、刑務所ビジネスは成長産業になり、政治への発言力も増した。こうして刑事司法と民間刑務所の利益が合体した「産獄複合体」が形成された。受刑者の安定供給のために、刑の厳罰化長期化、警察の重武装化が加速する。テレビなどで手錠をかけられる黒人少年の映像が毎日のように流され、黒人イコール犯罪者のイメージが増幅された。
「収監や保釈後のGPS監視などで、隷属状態におかれた黒人の数は1850年代の奴隷より多い」「刑務所収監者の40%は、人口の6.5%にすぎない黒人」「アメリカ黒人が生涯のうちに収監される可能性は3人にひとり、対して白人男性は17人にひとり」など、驚くべき数字が矢継ぎ早に画面に現れ、1時間45分息つく間もなく見入った。
「差別はいけないけれど、犯罪者を刑務所に入れるのは当たり前」「法と秩序は大切だ」この素朴な正義感を隠れ蓑にして、あらゆる差別が世界中で意図的に再生産されていることを、忘れてはならない。
閉じる
*
-
「子どもを守る言葉 『同意』って何? YES、NOは自分が決める!」(レイチェル・ブライアン作、中井はるの訳/集英社) -
こどもの時に出会いたかった本(塚田ひさこ)
この本の筆者、レイチェル・ブライアンは、1億5千万人が見たという 「Tea Consent(お茶と同意)」を作ったアニメーターであり、これが初の著作となります。ちなみにTea Consentの動画は、日本でも刑法の性犯罪規定見直しの議論が高まる中、「性的同意」の概念についてわかりやすいと取り上げられ話題になっていたので、ご存知の方も多いでしょう。
レイチェルは、世界中で問題になっている子どもを取り巻く困難な環境、いじめ、抑圧、性暴力などから子どもを守るために、この本を作りました。
この本のキーワードは「同意」と「バウンダリー(境界線)」ですが、前置きとして最初のページに、「キミは『キミ』という世界にたったひとつだけの大切な国の王みたいなものなので、キミがキミ自身の『王』であり、からだも心も100%自分のもの。だから自分で決めていいんだよ」と教えてくれています。
もっと読む
おお、これはまるで一人ひとりが、かけがえのない存在であると「個人の尊厳」を保障する憲法13条そのものではないですか! と、最初からがっつり心を掴まれました。聞き慣れない「バウンダリー」という言葉については、「キミが大丈夫だと思うことと、嫌だと思うことの間を分ける見えない線のようなもので、ひとりひとり相手によって違う」と、具体的な例を挙げてイラストとともに解説をしています。そして、それを決めるのも「キミ自身」であり、自分の気持ちやからだに感じる直感を見逃さないで、「いやならいやだとちゃんと伝えることが大事だけど、それでもダメなら逃げていいいんだよ」と教えてくれています。
読みながら、ああ、私もこどもの時にこの本に出会いたかったと心底思いました。あの時、嫌だと言ったら大人に突然殴られたとか、本当に親や学校の先生の理不尽さに、よく我慢していたなとか、いろんなことが思い出されて、泣けてくるほどでした。もちろん、この年になった私がそう感じたように、大人にとっても、励まされるし、癒しにもなるし、気づきにもなるし、そしてやっぱり「自分のことは自分で決めていい」という当たり前の決断に対して勇気が持てます。
世界はどんどん悪くなっているのではないか、と絶望的な気持ちになることも少なくない昨今ですが、「日本国憲法」や「世界人権宣言」など人間の叡智の結集の土台が今もあり、この本が生まれたように、少しずつでもその理念に現実社会が近づいていってもいる。そんな「希望」となる本書との出会いでした。
ちなみに「同意」は、最近では、日本学術会議が「同意のない性交は犯罪である」と、国際的な人権基準を反映した刑法改正を求める提言をまとめたことがニュースにもなりました。「同意」という言葉が注目を集めているタイミングで、子どもにも「同意」の概念がわかる内容の本書が出たことも、また良かったです。
閉じる
*
-
ベルリン 3部作(クラウス・コルドン著、酒寄進一訳/岩波少年文庫) -
20世紀の歴史が凝縮された都市の物語(芳地隆之)
ナチスの台頭前夜からその体制が崩壊するまでを描くこの物語は、ベルリンに暮らすゲープハルト一家と隣人たちの暮らしを中心に進む。
まずは前夜――。第1部『ベルリン1919 赤い水平』の主人公は長男のヘルムート(通称「ヘレ」)。第一世界大戦で対フランス戦線に出征し、戦地で片腕をなくした父、ルディを彼と家族が迎えるところから始まる。愛国心を胸に戦場へ向かったルディは、夥しい無駄な死を目にし、平和を目指すため共産党に入党した。
戦争は終わり、敗戦国となったドイツ帝国は消滅し、革命の機運が高まっていた。しかし、ドイツ社会民主党主導の政権はドイツ共産党とことごとく対立する。ドイツ共産党の前身であるスパルクス団を結成したローザ・ルクセンブルグ、カール・リープクネヒトらは義勇兵を使って殺害された。
革命は頓挫。その間隙をぬうように力をつけていくのがアドルフ・ヒトラーである。社会民主党と共産党は、互いに手を結ぶくらいなら、アドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)と組んだ方がましだと考えていた。
もっと読む
そして台頭――。第2部『ベルリン1933 壁を背にして』の主人公はヘレの弟、ハンスだ。彼はヘレとともにヒトラーを目撃する。1933年1月、前年の選挙でナチスを第一党にまで押し上げたヒトラーが首相に就任。首相官邸の窓辺に立つ彼の下には大勢の市民が集まってきた。女性たちはヒトラーに向かってバラを投げかけ、ドイツ国歌が鳴り響くなか、無数のたいまつの火が揺れ、鍵十字の旗がたなびく。人々は「ハイル、ハイル、ハイル(万歳)」と叫び、ヒトラーに敬礼する。
ハンスはヘレとともに危険な流れを食い止めるべく、反ナチス抵抗運動に身を投じるが、2人がヒトラーを目撃してまもなく、ナチスは国会議事堂を放火。犯人は共産党員だとして党員を根こそぎ逮捕する。
街では褐色の制服を着たナチスの武装組織、突撃隊が我が物顔で闊歩するようになり、ヘレと妻のユッタ、やがてはハンスも刑務所に収監され、その後、強制収容所に送られることになる。
やがて崩壊――。第3部『ベルリン1945 はじめての春』の主人公はエンネ、ヘレの娘だ。生まれて間もなくして両親が逮捕されたため、彼女は祖父母に育てられていた。
ここで描かれるのはエンネの目から見た敗戦と戦後の混乱である。英米軍による空襲でドイツの首都はほぼ壊滅し、進軍してきたソ連軍兵士は略奪や凌辱を繰り返す。敗戦後に明らかにされる強制収容所の実態を知る大多数は、ナチスへの迎合を「仕方がなかった」として忘れようとする。
その後、ドイツは東西に分断されるわけだが、それを暗示するところで終わるこの3部作は、歴史の流れを叙事的に綴る大河小説ではなく、20世紀前半のドイツの歴史の転換点となる年に、人々がどのような暮らしのなかで、何を思い、どのような行動をとったのか、庶民の視点、地べたに近いところから語っていく。
ちなみに11月9日はドイツにとって特別な日だ。1918年のその日、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が廃位し、ドイツ帝国は終焉を迎えた。それから20年後の1938月のその日には、ナチス政権下のドイツ全土でユダヤ人教会やユダヤ人の商店などがナチスの親衛隊や民衆によって破壊される「クリスタル・ナハト」が起こった(割られたショーウィンドウのガラスが街灯の下できらきら光っていたから、そう名づけられた)。そして71年後のその日、東西ベルリンを分断していた壁が崩れ落ちる。
20世紀の歴史が凝縮された都市。それがベルリンであった。
閉じる
*
-
『フラワーデモを記録する』(フラワーデモ編/エトセトラブックス) -
社会の空気を大きく変えた1年間(海部京子)
2019年3月、性暴力事件の無罪判決が4件続く。フラワーデモは、これらの判決とすべての性暴力に抗議する運動として、4月11日に東京と大阪で始まった。毎月11日に行われるデモは月を追うごとに全国の都市に広がり、1年で47都道府県に開催組織ができた。そのフラワーデモの2019年4月から2020年3月までの活動をまとめたのが『フラワーデモを記録する』である。
本書は、各地でデモを主催し声を上げた女性、さまざまな性暴力事件を報じてきた女性記者、性暴力による被害者を支えたたかってきた弁護士らの寄稿を中心に構成されている。そこに記されているのは、フラワーデモが社会の空気を変えた1年間の軌跡だ。
私自身、初めてフラワーデモに足を運んだ日のことは忘れられない。東京駅を背にして、行幸通りを進むと、広々とした歩道に人の輪ができていた。自らが受けた性暴力の痛みを語る女性たち。そして花や「#Me Too」「#With You」のプラカードを手に、その言葉をただただ受け止めようとする女性たち。
もっと読む
レイプは魂の殺人と言われている。女性たちのスピーチが続いているときに、ふと周囲を見渡すと、ライトアップされた東京駅の威容があり、瀟洒なビルが建ち並び、そこで聞こえてくる言葉は魂の叫びだった。いまここで、何が起きているんだろう? 何かが大きく動き出している……。そう感じたのだった。フラワーデモを開催する都市はどんどん増えていき、2020年3月までの延べ参加人数は10,990人にのぼるという。その中で、2019年12月には伊藤詩織さんの民事裁判の勝訴があり、2020年に入ると、前年の性暴力事件の無罪判決が二審で逆転有罪となる例も続いた。フラワーデモは、1年をかけて女性たちの行動をうながし、「被害を受けた女性は黙らない」という社会の空気をつくり、司法をも動かしたのだ。
本書に寄稿している角田由紀子弁護士はこう書いている。
「2019年から2020年にかけての時間は、日本の女性の権利の歴史に残るに違いない。あの時の女性たちは、新しい歴史のページをめくったのだと、後世の人々が思い出してくれるかもしれない。」
フラワーデモは、角田弁護士ら長年性暴力の問題に取り組んできた女性たちと、若い世代が連帯する場でもあった。全国の幅広い世代の女性がつながり、この国の女性運動の歩みを大きく進めたのである。そう考えると『フラワーデモを記録する』は、50年後、100年後に、女性運動史を振り返るときに貴重な資料となる書でもあるのだろう。
閉じる
*
-
『特捜部Q アサドの祈り』(ユッシ・エーズラ・オールスン著、吉田奈保子訳/早川書房) -
寝不足になること必定(鈴木耕)
ぼくの愛してやまない『特捜部Q』シリーズの第8弾。今回も十分に堪能させてもらった。
特捜部Qという過去の未解決事件を担当するコペンハーゲン警察の部署の一員のアサドは、イスラム系の移民の出だ。これまで、数々の難事件を、マーク・カール刑事やローセ捜査員とともに解決してきた。シリーズ中では、心優しい、しかもとぼけた味わいの長身の人物として描かれている。シリーズの中ではほぼ副主人公といった役どころ。そのアサドに、今回は焦点があたる。
もっと読む
アサドの過去が、それも凄まじい過去が語られる。なぜ彼がこれまで、自分の過去を一切明かさなかったのか。親族はどこか、自宅の場所さえ、近しいものにも知らせてはいなかった。なぜか。それが今回の物語である。テロリズムと拷問と人質……。その人質が愛する妻であり、忘れられない娘たちであったら、自分の命など惜しくはない。絶対に救出する。
本書の帯にあるように「たとえ自分の命を失うことになろうとも――」。
今回はいつもの流れとはまるで違うハードボイルドタッチだ。ドイツの大都市を舞台に、大規模テロを阻止できるか、そして自分の妻や子を救出できるか。
血と汗と涙と、そして祈りに満ちた分厚い物語。
翌日の仕事のある人は、夜読むのをやめたほうがいい。読み始めたら止まらない。眠れなくなる、寝不足になるのは必定である。
閉じる
*
-
『過激派の時代』(北井一夫著/平凡社) -
若者たちは、「過激派」だったのか?(鈴木耕)
「過激派」っていったい何だろう。この写真集は、それを問いかける。
ページを開く。収録されているのは、ほとんどが学生や市民が1960年代末に繰り広げたデモの写真である。多くの若者の顔が映し出されている。では、デモに参加した若者たちが「過激派」だったのか? ぼくが写っていてもおかしくない写真の数々。抗議をしている顔、訴えている顔、そして闘っている顔。それが「過激派」だったのか。
例えば1967年10月8日の羽田周辺。ぼくもそこにいたのだ。ただし、ヘルメットもかぶらずゲバ棒も持たず、ぼくはただ「佐藤訪米阻止」(当時の佐藤栄作首相が米ニクソン大統領とベトナム戦争について協議するための訪米=少なくとも学生や若者たちはそう捉えていた)というスローガンに共鳴してデモに参加したのだった。
もっと読む
機動隊に追い回されて逃げまどっていたぼくが「過激派」だったのだろうか。この写真集の中には、ぼくのような若者がたくさん存在する。時代の顔がぼくらだった。それを記録したのがこの写真集だ。大人たち(ことに政治を牛耳る大人たち)への抵抗・否定という意味では、若さは過激だったのかもしれない。だが、過激ではない若者にどんな価値があるか? だから、ここでいう「過激派」とは、若さへの賛辞であると思っていい。写真家の北井氏は、ぼくより1歳だけ年上だ。彼もまた、ぼくと同じような若者だったのだ。時代の同伴者と言える。
この本では、闘いの意味を、そしてそれを記録した写真の価値を、山本義隆氏が解説している。これも必読である。
なお、この写真集を編集したのは、「札幌宮の森美術館」である。これらの写真の価値を、時代を切り取ったアートとして美術館が認識している証左である。
閉じる
*
-
『開高健は何をどう読み血肉としたか』(菊池治男著/河出書房新社) -
世界をともに旅した編集者が読み解く、作家の原像(鈴木耕)
著者は集英社「月刊PLABOY」誌で、開高健担当の編集者だった。というより、あの有名な写真集『オーパ!』の担当編集者だった、というほうがピンとくる。開高御大の釣り旅行に同伴、写真家・高橋曻とともに世界を旅した歴戦の強者である。
そういうと、ゴッツイ男を想像するかもしれないが、実は繊細な心優しい細身の男だ。しかし外見はそうであっても、中身はやはり、そうとうゴッツイのである。なにしろあの文豪と、ブラジル(アマゾン)、アラスカ、カナダ、コスタリカ、スリランカ、モンゴルと、ほぼ文明から隔絶した地域を、延べ三百数十日、足かけ14年を共に過ごしたのだ、その精神の強靭さは想像できよう。
もっと読む
これまでにも菊池は、文豪・開高に関する本や文章をたくさん書いている。そのどれもが開高さんへの思慕と愛情にあふれているが、本書はその白眉ともいえる。表題にあるように、開高さんの自著、開高さんに関して書かれた本、さらに開高さんが読んでいた本を克明に読み解き、そこから開高健という人間の原像を紡ぎ出しているのだ。開高さんは本を大事にする人ではなかったという。だから彼の蔵書は、やたらとページが折られていたり、書き込みがあったり、さらには大事な部分を切り取ったりしていたらしい。その痕跡から、菊池は開高さんの思考に分け入っていく。そして、開高像へ辿り着く。いやはや、この著者の開高さんへの傾倒はそんじょそこらの編集者には真似のできないものである。
これほどの心情を捧げられれば、いかな文豪とて「ありがとうよ」と頭を下げるしかないだろう。作家と編集者、これほど幸せな組み合わせを、ぼくは見たことがない。
閉じる
*
-
『ぼくは挑戦人』(ちゃんへん.著、木村元彦構成/ホーム社) -
いじめ、単身渡米、ルーツ探しの旅……プロパフォーマーが綴る“波乱万丈”(鈴木耕)
とってもいいよ、この本。
挑戦人という言葉、朝鮮人にひっかけたもの。つまり著者は、在日コリアンである。ちゃんへん.は、京都の在日コリアンが多く住む「ウトロ地区」で生まれた。祖父母ともに朝鮮半島から渡ってきた。そして在日二世の父母。
この家族がなかなか面白い。母はやがてクラブを開きなかなかの成功を収める。したがって経済的には恵まれていたほうだったらしい。欲しいものは何でも買ってもらえた。仕事でかまってやれない母の、せめてもの子どもへの愛情……。
しかし、小学校に入るや、彼は本名の金昌幸(キムチャンヘン)から岡本昌幸(おかもとまさゆき)と名前が変わる。幼い彼には、その理由が分からない。同じ境遇の人たちの間で育った少年が、ある日、まったく違う文化を持った世界へ投げ込まれる。戸惑うのが当たり前だ。ここから彼の“波乱万丈”が始まるのだ。
もっと読む
当然のごとく(これが“当然”なのが絶対におかしいのだが)、ちゃんへん.は壮絶ないじめにあう。なぜ差別されるか分からぬまま、彼は母にも言えず耐えるしかない。しかしそれを知った母のキレっぷりがカッコよすぎる! すぐさま学校へ乗り込んで切る啖呵。緋牡丹お竜の再来か(笑)。彼は独り遊びをおぼえる。まず、ハイパーヨーヨーだ。さらに、ジャグリングの魅力に取りつかれる。そしてなんと、中学生で単身渡米。パフォーマンスの大会に出場してヨーヨーとジャグリングを披露して、見事金メダルに輝くのだ。
そこからの活躍ぶりが凄い。とにかく世界を飛び回る。アメリカはもとより、ヨルダン、ケニア、南アフリカ、ブラジル、ことに貧民窟や暴力の街へ平気で(恐る恐る?)入り込む姿には感心するけれど呆れる。その過程で、思わぬ有名人に出会ったりするエピソードも愉快だ。
そして、自らのルーツを探すべく韓国へ渡る。ついでにロシアの朝鮮族の住む地区を訪ね歩く。その行動力には度肝を抜かれるのだ。
ね、波乱万丈といった意味が分かるでしょ?
こんな面白い「自分語り」に久々に出会えた。どんな逆境に陥っても、あっけらかんと通り抜けてしまう意志力に、ぼくは読んでいて何度も膝を打った。
見事な「挑戦人」である。
閉じる
*
-
『日没』(桐野夏生著/岩波書店) -
あたらないことを願う「予言の書」(鈴木耕)
究極のディストピア小説。というより、とても不快な予言の書、か。
この著者の小説は、どれも一筋縄ではいかない。登場人物が捻じ曲がっているのだ。人間を「いいヤツ」「悪いヤツ」で分類することを拒否するのだ。
〈そんな人間がいるわけないじゃないの。いいヤツがとことん善人で、悪いヤツが底知れぬ悪意を秘めている、なんて考えは浅薄この上ない。そんな小説、読みたくもないし書きたくもない。〉
もっと読む
多分、著者はそう言うに違いない。前の作品『バラカ』(集英社)もそうだった。原発爆発後の汚染世界を舞台にしたこの小説でも、救いの神とも思われた人物の造形が、読む者に深い不快を与える。人間の深奥、突きつめればここに至る……のか。
『日没』もそうだ。すべての物書きの地獄がここにある。この地獄を見ないですむ物書きがいるとしたら、それこそ人間の不快の象徴である。
これは、国家が次第に人間の思考(というより、個人の脳の中身)にまでためらいなく侵入してくる時代の地獄小説なのである。だからこそ、ぼくはこれを「予言の書」と読んだ。予言があたらないことを切に願いながら、これを読み終えた。
閉じる
*
-
『私とあなたのあいだ~いま、この国で生きるということ』(温又柔・木村友祐著/明石書店) -
二人の作家の真摯な往復書簡。この社会とどう向き合うのか?(編集者C)
木村友祐と温又柔……二人の芥川賞【候補】作家が、2019年3月から20年8月まで互いに書簡を送り合った「公開往復書簡」がこの本だ。二人は、09年に、新人作家の登竜門である「すばる文学賞」の受賞者(木村)と佳作受賞者(温)となったことで出合う。その後、交流を深め、励まし合い、意見を交わし、それぞれ創作を続けてきた。そして、二人ともが、芥川賞の候補作品を生み出すまでの作家となった。
しかし、そんなことは、あまり大したことではない。芥川賞は二人とも取れていないし、私からみると、そういった文壇的な評価に対して彼らはあまり重きを置いていないように感じる。ただひたすら、彼らは「まっとうである」ことを目指しているのだ。
もっと読む
標準語と方言、日本語と外国語、日本人と外国ルーツ、男性と女性、持つ者と持たざる者、正規と非正規、人間と動物、中央と地方、差別と被差別、抑圧と抵抗、国家と個人……マジョリティとマイノリティ。日々の暮らし、創作活動の中で、彼らはいろいろなものとぶつかり、考え、疑問を呈する。なぜこんな気持ちになるのか? なぜ怒りや悲しさを感じるのか? どう生きていけば、どう表現していけばいいのか? どうしたらまっとうでいられるのか? それらを問い続ける。作家は作品で表現すればいいとして、直接的な発言を避けるというのが、これまでのお決まりだった。だが現代の情勢は、おそらく「物語」を超えるフィクション性(そんな言い方ってある?)をもって次から次へと「生きづらさ」を生み出し、うそでしょ! と叫びたくなるような事態を迎え、作家にこんな切実すぎる文章を紡ぎ出させた。
息苦しくなるほど真摯な二人の書簡を読み終えて思うのは、自分の「マイノリティ性」に自覚的でいようということ。そうすれば、少しはまっとうな感覚を保てるような気がする。
閉じる
*
-
『白い土地~ルポ 福島「帰還困難区域」とその周辺』(三浦英之著/集英社クリエイティブ) -
震災から10年目。福島はアンダーコントロールなのだろうか?(編集者C)
2020年3月7日、福島に視察に訪れた安倍首相に向かって、「今でもアンダーコントロールだとお考えでしょうか」と想定外の忖度なしの質問を投げかけたのが、この本の著者、三浦英之だ。三浦は、現在は、朝日新聞の福島県南相馬支局勤務の記者だ。これまで、東日本大震災や前任地のアフリカでの取材から、数冊のすぐれたノンフィクション作品を執筆し、世に送りだしてきたことでも知られる。
「白地」(しろじ)と呼ばれる、(福島第一原発の事故により)「放射線量が極めて高く立ち入りが制限されている帰宅困難区域のなかでも、将来的に居住の見通しが立たない地域」とその周辺に住む人々の暮らしを鮮やかに切り取った前半部は、涙がホロリと出てしまう。浪江町の闘う町長・馬場が話す3.11とその後の苦悩は、震災から10年が経とうとする今、必読と言えるだろう(これが馬場の遺言ともなった)。後半は、文頭に書いたように地方の支局担当記者としての奮闘ぶりが描かれていて、まだまだ新聞記者も捨てたもんじゃない! と思わせる。
もっと読む
私のお気に入りは、第4章「鈴木新聞舗の冬」だ。三浦は、2017年福島総局赴任から半年間、担当の原発被災地の実態を見たいと、浪江町の鈴木新聞舗の配達を手伝う。極寒のなか、住人が極端に少なくなった担当区域で巨大イノシシに出くわしたりしながら、新聞(それも朝日新聞ではない)を配り続ける。三浦の手伝いを受け入れてくれた鈴木店長は、日本新聞協会の地域貢献賞を受け、東京のプレスセンターで表彰される。表彰式の帰り、東京のまばゆい灯りを車窓に見ながら、真っ暗な浪江に戻っていく鈴木と三浦。印象的な場面だ。「復興五輪」という言葉はいつまにか消え失せ、東京だけが明るく輝く。「福島はきっと東京のようには前に進めない」と三浦は書く。廃炉作業の進まぬ原発、汚染された土地、人々の心の痛み……誰が「コントロールされている」と言えるのか?
閉じる
*
-
『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(熊代亨著/イースト・プレス) -
「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある」社会が取りこぼしてきたもの(西村リユ)
読みながら、自分の子どものころの記憶が、ふと頭をよぎった。昭和の終わり近くだったけれど、近所の家の壁にボールをぶつけて遊んだり、家の前の道(私道ではない)に落書きしたり、木の柵で囲われた空き地に勝手に入り込んで鬼ごっこに興じたり、今では考えられないことばっかりやっていた気がする。
あるいは、休みの日に親に連れられて行った大きな公園。当時は入場も無料だったそこには、いつも昼間っからベンチにおじさんたちがたむろしていて、将棋を指したり、昼寝したりしていた。その公園は、今では小綺麗な親子連れが遊びに来るのにふさわしく、ピカピカと美しく清潔に整備された(そして、有料のレジャー施設が並ぶ)場所になっている。
もっと読む
そんなふうに、私たちの社会は確実に、一昔前よりも「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある」ものへと変貌してきている。それはもちろん、悪いことであるはずがない。けれど一方でそれは、その「秩序」に反する存在にひどく厳しい視線を向けることにもつながっているのではないか。そしてそのことが、誰かの不安や恐怖、生きづらさを生み出しているのではないか──。これが、精神科医でもある著者の問いかけである。美しくて清潔な街並み、時刻表どおりに運行される列車、秩序に従い、行儀良く振る舞う人たち。幼い子どもたちさえも、一昔前よりもはるかに行儀良く、秩序だって行動している。健康への意識は高まり、平均寿命は男女とも80歳を超えた。サービス業のクオリティは他国と比較しても際だって高く、若い世代のコミュニケーション能力の高さには驚かされることもしばしば。私たちは、そんな社会を生み出してきた。
繰り返しになるけれど、その一つひとつが「悪い」わけではもちろんない。けれど、それが一歩進んで、美しくて清潔で「なければならない」、行儀良く「いなければならない」、コミュニケーション能力が高く「なくてはならない」としたら。自分が何かの拍子に、そこからはみ出てしまったとしたら。それはあまりに、苦しいことではないだろうか。
読み進めるうち、ここ数年ずっともやもやと抱えていた違和感や居心地の悪さを、的確に言語化してもらったような気がした。同じような違和感をもつ人は、この社会にも決して少なくはないのではないかという気がする。
ではどうすればいいのか、の「処方箋」は本書にも明確に示されてはいない。けれど「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある」社会が取りこぼしてきたものに目を向けることは、多分とても重要だ。まずは自分が社会に抱く違和感を「なかったこと」にはしないところから始めたいと思う。
閉じる
*
-
映画『だってしょうがないじゃない』(坪田義史企画・監督/2019年) -
「しょうがない」のは、しょうがないのか(中村)
40歳を過ぎて初めて発達障害(ADHD)の診断を受けた坪田監督は、あるとき親戚に広汎性発達障害のおじさんがいることを知る。その「まことさん」のもとに通いながら交流を深めていく3年間のドキュメンタリーだ。残念ながらDVDになっておらず、いまは各地での自主上映会が続いている(あっ、それじゃ年末年始に見られないのか……)。
母子家庭で育ったまことさんは、母親が亡くなったあとも、借家でのひとり暮らしを続けている。監督とまことさん――ちょっとマイペースな2人が、お祭りに行ったり、散歩をしたり、家で一緒に飲んだり、そんな日常がゆっくりと流れていく。映画を観ているうちに、まことさんのこだわりや生活のリズム、好きなものなどがわかってきて、監督と同じように、まことさんとの距離が近づいていくような気持ちになる。これがまた、なんだか憎めない感じの人なのだ。
もっと読む
まことさんは、ビニル袋が風に舞う様子が見たくて夜中に飛ばしてみたり、マッチを何本も擦って火がつくのを眺めたりする。その場面をみて、「ああ、私も昔、そういうのが好きだったなあ」と思い出した。でもやらないだろう。なぜなら、まことさんのように近所から苦情がきてしまうからだ。でも、ビニル袋が風に舞う様子を見ていたい気持ちはとってもわかる。思い出の詰まった庭木が「手入れが大変だから」という理由で切り倒されたとき、住み慣れた借家を出てグループホームに入ってはどうかという話が出たとき、まことさんが不本意だと思っているのは明らかなのだけど、「しょうがない」と諦める。
何かのインタビューで監督は、タイトルの「だってしょうがないじゃない」という言葉を、「できないものはしょうがない」と障害を受容していく意味でもとらえていると話していたけれど、映画を見ながら、「私たちがついつい使う『しょうがない』って本当に『しょうがない』のかな」と問われているような気持ちになった。「障害者の自立生活」や「意思決定の尊重」という言葉でこの映画を紹介もできるのだろうけれど、映画を観終わってとにかく気になったのは、まことさんがこの先、どこで、どう暮らしていくのかだった。あの笑顔を失うことなく暮らしていけるのだろうか。多くの観客がそう思ったのではないか。
夜中にビニル袋を空に飛ばしてじっと眺めている人が近所にいたら、きっと緊張してしまうだろうけど、それが「まことさん」だったらどうだろうか。画面越しではあるけれど、まことさんという人のことを知っていくことで、受け取り方が変わってくる。そして、それが大事なことなのだろうと思う。
閉じる
*