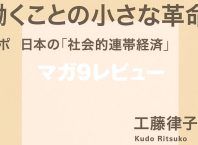2022年の第19回本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬著/早川書房)を読んだ時の驚きはいまも覚えている。30代の日本人作家が若いロシア人女性の狙撃手の行動と内面、そしてその背景にある戦争やソ連社会まで描く筆致に舌を巻いた。著者の2作目となる『歌われなかった海賊へ』(早川書房)は、ナチスがユダヤ人を強制収容所に移送して何をしているのかを知った若いドイツ人の男女が、アウシュヴィッツへつながる線路を爆破し、政権を転覆させようとする物語である。いずれも人間の想像力はかくも自由に時空や場所を超えることができると思わせる、文学の可能性が伝わる作品だった。
『同志少女よ、敵を撃て』の舞台は独ソ戦である。本コラムでも紹介した『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』(大木毅著/岩波新書)によれば、両国の世界観が真っ向からぶつかる戦争であった。ヒトラーはソ連の「ユダヤ的ボリシェヴィズム」をこの世から抹消することを目的とし、スターリンはファシストからロシアを守る大祖国戦争と位置づけ、敵を一人残らず殺せと命じた。そして戦場は戦時法の通用しない酸鼻極まるものとなった。
映画『ロシアン・スナイパー』は1957年、故フランクリン・ルーズヴェルト元大統領夫人が、当時のソ連共産党書記長のニキータ・フルシチョフに招待されて、モスクワ・ヴヌコヴォ空港に降り立つシーンから始まる。スターリンの死後、米ソの雪解けの時代だ。ソ連政府のお付きの者が早速、書記長のところへ案内しようとすると、夫人はその前に「ある人の元へ連れていってくれ」という。ある人とはリュドミラ・パヴリチェンコ。独ソ戦において309人のドイツ兵を倒した女性の狙撃兵と再会するためである。
最初の出会いは1942年、米国の首都ワシントンだった。ホワイトハウスでルーズヴェルト夫人主催による連合国軍の学生たちが集う場にリュドミラがいたのである。ルーズヴェルト夫人は女性狙撃手の存在に驚かされ、「あなたは敵を何人殺したの」という問いに対して、表情を変えず「309人です。人間ではなく、ファシストを殺しました」と答えるリュドミラをまじまじと見つめるしかなかった。
いったい彼女は何者なのか。ルーズヴェルト夫人が回想する形で、舞台は独ソの戦場と米国と都市との間を行き来する。
1937年、ウクライナの首都にあるキエフ(現キーウ)国立大学史学科に首席で合格したリュドミラは、たまたま通りかかった大学内の射撃場で男子顔負けの腕を見せたことで、ソ連軍に女性兵士として招集される。訓練に男女の別はない。女性兵士たちが持参した女性ものの服や靴、ぬいぐるみなどはすべて焼却することを命じられ、リュドミラらは黙々と訓練をこなしていく。そして1941年6月、ドイツ軍がソ連に侵攻したという報を受けて前線に派遣される。
黒海沿岸の都市、オデッサ(現オデーサ)に配属されたリュドミラの任務は、敵の将軍を一撃で仕留めて部隊の士気をくじき、戦車のわずかな覗き窓に照準を合わせて操縦者を撃つことだった。弾を弾倉に入れる、照門を真っすぐ、照星と的をそろえる、深呼吸をして、息を止め、優しく引き鉄を引く――その正確無比の射撃からリュドミラは男性兵士から「死の女」と呼ばれた。
狙撃兵は常に部隊とともに移動するわけではない。上官と2人で敵の後方に回ることもある。リュドミラはときにあえて急所を外し、敵を苦しませるようなことをして上官に叱責される。戦況は厳しい。ナチスドイツの戦車部隊による砲撃、そして空軍による爆撃。味方兵士の阿鼻叫喚のなか塹壕を這いずり回るシーンはモノトーンがベースになり、冒頭で映される夏の黒海の眩しい色彩とは対照的に、死んだ兵士たちの血の赤が鈍く光る。
オデッサはナチスドイツの手に落ちた。リュドミラはクリミア半島の南西部に位置する黒海に面した港湾都市、セヴァストポリへと転戦を強いられる。そこもまた激戦地となり、重傷を負って戦える身体ではないにもかかわらず、戦場へ志願するのは、愛した上官を次々と失い、生きる目的を戦場にしか見いだせなくなったからだ。しかし、戦争前からリュドミラに思いを寄せ続けた医者のボリスの計らいで、ナチスドイツの攻撃が激しさを増すなか、リュドミラは潜水艦に乗ってセヴァストポリを脱出する。その後、リュドミラは国際学生会議に招待され、ルーズヴェルト夫人と会うのである。
映画の原題は『セヴァストポリの戦い』。セヴァストポリの町は、1941年から1942年にかけてドイツ軍に包囲されたもののソ連軍の反撃で奪回された。スターリングラードでの攻防に匹敵する戦いとして記憶される地である。とはいえ、本作品はソ連の兵士たちを英雄視はしない。いたいけな少女がリュドミラたちの集まったパーティの場で、「ファシストを殺してしまえ」と憎々し気に語るシーンには背筋が寒くなる。
いまのロシアが同じ題材でこの物語を撮ったら、ソ連・ロシアがウクライナを防衛したセヴァストポリの兵士を称える戦意高揚的な作品になっていただろうと想像する。本作品がロシア・ウクライナ合作によって完成したのは2015年。ロシアがクリミア半島を同国に編入したと宣言したのは前年3月であるから、両国のスタッフが協力して制作することができたギリギリのタイミングだったのかもしれない。それによって、戦争という極限の状況によってソ連・ロシアという国家とジェンダーの問題をあぶりだす作品が生まれた。『同志少女よ、敵を撃て』に話を戻せば、女性の狙撃手がロシア、ウクライナと日本で同じ時代に物語の主人公として取り上げられたのは、決して偶然ではない気がするのである。
(芳地隆之)
*
『ロシアン・スナイパー』
(2015年ロシア・ウクライナ/セルゲイ・モクリツキー監督)
※アマゾンにリンクしています