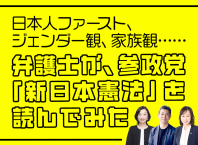1980年代から原発建設計画が持ち上がり、多くの住民が反対の声を上げ続けてきた山口県・上関町。昨年夏、その上関町で新たに、使用済み核燃料の中間貯蔵施設計画が浮上、町長がその受け入れを表明しました。「核」に翻弄されてきた町で、何が起こっているのか。長年取材を続けるライターの山秋真さんが、現地のリアルな「今」を伝えてくれました。
2024年4月23日、山口県の上関(かみのせき)町で中国電力(中電)が、ボーリング(掘削)作業に着手したと報じられた。原発から出る使用済み核燃料を一時的に貯蔵するとされる施設(以下、中間貯蔵施設)の建設へむけた、立地可能性調査の本格化である。
ユーラシア大陸の東岸ぞいに弓なりにつらなる日本列島の、最大の島・本州。その西端を占める山口県の、南東部に位置するのが上関町だ。瀬戸内海とよばれる内海の多島海域で、ふたつの海流がであう潮目にうかぶ島々と半島から成る。
町内で、太平洋からの海流と最初に出会うのは祝島(いわいしま)だ。周囲12キロメートルほどのハート形の陸に森がひろがり、海にも森のごとく海藻がたゆたう。鳥や魚や貝にクジラの仲間も子育てする環境と聞く。
祝島では立春ころの大潮(おおしお)の日にヒジキ漁が解禁となる。午前0時に日付がかわるとベテラン漁師の竹林民子さんもいそいそ磯へゆく。
そのとき宇宙では、太陽と地球と月が直線上にならんでいるらしい。海は、水面がゆっくり高くなってまた低くなることを、ほぼ日に2回くりかえす。海面がもっとも高い満潮(まんちょう)と、もっとも低い干潮(かんちょう)の差異は、満月と新月すなわち大潮のころに際立つ。おもに太陽と月の引力そして地球の自転によるという。
つまり地球では、干潮の時間帯に海から露わになる海底の面積が、大潮の数日間に最大となる。その宇宙の法則にのっとって祝島の漁師は働く。
ヒジキ漁は解禁から2ヶ月ほど。海の森なしに生命を育むことは難しいから、生きものが困らないよう、絶やさないための工夫だ。人も生きものなので、我がため未来の人のためでもある。
磯につくと民子さんはヘッドライトを頼りに鎌を動かしはじめる。「よいしょーよいしょー」、リズムをとって精をだす。2時間ほどで海にもどる束の間の陸地なのだ。
重労働だが機嫌よい。汗をかきかき吸う空気はこよなく心地よい。見習いをさせてもらった数年前に私も体感した。海中からあらわれた「森」が極上の酸素をもたらすのか。80歳を超えてなお胆力を保つ彼女の秘訣かもしれない。
大潮の引潮どきの祝島のひじきの森
常軌を逸した性急な展開
だが2023年夏の民子さんは漁をたびたび休む羽目になった。8月1日に突如、上関町に中間貯蔵施設をつくる計画が報じられたから。
翌2日朝、上関町役場へ中電の幹部3人が現れた。少なくない住民が駆けつけて「帰ってください」と訴えるのを振りきり、奥の入口から庁舎の中へ消えた。中電が午後に開いた記者会見によれば、関西電力(関電)と共同で中間貯蔵施設をつくる計画を西哲夫町長に申し入れたという。
この件について町長から町議会議員へ説明すべく、上関町議会の全員協議会が8日に開かれることになった。もともと上関原発の計画に反対する立場の、秋山鈴明(すずか)・清水康博・山戸孝の3議員と町議経験者3人が公開での開催を要望したが、非公開とされた。それでも8日当日、「町民は経緯について町長の口から聞きたい」と説明を求める人びとの姿が庁舎前にあった。
14日には全10人の町議が、中電から説明をうける予定となった。ただし8日の件で要望書をだした町議3人は、あらかじめ欠席の意向を伝えて登庁を控えている。議会に対して「説明した」という既成事実化に利用されかねない懸念からだ。
14日当日の庁舎前は町内外から駆けつけた人が溢れた。姿をみせた中電に「順番が違う」「町民に説明しましたか?」「(国の)核燃料サイクルは破綻しとる」と訴えかける。
「今日は盆ぞ!」と憤る民子さんの声も聞こえた。しかも新型コロナ感染症が蔓延してから会えずにいた家族と、やっと再会する盆だ。
「この盆に、なぜ、こがいなことを?」
怒りの火に油を注がれ、あちこちから声が飛ぶ。
「どうして福井県が断ったものを、山口県が受けいれなきゃいけないんですか」
「町議への説明は要りません、帰ってください」
「山口県民全体に説明してください」
庁舎前が混乱する事態となり、説明会の予定は中止された。
それでもその午後、この件について臨時町議会を18日に開くことを、議会運営委員会が粛々と決める。しかも、西町長は中電の申し入れを18日中にも受け入れる意向と報じられた。
民は蚊帳の外に甘んじず
18日は早朝から上関町役場へ人がぞくぞくと集まった。臨時町議会を傍聴したいと並んだ人だけでも100人ほど、取材者も含めれば150人もいたか。上関原発の計画をずっと押しとどめる祝島はもちろん、町内の他地区や周辺自治体、さらに県内の遠方からも。老若男女の多彩な顔ぶれは、思いを手書きした布やダンボールを掲げる人はいても、団体や政党の旗などはない。
8時30分ころ町長の車が現れた。人びとは駆けよって「説明して」と嘆願する。だが車は窓も開かれない。それでもあちこちから声が湧いた。
「窓をあけて町民の声を聞いてください」
「町長も町議も中間貯蔵施設の話を選挙で言わなかったでしょう」
「核のゴミは要りません」「独裁はいけません」
役場の職員はうろたえつつ「車から離れて」と言う。
「離れられん!」と即座に声が起こった。
「警察にお願いすることになる」。役場の職員はのたまった。
「未来に対する犯罪ですよ」。女性が返す。
「マスコミも危ないから、脚立の上とかで撮影は遠慮して、さがって」と職員。
マスコミは一斉に後方へさがった。
「核のゴミは危なくないんですか?」。祝島の中堅世代の女性が問う。
「町長ひとりより、町民を守って」と職員に懇願する声もあった。
暴力に頼むカモフラージュ?
男性の一群が現れた。シャツとズボンの私服姿だが「警察」の腕章も見える。最前列のまんなかで拡声器を握るひとりが、車のドアを開ける、「部隊」を突入する、ケガをする恐れがあるから離れてと告げると、8時42分、42分、43分と立てつづけに3回「警告」をした。それが済むやいなや、背後に控えた男性群が丸腰の人びとへ突入していく。
「皆さんは庁舎の敷地に入って不法に通路を塞いでいる」と拡声器ごしに威嚇する男性に、「なにが“不法”か!」と応じる女性がいた。民子さんの声に似た響きだ。宇宙の法則にのっとる人の瞳に、人のつくった法規はどう映るだろう。
部隊は力ずくで人びとを押していた。立っていようが倒れようが腕や脚をつかんで引っぱる。あちらこちらで悲鳴がした。高齢者もいるのに民は無事かと気にかかる。取材をつづける私も押された。圧迫されるだけで痛みが走る。部隊員の身体は、強靭な肉体というより硬質の物体であるかのようだ。握力にも悪意を感じた。ただし表情は穏やかで、口調も「危ないですよ」と丁寧かつ猫なで声という具合だから遠巻きには分かりにくい暴力だ。
騒然とするなか次々に人がどかされていく。まもなく部隊はスクラムを組みはじめた。運転席のドアの前に誰もいない空間をつくり、おもむろにドアを開く。
西町長が車から姿をみせ、その空間に降りたった。
「町長ー!」
叫ぶような声が沸々と起きる。それを一顧だにせず町長は、スクラムごと庁舎へむかい、逃げるように中へと消えた。
警察がスクラムを組むなか車を降りる西町長
8月18日9時すぎ、臨時町議会がはじまった。町長は、原発を新設するために中電が町内に取得済みの用地で、中間貯蔵施設の建設にむけた立地可能性調査を、地域振興策として進めたいという申し入れが中電からあったと報告。自分は容認する考えだが、議員の意見をきいて判断したいとした。そして議員10人が意見を順に述べると、町長は調査の容認を表明して、2時間と経たぬ間に閉会した。
質疑も討論も採決もない。わずか16日間で核施設の計画を受け入れる町長の独断専行を、住民は蚊帳の外でも議会が関与したと見せかけてカモフラージュするだけの場なのか。
怒りの傍聴、後退する公開
とうぜんながら町議会の9月定例会の一般質問にも人が詰めかけることとなった。そこで必ず町長は議員の質問をうけて答弁するからだ。
だが、質問に答えない、もしくは実質的に答えない答弁が多かった。ためしに数えると答えないケースは4回、質問とズレたケースは5回。
ことの経緯から傍聴席はそもそも怒りに満ちていた。山戸議員が質問の冒頭、「判断してから(町民に)説明して理解をしてもらう、ではなく、説明して理解をしてもらってから判断すべきだ、と私は臨時議会で述べた」と言うと、「そういうこと」と傍聴席から呟きが聞こえる。「町が主体となって町民に十分な情報や議論する場・時間を提供することは考えていないか」と問われた町長が「(町民は)中間貯蔵施設について勉強して、場合によっては視察もして…」と応じれば、吐息まじりに「接待、接待」と声がする。さらに町長が「 “核のゴミ”と(議員は)呼ぶが、(使用済み)核燃料はリサイクルできる資源…」といい募ると、「ゴミ以外の何か?」「リサイクルできる?」と、どよめきまで起きている。
殊更ざわめいたのは、「反対する人の意見に耳を傾けないということではない」として町長が「確かに説明不足は否めなかった」と認めながらも、「8月中旬以降は(中電が町内へ)説明に伺った」から「立場は違えど冷静に(中略)町の将来を町民で考えて」と述べたときだ。「考えとる!」「町民だけの問題ではない」と声が噴出。それをみた町長は「もう答弁できない」と座ってしまったため、「それくらいのことで?」「小さい人間じゃのぅ」と、ささやきが波紋のように広がった。
すると町長は議長を振りかえり、議長が「退場を命じます」と告げた。傍聴席の町民の存在感も持ち味だった上関町議会で、異例の対応ではないか。女性の町民がひとり退席することになった。
答弁なし・ズレ・拒否、そして…
そこから議会は穏当に流れるかに見えた。だが秋山議員の質問で空気がまた変わる。
「住民が自分の町に意見を言うことを諦めなければならなくなっている状態を、どう考えるか」と問われた町長は、噛みあわない答弁を重ねた。しかも、「回答いただけてない」と粘る議員の発言を、「終わります」と議長が遮る。「答えてないよ?」「質問に答えないのは問題だ」と傍聴席に戸惑いが漂った。
清水議員の質問への答弁もズレを否めない。それでも議員は、「原発の問題で41年間これだけ町が苦労してきた中で、さらに原子力施設という茨の道を選択したことに、他の選択肢がなかったのかと感じる」と応じ、更に問うた。「町長自身は2022年10月の就任以降、行政として他の地域振興策を検討したか。それでも、中間貯蔵施設という判断なのか」と。
その答弁で町長は、2011年に前町長が立ちあげて2年つづいたという「地域ビジョン検討会」について話しだした。時期や立場など質問から外れる内容と思われたが、つづけて橋本政和副町長もその説明を重ね、こう結んだ。
「過去も理解した上で考え方を発信すべき。でないと先輩議員や町の執行部に失礼な話だ」
噛みあわない答弁をしつつ、新人議員にマウントをとるかと見まごう態度で行政が臨む議会で、十全な議論は成立するのかと危惧される。清水議員をふくむ前述の3議員は、おもに祝島を拠点に活動する30〜40歳代。いわば町の将来の担い手だが、育てようという気配の乏しさも気になった。
23年9月以降3回の定例会での答弁を振りかえると、質問に答えないケースは9回、質問とズレるケースは14回、拒否は8回ほどか。マウンティングの懸念がある内容も、23年12月は山戸議員に、24年3月は秋山議員と山戸議員に対して見受けられた。たとえば3月議会の様子を撮影した動画を、この原稿の最後に載せておくので見てほしい。
これでは議会が機能しないまま、「住民の議論」や「地元の理解」の外形のみ整えて、中間貯蔵施設の計画が進みかねない。民意は置き去りとなることが危ぶまれる。
民意と奮起
だが逆に奮起した若手もいるようだ。答弁を避けられても議員は工夫を積み重ねる。いつしか傍聴席には、見守るような空気が漂いはじめた。3月の定例会では「次の議会で頑張れ」という声まで聞こえている。
定例会の翌日、民子さんは釜場にいた。数日前までの大潮のあいだに刈りとったヒジキを、鉄の大鍋に投入している。漁の解禁からしばらく短かったが、今になって伸びたそうで、「今年のヒジキは良い」らしい。
長島の山々と対岸の祝島
満ち干(ひ)の周期を重ねつつ流れつづける潮(しお)は、日ごとに違うと祝島漁師は話す。恵みをもたらす大いなる自然は同時に、古来その圧倒的な力で人びとに畏怖の念をいだかせてきた。24年の元日におきた能登半島地震で海底が大きく隆起したことも記憶に新しい。
その震源だった石川県珠洲(すず)市内の2地点で、かつて関電と中部電力と北陸電力は原発をつくる計画だった。今回の震央は2つの候補地のまさに直近にあたる。03年に計画が凍結されたこの珠洲原発が、もしも国策どおり計画どおりつくられていたら?
今ごろ私たちは、自然災害に原子力災害が加わった深刻な事態に直面していたかもしれない。13年前の東日本大震災によって福島県でおきた東京電力の原発事故による、甚大かつ広範な被害の再来も、否もっと過酷な被害も、ありえただろう。
そう想像した人は少なくなかった。元日の地震のあと、珠洲の原発反対運動を担った人びとのもとへ「原発を止めてくれてありがとう」という声が各地からたくさん届いていると聞く。
裏返しの事実として浮かびあがるのは、無毒化できない毒性が時空を超えて影響を及ぼす原子力の問題に関する大事なことを、ごく限られた時代と地域の人が決めてきた過去である。
それへの不満は、いまや透けてみえるようだ。この中間貯蔵施設をめぐっても、周辺の柳井・周防大島・田布施・平生(ひらお)という4市町の首長が中電と国による説明会を求めていくことを、5月8日に確認したと報じられた。
中間貯蔵施設の行方は、各地の原発の再稼働ひいては岸田政権が打ちだす原発回帰の政策をも左右する。それはまだ予断を許さない。いま上関町議会には、見るべきものがある。
*
上関町/祝島についての山秋さんの著書(2012年出版)『原発をつくらせない人びと――祝島から未来へ (岩波新書)』
*
▼動画1:上関町議会3月定例会での秋山議員の一般質問
▼動画2:上関町議会3月定例会での秋山議員の一般質問への西町長の答弁
▼動画3:上関町議会3月定例会での秋山議員の再質問、西町長らの再答弁、秋山議員の再々質問
▼動画4:上関町議会3月定例会での秋山議員の再々質問の続きと西町長の再々答弁
*本稿は一般財団法人上野千鶴子基金の助成を受けた取材活動を土台に執筆しています。
*