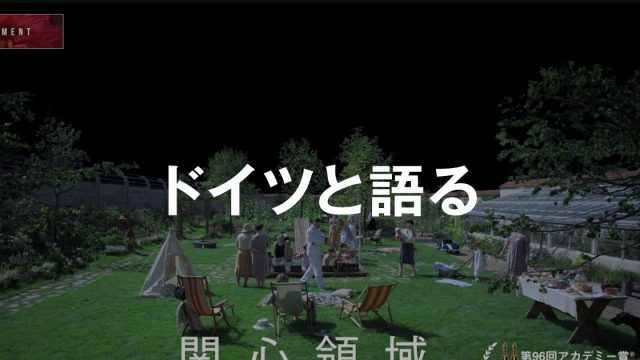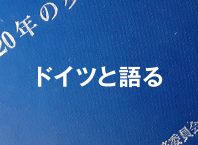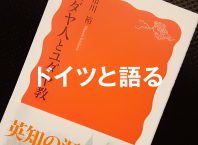映画『関心領域』(2023年米国・英国・ポーランド/ジョナサン・グレイザー監督)は黒く塗りつぶされたような画面と不協和音のような音楽とともに始まる。時代は1942年。場所はアウシュヴィッツ。舞台は強制収容所に隣接する屋敷。そこには収容所所長であるナチスの親衛隊幹部、ルドルフ・ヘス一家が暮らしている。
不穏な始まりから一転、スクリーンは緑豊かな川沿いで家族がピクニックを楽しむ様子を映し出す。屋敷では妻のヘートヴィヒが庭の花の成長具合をみたり、子どもたちがプールで遊んだり。しかし、こちらはどうにも居心地が悪い。物語の背景を知っているから、だけではなさそうだ。
スクリーンを追っていて気づいた。カメラが俳優たちにあまり近づかないのである。
俳優のクローズアップはない。カメラは屋敷のいろいろな場所に固定され、様々な角度から一家を撮ったのだという。私たちはやや遠巻きに眺めながら、ヘートヴィヒが他のドイツ人女性との会話の中で語る「歯磨き粉のなかに宝石が隠されていた」というエピソードを耳にし、あるいはヘートヴィヒが鏡の前で試着する毛皮のコートを目にして、この持ち主は誰なのだろうと考え、息子が枕もとに並べるの金歯のコレクションに心がざわつく。
ときどき銃声や悲鳴が響き、煙が立ち上る。それ以上の情報はないが、ヘートヴィヒを訪ねた母は、しばらくすると娘に黙って立ち去った。母はその場が醸しだす空気に耐えられなかったのだろう。母の置き手紙を一瞥したへートヴィヒはそれをストーブにくべる。自分(母)だって自宅の隣人が追いだされた後、その家のカーテンを手に入れ損ねたと嘆いていたじゃない、とでも言いいたそうに。
この映画のタイトルが示唆するように、アウシュヴィッツ強制収容所の内部で行われていることは、ヘス一家の関心外だったのだろうか。いや、違う。ヘスがカヌーに子どもを乗せて川遊びをするシーンがある。そのとき上流から何かが流れてきて、ヘスの下半身に当たる。ヘスが手にしたそれは、カメラは離れているので、「硬くて白いもの」としか認識できないのだが、ヘスは狼狽え、子どもたちを川から連れ出す。そして屋敷に戻ると、バスタブで子どもたちの身体をごしごし洗う。バスタブには灰色の小さな砂利のようなものが落ちてくる。
ヘスは強制収容所で行われている行為がおぞましいことであると考えていたのか、それとも流れてきたものをおぞましいと感じていたのか。オラニエンブルクへの異動を命じられたヘスは、それがエリートとしての出世コースであること、そしてアウシュヴィッツを離れることに安堵しているようだった。ところがヘートヴィヒは、自然に囲まれた子育てにも最適な、長年の夢だったこの暮らしを手放したくないと、ヘスに単身赴任を求めるのだった。
ヘスが親衛隊本部で「アイヒマンに指示を受けるように」と命じられるシーンがある。アドルフ・アイヒマンはヘスの上司であり、ユダヤ人の強制連行を指揮することで、自らのポストを上げていった人物だ。ヘスもアイヒマンの出世コースを辿っていく。
別の映画の話になるが、『ハンナ・アーレント』(2012年ドイツ・ルクセンブルク・フランス/マルガレーテ・フォン・トロッタ監督)には、哲学者のハンナ・アーレントが、戦後、アルゼンチンに逃れたアドルフ・アイヒマンがイスラエルの諜報機関モサドに捕えられ、エルサレムで裁判にかけられる姿を険しい表情で見つめるシーンがある。「自分は命令に従っただけ」とユダヤ人虐殺の罪から逃れようとする主張するアイヒマンが臆病な小役人に見えたからだ。普段は心優しい家庭人であっても、命令とあれば大量殺人を平気で実行するアイヒマンをアーレントは「凡庸な悪」と評した。
裁判の傍聴の記録である『エルサレムのアイヒマン』を書き上げたアーレントは、イスラエル国内、そして彼女が暮らす米国のユダヤ人から大きな反感を買った。未曽有の大虐殺が、そんな小者によって実行されたということに人々は耐えられなかったのである。イスラエルにとって、アイヒマンは極悪非道のモンスターでなければならなかった。
ここには二つの微妙な嘘がある。ひとつはアイヒマンが何も知らずに命令に従っただけではないということだ。出世のために大量殺人を進んで行ったアイヒマンは、罪を免れるために、あえて凡庸さを装ったきらいがある(『関心領域』のヘスと重ねてみればわかる)。アーレントの「凡庸な悪」はその卑怯さまでを射程に入れた表現だったのではないか。そしてもうひとつは、イスラエルがアイヒマンの裁判を使って、「ホロコーストがあったからイスラエルが必要だ」という論理を強化しようとしたことだ。
イスラエル建国の指導者たちの多くはロシア東欧出身である。イスラエルの建国を目指すシオニズムに傾倒した彼らは、第二次世界大戦の終結前にパレスチナへ移住し、統治国である英国に対して軍事闘争を展開してきた。したがって彼らはホロコーストのサバイバーではない。サバイバーに対しては「シオニズム運動に参加しなかったから、そんな目に遭ったんだ」と冷ややかにみていた。シオニストに「あなた方がホロコーストで受けたようなことを、どうしてパレスチナ人に対して行うのか」という批判は届かないのである。
欧米諸国の多くは、現在のイスラエルによるガザに対する容赦のない攻撃に、眉を顰めこそすれ、イスラエルを公式の場で非難することはしない。とりわけドイツは、イスラエル政府への批判が反ユダヤ主義と結びつけられることから極めて慎重だ。と同時にイスラエルを西欧的価値を共有する国とみなす一方、イスラム世界とは価値観が相いれないという姿勢も――良心的だと思われる知識人のなかにさえ――見える。シオニズムは19世紀に、フランスに根強く残る反ユダヤ主義を憂慮したテオドール・ヘルツルがユダヤ人の国をパレスチナの地につくるという思いに端を発している。イスラエルはヨーロッパが生んだ国といえる。
われわれの視点からみるとどうか。2023年11月5日、イスラエルのネタニヤフ内閣のエルサレム問題・遺産相であるアミハイ・エリヤフは、ガザに原爆を使用することも「ひとつの選択肢だ」と述べた。2024年3月25日には米下院の共和党のティム・ウォルバーグ議員が、ガザに対して「長崎や広島のようであるべきだ。早く終わらせられる」と発言している。この言葉からパレスチナ人だけでなく、日本人も蔑まれていることが伝わってこないだろうか。
それらの発言の裏には、日本を焼け跡にしたことで、戦後は反米から親米になったように、ガザも灰にしてしまえば、反イスラエルから親イスラエルに転じるだろうという考えが隠されているように思われる。そうであれば、パレスチナ人という特定の民族を抹殺することを躊躇しないという点で、『関心領域』におけるナチスとどれほどの違いがあるというのだろうか。
この映画をそこまでレンジを広げて見ざるをえなかったのは、こちらの内面をかなり揺さぶられたからかもしれない。
(芳地隆之)
*
『関心領域』
(2023年米国・英国・ポーランド/ジョナサン・グレイザー監督)
*
『ハンナ・アーレント』
(2012年ドイツ・ルクセンブルク・フランス/マルガレーテ・フォン・トロッタ監督)