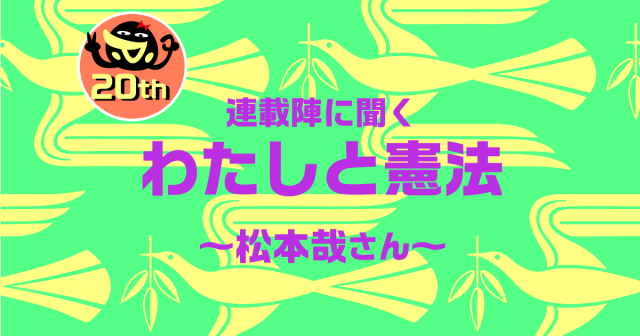マガジン9創刊20周年を機に、あらためて「憲法」のことを一緒に考えたいと、マガジン9で連載中の執筆陣の皆さまに「わたしと憲法」のテーマでご寄稿いただきました。
世界の大バカたちのマヌケ革命と日本国憲法(松本哉)
いや〜、日本国憲法、前文からいきなり絶好調に飛ばしまくってますね〜。自分はまさかの法学部出身なのでかつては憲法は何度も読んでたはずなんだけど、改めて見てみると相変わらず絶好調のテンションでいい。
ただ自分的には、ここ最近は法も国も全部無視しつつ「世界マヌケ革命」を掲げて世界各国のふざけ切った大バカたちとの交流を通して、世にはびこるギスギスしたしょうもない社会に対してダメージを与え続けることに勤しんでいる。では、その立場から日本国憲法を読むとどうなるのか!? さあ、この無謀な企画、やってみましょう〜。
マヌケとは何か
さて、本題に入る前に、そのマヌケな反乱について。まず、世界のやつらが楽しく遊べない諸悪の根源はやはり国境じゃないかっていうことで、それを混乱させるためにひたすら行ったり来たりして謎のアンダーグラウンドなやつらを混ぜまくっている。そんな時に大事にしているのが、予想外に登場する大バカなやつらへの信頼。
そもそも人間って本当にいろんなやつがいるので、ひたすら交流を広げていけばいくほど、次から次へと予測不能の「なんなんだコイツは〜!」という自分の想定を超える謎の人物が登場しまくる。善なのか悪なのか? 利口なのかバカなのか? いいやつなのか嫌なやつなのか? 全く不明な感じ。ただ唯一、DIYの地下文化圏で出会うやつらは、金もうけ目的や主流のカルチャーではない謎の“自分らで勝手に面白い世界を作ってやる”って価値観で生きてるっていう共通点がある。これがめちゃくちゃ面白い。もうそれが国を跨ぎまくってるもんだから、誰がナニ人かなんてどうでもよくなる感覚。で、そんなまぐれで遭遇しまくった謎のやつらが結託して、このくだらない世の中に巻き込まれることをうまいこと回避して、どんな面白いことができるのか、何ができるのか? そんな感じがマヌケな反乱だ。
それも、「正しい賢者が愚人を啓蒙・教育して、みんなが完璧な人間になって素晴らしい世の中がやってくる」なんてのはハナっから信用してない(そもそもそんな世の中に住みたくない)。やはりここは、次々と登場する意味不明のロクでなしや出来そこないたちが集まって、三人寄れば文殊の知恵の作戦で、大バカなみんなでああだこうだと騒いだり揉めたりしながら失敗したりまぐれでうまくいったりを繰り返しながら世の中をなんとかしていく方がいい。効率はすごく悪いのかもしれないけど、世の中大バカだらけなので行程を踏むのは避けて通れない。てんやわんやの日々で世の中どうにかしていくしかないのはもう宿命なのだ。
ということで、よほどひどいやつ(弱者を平気で踏みにじるやつややたら差別的なやつなど)とは縁を切りつつ、それ以外の大バカたちへひとまず信頼を寄せて「よっしゃ〜、勝手なことやるぞ〜」って感じ。
出ました日本国憲法
さて、いよいよ本題。出ました〜、ついに登場の日本国憲法! 言わずもがな重要なのは冒頭の謎の宣言文「前文」だ。構成上、「これからこういう話するから、オマエら心して聞けよ」とばかりに、前文でひとまず基本的な考え方の芯をバシッと宣言して、それに続く各条文ではそれに基づいたジャンルごとの決め事を書き連ねている。ま、初っ端の第一条の「天皇」のところでいきなり前文の理念と辻褄の合わないこと言い出すのがちょっと拍子抜けなんだけど、それ以外は基本的に前文の理屈に基づいて書かれている。
さあ、なので今回はその日本国憲法の心臓部である前文を、世界マヌケ反乱の観点から見ていってみましょう〜。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
要は、みんなが納得する顔役を立てて、海外のやつらともうまくやりながら、みんなでのびのび楽しく末代までやっていこうじゃねえかと。で、そのためにも政府が余計なことして戦乱に巻き込まれることもあっちゃいけないし、そもそもうちらみんなで物事決めていこうじゃねえかっていうこと。冒頭から、争おうとしたり人の上に立とうとしたりっていう腐った根性のやつらに釘を刺すところから話が始まる。
これ、各地のアンダーグラウンド圏のやつらと交流する時にもこの気持ち持っとくのは重要なこと。よその連中とうまくやってこそってのがいいし、うちらがちゃんとやるから政府は余計なことして他所様と揉め事起こすんじゃねえぞと念を押してるところもいい。いきなり冒頭から、随分と欲張って宣言してる。こりゃ何か言い始めるぞコイツは、っていう空気感漂う前置きだ。
そもそも国政は、 国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
みんなが真剣に選んだ顔役の方々がいろいろ取り仕切って、ちゃんとみんなが恩恵を受けるようにうまくやっといてもらおうって話。ただ、これを勝手に思い違いして、何でもかんでも全部任せて自分らは恩恵を受けるだけなんてことになったら、そんな都合のいい話はない。で、全部他人任せにしといて、うまくいかなかったときに「どうしてくれるんだ!」と怒るんじゃ、顔役の方々が浮かばれない。そもそも全部任せるなんてできっこない。そういう話じゃない。
そう、この冒頭の「国政は」ってのがポイントで、社会を挙げてやんなきゃどうにもこうにもならない大仕事は、さすがに誰かがまとめ役として動かないとどうしようもない、ということで、それ以外のことはそれぞれみんなが右往左往しながら勝手にやりまくるのが筋だ。例えば、挨拶の仕方から酒の飲み方、その辺の喧嘩の仲裁まで全部他人任せで決めてもらおうなんてことを言ってるわけじゃない。ここは間違えてはいけない。世の中のほとんどのことは国政ではない。
いろんな人と交流する中で大きなイベントとかやる時も、それぞれのパートでのまとめ役は必要で、例えば音楽イベントなんかだったらこのステージはこの人にある程度まとめてもらうとか、警察とか近隣住民とかが文句言いに来たらひたすら怒られ続けてもらって時間を稼ぐ担当(顔役)とか、本格的な宣伝が必要な時は宣伝得意なあの人に任せよう、などなど。「国政」も実はその程度のもの。もっと言えば飲み会の幹事(または宴会部長)みたいなもの。適当な飲み会の時なんかは幹事はいらないけど、ちゃんとした会の時はいたほうがいい、そんな感じ。なのでこの段落は、「どうしても誰かにまとめて頼んどかないといけないときはやってもらうけど、勝手なことするんじゃなくてちゃんとみんなのこと考えて動けよ」ということだ。それも「これ頼むよ〜、無理だったら他の人に頼むから言って」という軽くふわっとした程度のもののはず。それが国政。
あ、それと最後に書いてある「その理屈に合わない妙な決め事は許さねえ」と眉間に皺を寄せる感じもしつこくて面白い。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
みんながお互いに敬意を払って、無用な揉め事は決してあっちゃいけないということ。いや〜、これもことあるごとに人の悪口ばかり言ってる最近の日本社会で重要な話。おまけに、威張ったやつが子分従えてのさばったり、すぐ人をひどい目に遭わせるようなせせこましい魂胆をこの世からなくすために、ここは一丁、世界の中でひと肌脱ごうじゃねえか、っていう大風呂敷にも程がある宣言! これは大きく出た! いや〜、この謎に理想高いハッタリかまして大きく出る言い回し、結構好き。できるかできないかわからないけど、とりあえず大きく出とけみたいな感じ。さてはこれ書いたやつ江戸っ子だな?!
そうそう、今も各国各地の地下文化圏の面白い店とかスペースのやつらと交流してるとき、確かに、それぞれの国や地域の事情や環境によってできることできないことも違うし、独自の困ったことも多い。でも、みんなでいろんな知恵を絞ってうまく地下文化交流圏が続く努力してる。何なら、しょうもない支配者たちの影響をいかにうまくかわして、世界各国に散らばるマヌケたちがお互いのDIY精神を信頼して、いかにみんな生き延びるかを常に知恵を出し合ってもくろんでいる。なるほど、そういうこと言ってるんだな、ここは。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
出ました〜!!! どこぞの富豪大統領が言い出してる自国中心主義を80年前に釘刺してる。テメエさえよければ他人はどうなったって構わねえなんていう自分勝手な了見は、俺の目の黒えうちは許さねえし、オメエさん方もそこは曲げちゃなんねえとこじゃないのかい、ということ。これ当然国家間だけじゃなくて、人と人が触れ合う時の基本中の基本。世界のマヌケたちが交流するときも同じで、例えば海外でイベントをやってもらったら、その人たちが来たら何か企画してあげたり、あるいは商品を取り扱ってもらったら、こっちでも仕入れてあげたり、泊めてもらったら泊めてあげたりなどなど、完全に平等には無理だとしても、持ちつ持たれつの方が関係は続くし、相手の善意を吸い上げて一方的にどちらかがいい目に合うみたいなことやってたらバチ当たるよってことだ。う〜ん、わかってるねえ、憲法の親方。人格者だよ、あんた。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
最後に「こうなりゃ乗りかかった船、トコトンやってやろうじゃねえか、ばかやろう」の一言。いやー、この誰からも言われてないのに、自分でなんだかんだ言い出して追い込んだ末、勝手にテンション上がっちゃって、畳の上にどっかと大あぐらかいて座り込んで「やると言ったらやる。止められるもんなら止めてみろい、べらんめえ!」と、意地張り出しちゃった感じ。「まあまあ、気持ちはわかったから。無理にそこまで言わなくても」と周りがなだめても「バカヤロー! テメエら引っ込んでろ!」と逆効果な感じ。いや〜、子どものころ近所(東京・江東区)にこういうオヤジとかおばちゃんよくいたな〜、いや、最高すぎる。それに言われてみれば自分でも身に覚えある。みんなで飲みながらやたらスケールのでかい計画の話なんかしてる時、勢い余って「よっしゃ〜、やっちまうか〜! やろうやろう!」ってなることよくある! わかる! その気持ちわかるよ、日本国憲法!
日本国憲法を現代に生かす作戦!
と、柄にもなく日本国憲法の基本理念を研究・解説してきたわけだけど、読めば読むほど、江戸っ子のオヤジが銭湯の脱衣場ででかい話し始めちゃってるようにしか聞こえなくなってきた! でも、なかなかいいこと言ってる!
しかし! 唯一、難点がある。国という規模がでかすぎるということ。例えば日本は1億2千万人もいる。その規模で「一つの社会」を築くのは到底無理。特に、みんなの信頼を受けた顔役に大仕事任せましょうなんてくだりはまさにそのもので、顔なんか見えっこないし、顔の見えないやつなんか選べっこない。もっと言えば国の規模の違いもあって、数十万人の国がある一方で数十億人の国もある。これで、お互い対等に主権を尊重してうまいことやってくれって、そりゃなかなか難しいでしょ。
でも、この規模感がどこもだいたいひとつの村や集落、またはJRの駅ひとつ分ぐらいの規模だったら一挙にうまくいきそうな気がしてくる。確かに憲法ができた戦後すぐの状況を考えれば、国単位で物事を決めないといけなかった事情もあるんだろうから、百歩譲ってそれは勘弁するとして、それから80年経ったいま、交通やインターネット、貿易や経済など、ありとあらゆるものが混ざってきてるので、さすがに現状のこの巨大な「国」単位で全ての物事を考えようっていうのはさすがに無理がきてる。
ただ、その憲法の言わんとしてることはよくわかる! ということで、ここは試しにひとつ、規模感を変えて、前文の冒頭部分を集落単位に単語を置き換えてみよう。
うちの集落は、正当に選挙された寄合における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、近所の集落の人たちとの協和による成果と、うちの集落全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、町内会長の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が集落のみんなに存することを宣言し、この憲法を確定する。
ほら、これなら急にリアリティがあるようになってきた。なるほど、そういうことか! じゃあ、やはりここは日本国憲法の理念を尊重して国をバラバラにして、今の規模感での「国」にとらわれなくても済むような社会を作るのがいい。別に今の日本サイズの行政区分はあってもいいけど、重きを置くべき規模感がどうも間違ってるんじゃないかって気がしてならない。今の「日本国」はそのままでもいいけど、もう少しグーッと存在感薄くなってもらって、霧がかかったぐらいにして、実質はその中の数千に分割独立した小国がクローズアップされる感じ。そして数千の日本国憲法(名前は変わるかな?)。これはやばい!
特に昨今の世界では、大国ぶったでかい顔したやつらが何の遠慮もなく威張り始めたり好き勝手やり始めたりと、歯止めが効かなくなりつつある。ここはこの日本国憲法を戴く日本が「オメーら、そうじゃねーだろ!」と、裸一貫(平和主義)で乗り込んで言い放ってやるのがいい。それに、前文で「世界でひと肌脱いで、トコトンやってやろうじゃねえの」と啖呵切ってしまった以上、ここは戦後80年を機に、我らが日本が率先して日本の中に数千の小国を新設し、「オマエらももう少し細かくやってくれ。デカすぎて話がわかんねえよ! もっとチマチマやれコノヤロー」と言ってやろう。
そして話は戻って世界マヌケ革命。実際に世の中を作るのは「国家」の代表を語る宴会部長の人たちではなく、その辺をウロチョロする無数の謎のやつら。そういう意味でも、国の力が薄まってもっと細かくなれば、民衆と国が近い存在になっていくに違いない。そうすれば憲法もすごく生きてくるはずだ。
よし、まあとりあえず国がこっちに近づいてくるまでは、その土壌作り兼ねて勝手にやっておこう。近づいて来ずに逆行して富国強兵みたいなことになるなら引き続き全無視してやっていけばいいし。
ということで、憲法マヌケ解釈、これにてお開き〜。
*

マガジン9連載:松本哉の「のびのび大作戦」https://maga9.jp/category/matsumoto/