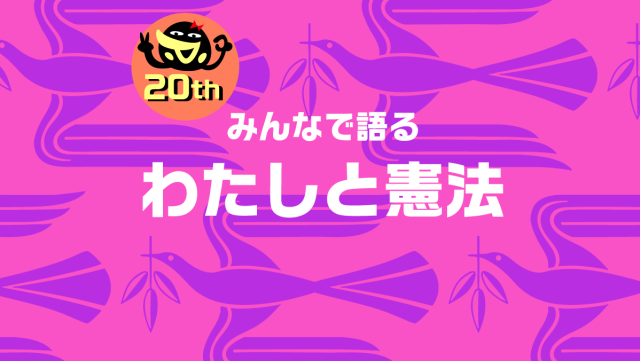コツコツと週1回の更新を続けてきた「マガジン9」、気付けば今年3月で創刊20年を迎えました。創刊当時の名称は「マガジン9条」。その後「マガジン9」の名前になってからも、「憲法と社会問題」を変わらずテーマに掲げてきました。
そこでこの20周年を機に改めて、「あなたにとっての憲法」について、いろんな方たちに語っていただこうと考えました。憲法が持つ意味は、大事だと思うことは、好きな条文は──。さまざまな分野で活躍するみなさんの思いや考えに触れつつ、あなたにとっての「わたしと憲法」を、ぜひ考えてみてください。
*
語ってくれたみなさん(50音順)
青木美希さん(ジャーナリスト)
いとうせいこうさん(作家・クリエーター)
伊藤千尋さん(国際ジャーナリスト)
上原公子さん(元国立市長)
「ウネリウネラ」竹田麻衣さん(文筆・出版業)
荻原博子さん(経済ジャーナリスト)
金子勝さん(淑徳大学大学院客員教授)
金平茂紀さん(ジャーナリスト)
鎌田慧さん(ルポライター)
五野井郁夫さん(政治学者)
斎藤貴男さん(ジャーナリスト)
佐高信さん(評論家)
四國光さん(詩人/画家四國五郎・長男)
志田陽子さん(武蔵野美術大学教授)
白井明大さん(詩人)
鈴木耕(ライター・編集者)
竹信三恵子さん(ジャーナリスト)
田端薫(マガジン9スタッフ)
中島岳志さん(政治学者)
永田浩三さん(武蔵大学教授、元NHKプロデューサー)
平井美津子さん(大阪府公立中学校教師、映画『教育と愛国』出演)
福島みずほさん(参議院議員)
保坂展人さん(世田谷区長)
芳地隆之(マガジン9スタッフ)
盛田隆二さん(小説家)
柳 広司さん(小説家)
- 青木美希さんジャーナリスト
- 今年は治安維持法から100年になります。表現の自由は守られているでしょうか。憲法21条にはこうあります。
- 記者たちから表現の自由が侵されているとの訴えを見聞きするようになりました。
私も体験している一人です。
大手メディアは原発は安全だという「安全神話」を長く流布してきました。私は読者として、また研究者の娘としてその姿を目の当たりにしてきました。新聞社3社の記者をしてきたのですが、5年前に突然記者職を外され、それでもなお休日を使い、社名を名乗らずジャーナリストの名刺で原発を追ってきました。
メディアを含む原子力ムラの実態を描く本を出版しようとしたところ、現在の勤務先から再三にわたって出版が認められませんでした。それでも個人として『なぜ日本は原発を止められないか?』(文春新書)を出版しました。出版後も圧力を受け続けています。
日本政府は今も原子力緊急事態宣言中で、数万人が避難しています。事故の甚大さを身をもって知ったこの国の政府が、なぜ原発事故を忘れさせ、再び原発を新設しようとするのでしょうか。福島の事故を受けて建設費が高騰しているため、政府は私たちの電気料金に新設費を上乗せする検討をしています。
一方で、福島の被災地の現状を載せてもらえない、大事なところを削られたという現場からの訴えは多数届いています。メディアの言論規制強化は、再び原発事故や戦争を繰り返し、多数の住民が命や生活を脅かされる事態に加担することになります。
今を生きる者の責任として、私は事実を伝え続けたいと思っています。
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
- いとうせいこうさん作家・クリエーター
- 憲法は誰が制定したのかという問いが繰り返され、むろん日本人自身だという人がいれば、戦勝国アメリカだという人がいる。
制定の経緯の詳細はここでは抜きにして、「誰が」を「何が」に置き換えてみたい。つまり制定を背後からしっかりと押してやまなかった何かとは、という質問だ。「だからそれが日本を支配下に置きたかったアメリカだ」と再び頑強に主張する向きもあろう。
しかし私はその「何か」は死者だと思っている。戦地に送り出されて餓死した方々、飛行機ごと敵艦体の上を目指すことになった方々、戦地でなく日本の中で火の海に呑まれた人々、あるいは異国で生まれて日本のために命を落とすことになった存在を含めて、あらゆる死者が憲法の後ろにいると感じるのだ。
同じ悲劇を起こさないために、別の幸福を築くために、それは生者の現在を超越し、そのスパンの短い欲望を抑制して「平和と安寧」を希求しなければ死者は報われない、と当時ガレキだらけになった日本に生き残った人々は考えただろう。そしてそれが彼らを倫理的にしたはずだ。つまり死を前にして。
今、そうした死者を忘れた生者が横行してやまないと感じるが、それは私が小さな頃から東京下町の、たいていは橋のたもとあたりで大空襲の犠牲者を慰める地蔵像、関東大震災の被害を記憶しようとする石碑を見て育ち、今でも頭を下げるからだろう。
私は死者の代弁者でありたい。
それは憲法の背後にある、最も根本的で揺るぎない考えではないか。
- 伊藤千尋さん国際ジャーナリスト
-
なぜ憲法9条の碑を建てるのか
全国に、いや海外にも、憲法9条の碑が次々に建てられています。
記念碑と言えば普通、過去の業績を忘れないために建てますが、9条の碑は違います。過去の事実を見据え、間違った方向に進もうとする現在の社会をただし、だれもが安心し輝いて生きることができる社会を未来につくりあげる指針として建てるのです。
僕が初めて見た9条の碑は日本ではなく、アフリカ沖のスペインの島でした。世界の国が軍隊を無くせば、本当に地球は平和になる。その第一歩を日本の憲法が実現したことに感動したスペイン人が街の中心部を「ヒロシマ・ナガサキ広場」とし、日本国憲法9条の記念碑を設置したのです。他国の憲法のために土地も資金も出して記念碑を作った。僕はあらためて憲法9条の価値を知った思いがしました。
その後、日本にも9条の碑があることを知りました。最初に見たのは沖縄・読谷村の役場の前です。沖縄戦から50年を記念して村が建てました。趣意書には「すべての生命が当り前にその一生を終えることができる社会、平和なうちに生命を次ぎへとつなぐことのできる社会こそ私たちの願い。その社会の実現を信じよう。我々自身の力を信じよう。世界中が9条の精神で満ちることを信じよう」と書いてあります。沖縄の村が世界に向けて堂々と平和を訴えているのです。
そこから全国の9条の碑を訪ねまわる活動を開始しました。23の記念碑を回って2022年に『非戦の誓い』を出版し紹介したところ、各地で9条の碑を建てる運動が広がりました。昨年だけで14もつくられ、今や50を超えています。
茨城県では2024年、自衛隊基地の真ん中に9条の碑が完成しました。基地建設のさい買収に応じなかった農民が、滑走路のすぐそばにある自分の土地に建設したのです。9条も医療も命を守る点で共通していると、今や全国10の病院に9条の碑が建ちました。被爆80年とノーベル平和賞受賞を記念して今年、長崎の被爆の丘にも9条の碑が完成します。
三重県で9条の碑を建てた元高校教師は言います。「戦時中、小学校の校門を入ると奉安殿があり最敬礼するのが日課だった。それが私を軍国少年にした。今、どこかの学校に建つ9条の碑を観てから死にたい」。日本中すべての学校に9条の碑を建てたいものです。そうすれば平和少女・少年が育つでしょう。
- 上原公子さん元国立市長
-
2015年、安保法制をめぐって、学生を中心とした若者たちの団体SEALDsが、デモや集会のあり方を一変させた。彼らは、憲法の理念がないがしろにされていることに対し、自由と民主主義を守るために行動するとした。そして驚いたことに、「憲法は未完のプロジェクト」と称している。憲法のことを、なんと実に明快に表しているのだろうか。そう、憲法の質を高めるのは、私たちの仕事なのである。いかに、憲法の精神を使いこなすか。それによって、私たちの自由で民主主義社会が一層豊かになるし、使わなければ、忘れてしまえば、たちまち自由と民主主義は失われていくのである。
私は1999年に市長に就任する前の4年間、憲法学者が主宰する憲法教室に通っていた。先生は、講義の前に、一週間分の新聞から記事をピックアップし、憲法の視点から解説された。その経験から、市長になってからは、議場に憲法の解説書を携え、議論の武器としてきた。
憲法第97条の「基本的人権」は、すべての人が自分らしく生きる権利を有するとしている。自分らしく生きることの意味や価値観は、時代とともにどんどん変化し、成長し続けている。だから、憲法は永遠に「未完のプロジェクト」なのである。
憲法は、お題目ではなく、使いこなして、社会に実現させて、初めて生きてくる。
さあ、憲法をどんどん使いまくろう!!
- 「ウネリウネラ」竹田麻衣さん文筆・出版業
- 言葉を明らかにすること
- ここ数年、急速にSNSの使い方が難しくなったなと感じています。
細々と文章を書く仕事をしているのですが、旧Twitterでそれを拡散することは、ほとんどなくなりました。かつては、書いたものを通じて、読み手の方々と意見を交わすことに意義を見出していたのですが、それが困難だと感じる場面が、あまりに多くなったからです。
もちろん今も、ネット上で思いがけないつながりを持つことや、ほっと和むこと、励まされることもたくさんあります。ただ、何かを深く議論をする局面となると、SNS上ではよく話が噛み合わなくなってしまうのです。 - この「噛み合わなさ」はなんだろう、と考えた時、そもそも考えの起点や前提事項の理解にズレがあることに気づき、それを何とかほどこうとするのですが、やはりどうしても躓いてしまいます。そこでさらに考えてみると、論を構成する一つひとつの「単語」の定義が、相手の思うところとまるで違っているのだな、と思い至ったことがありました。
- 憲法をめぐる議論にも、同じような困惑をおぼえることがあります。
- 私が憲法を脅かす様々な出来事に対し、肌感覚で危機感を覚えたのは、子どもたちを膝に抱いている頃でした。
いまは中学一年生になった一番上の子がこども園に通っていたころ、園の職員や保護者、地域の人たちが、時折、憲法についてのお話会を開いていました。お茶を飲みながら、お菓子をつまみながら、もちろん小さな子どもたちも傍らに、ピンク色の小さな冊子『わたしとあなたの・けんぽうBOOK』(水野スウ)のページを、ゆっくりと繰っていきました。 - 「基本的人権」って何? 「平和」とは、「自由」とは。それぞれが、思い思いの言葉でぽつりぽつりと考えを述べると、それに対する感想や意見が、ぱらり、またぱらりと集まってきます。するとそれぞれの持つ「憲法観」のようなものと、その集合体としての「憲法」が、少しずつ、かたちを持って立ち現れてくるようでした。
憲法を構成する重要な言葉の意味について、それぞれが深く考え、その考えを互いに差し出し、他者との違いを理解した上で、共通の言葉を定義していく──。今思えば、あの小さく和やかな場で、とても大事なやり取りが交わされていたのだと実感します。 - 憲法が民主主義を支え得るのは、あらゆる人々が、日頃からそれをじゅうぶんに咀嚼しているという前提があってこそだと思います。しかし、その咀嚼が足りているかと言えば、そうではないような気がします。「議論」が必要だということはもちろんですが、私たちはそのもっともっと手前のところで、ずっと躓いてきたのではないでしょうか。
- 日本の憲法を英語に訳した時の単語数は4998語と、世界で5番目に少ないとされています。そのメリット・デメリットについては、専門家により様々指摘されていますが、長過ぎない憲法が、どんな人にとっても「携えやすい」ものであることも確かです。みんなが自分なりのペースで、その単語の一つひとつからじっくりと噛みしめるのに、無理のない分量であるようにも思えます。
- 私の思う「平和」とは何で、誰かが考えている「平和」とは、どんなものなのか。それぞれのかたちと差異を、きちんと明らかにすること。その誰かと共に生きていくために「平和」という言葉をどう位置づけるべきなのか、一緒に考えていくこと。自分の持っている字引だけで解釈するのではなく、相手の字引も借りてきて、とことん、話し合うこと。考えや立場を超えたあらゆる人たちと言葉を明らかにする営みを、諦めないこと。そうした丁寧な営みが不可欠だと、今、切に思っています。
- 「不断の努力」とはそういうことなのではないかと私は考えます。
- 荻原博子さん経済ジャーナリスト
-
貧富の差が激しくなっています。日本は世界第3位の経済大国でありながら、相対的貧困率は15.4%で7人に1人が貧困であり、貧困率ではアメリカの15.1%、韓国15.3%を上回っていて、先進国の中では最低の国ということになっています。
こうした中で大切なのは、憲法25条の「すべての国民は健康で文化的な最低限どの生活を営む権利を有する」をどう守るのかということ。
これを守るためには生活保護を強化しなくてはなりませんが、生活保護率はなんと1.62%(2024年5月厚労省データ)。貧困でありながら、憲法で保障されている生活保護からこぼれ落ちている人が多数いるということです。
自民党は、憲法改正などと騒いでいますが、その前に今の憲法を遵守し、多くの国民が健康で文化的な生活を営めるようにすべきでしょう。
- 金子勝さん淑徳大学大学院客員教授
-
財務省陰謀論が流布されている。私も、財務省は増税を企んでおり、財務省が財政統計をごまかしているのではないかという質問を受けました。
答えは全く逆です。政府は増税をせずに、赤字国債によって防衛費を膨張させています。戦前は臨時軍事費特別会計を作り、一度も決算しないまま赤字国債で軍事費を調達しました。ところが、いま財務省は、それとは異なる手法で国会のチェックなしに防衛費を膨張させています。
5~10年のローンで自衛艦を建造するやり方を「後年度負担」と言います。国会のチェックは最初の年だけです。つぎに大災害などに備えるための「予備費」も閣議決定だけで支出できるので国会のチェックが利きません。新型コロナウイルスの流行時に毎年10兆円まで膨らみました。さらに政府はさまざまな「基金」を作っており、いまや18兆円も基金は余っています。
私たちは軍事国家の歯止めとして憲法9条ばかり注目しがちです。しかし国会の審議と議決に基づいて予算や税金を決めるという憲法83~85条の規定は、軍事国家化を防ぐための近代国家の規定です。歴史的には、イギリスのマグナカルタや権利の章典にさかのぼります。それがいま破壊されているのです。
- 金平茂紀さんジャーナリスト
- 『平和に生きる権利』を聴くとき
- 先日、吉祥寺のライブハウスで、ミュージシャン大熊ワタルさんの誕生日を祝う『大熊祭』コンサートがあるというのでいそいそと出かけた。多種多彩な音楽が奏でられて楽しい夜となった。
大熊さんのコンサートで定番のように歌われているレパートリーに『平和に生きる権利』という曲がある。チリのフォルクローレ音楽家ビクトル・ハラの曲だ。この曲を聴くと僕はいつもなぜか憲法のことが心に浮かんでくる。原曲はチリだからスペイン語なのだが、日本語の歌詞は原曲の内容とはズレがある。ベトナム戦争の渦中でつくられたオリジナルの歌詞は、北ベトナムの民衆から慕われていたホー・チミンへの賛辞も含まれていた。大熊さんたちのバージョンの歌詞(こぐれみわぞうさんがアレンジしたようだ)にはない。けれども日本語の歌詞には原曲の精神がむしろ普遍的な形で引き継がれているように思うのだ。原曲の精神の核心は、弱い者、虐げられた者よ、立ち上がれ! との勇気づけにあるように思う。しかもメロディラインが美しくて、ある種の運動歌のように決して強圧的ではない。虚心になって読めばわかるのだが、日本国憲法の前文や、戦争放棄を謳った9条、思想信条、言論表現の自由、生存権を保障した憲法の各条文には、先人たちが希求した理想、公正さの実現へのみずみずしい決意が溢れている。
ビクトル・ハラは、選挙によって成立したチリのアジェンデ社会主義政権を軍事クーデターによって崩壊させたピノチェト将軍の軍によって1973年、射殺された。40歳没。
憲法を葬ろうという者たちがSNSなどを駆使して世の中に跋扈している。最近、好んで自分に言い聞かせている語句がある。「頭をあげろ!」。戦後40年の年に御巣鷹山に墜落した日航ジャンボ機の操縦室(制御不能に陥っていた)で、機長が最後の最後まで声を振り絞って発していた言葉だ。機首を高く立て直せという意味が、僕にはビクトル・ハラの歌のようにしみる。
- 鎌田慧さんルポライター
- 日本国憲法の誇りは、戦争放棄にある。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を維持しようと決意した」「国際社会において名誉ある地位を占めたいと思ふ」の憲法前文を私は誇りに思う。9条の戦争放棄の清々しさを、自民党改悪案は俗悪な駄弁で汚そうとしている。無謀な戦争の反省と非戦の決意は、国際平和主義の原点です。
- 五野井郁夫さん政治学者
- 戦後政治学にとっての憲法
- 政治学者の丸山眞男は、日本国憲法の基本原則にかかわる問題では日本にとっての「復初」(はじまりに立ち戻ること)から考えるべきだと説いた。この国のはじまりは何か、と。自前で強大な軍事力を保持しうるものの、戦後の廃墟の中から新しい日本の建設を決意したわれわれは、他国の誰一人をも殺すことなくこれまで八〇年間、平和を歩んできた。一九四七年に施行された憲法九条は、いまや現実にこの国の基本理念となった。近年では日本が掲げる非核三原則に、国際社会が核兵器禁止条約で追いついてきた。日本は改憲で戦争に後戻りするのではなく、平和憲法という日本の現実に世界が追いつくよう九条の精神を世界に広めていくことが、世界平和への貢献なのである。
- 斎藤貴男さんジャーナリスト
-
中学、高校生あたりまでは、「フン、憲法なんか」としか思っていなかった。戦争放棄と基本的人権の尊重と国民主権が三大原則で、なんて教えられても、そんなもの当たり前だし、日本だかアメリカだか知らないが、どっちみち国家権力が作ったもんじゃねえか、支配のための道具だろ、などと。
その「当たり前」を「当たり前」でなければならないと感じさせてくれているのが日本国憲法なのだと、骨身にしみて理解できるようになったのは、恥ずかしながら、30歳代も半ばを超えてからである。キッカケはたくさんあり過ぎるので割愛。
で、この憲法を絶対に手放したくないと、私は考えてきた。どんなに酷い世の中になったとしても、最後の最後にはギリギリの歯止めになるはずだと信じたからだ。ところが──。
このところの形骸化、というか、ほとんど無効化が、あまりにも甚だしい。2015年に可決・成立した安保法制は言うに及ばず、最近だと各地の高等裁判所が、同性婚を認めない現行民法を違憲と判断するのに、憲法24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」の「両性」を、「当事者」と読み換えればよいとしている始末。
こういうアクロバティックな論法を、専門用語で「憲法の変遷」と呼ぶそうだ。時代が変わり、国民の価値観も変わったと見做せられたら解釈も変わり得る、という。保守もリベラルも、それぞれの“正義”に従って、「解釈改憲」の方法論を濫用している図だ。
理窟がわからぬではない。どちらも結局は13条の定める国民の幸福追求権に適うのだから問題ない、と主張されている。だが、それを言い出したら、何だってできてしまう。憲法の意味がなくなるだけならまだしも、歯止めの体裁を取り繕いつつ、その実、政治権力やグローバル資本が企図する方向の実態を不可視化するという、タチの悪い機能に変質していきかねないのだ。
目的が正しければ、多少の乱暴は許される? ノーである。SNSによる世論誘導が常態化した現代社会。単なる身勝手が、いつの間にか“正義”にされていく可能性を、いったい誰が否定できるというのか。
ここまで来てしまったら、私はもう、何が何でも「憲法を守れ」とは言えなくなった。解釈改憲よりは正規の憲法改正のほうがまだマシ、かもしれない。きちんとした手順が踏まれ、それなりの論議が尽くされるのであれば、という条件付きではあるけれど。
こんなことを書いたら、「マガジン9」の読者にはきっと嫌われるだろう。しかし、護憲の立場だからこそ、見て見ぬフリをし続けたら必ず足元を掬われる、大切な論点だと、私は確信している。
- 佐高信さん評論家
- 「戦争はすべてを失わせる、戦争で得たものは憲法だけだ」と言ったのは城山三郎である。また、中村哲は「憲法は戦争で亡くなった人の位牌のようなもの」と言ってアフガニスタンで憲法の理念を実践した。私は一時、9条より99条をと主張した。99条には憲法を壊す危険性のある者が列記されているからである。
- 四國光さん詩人/画家四國五郎・長男
-
集団的自衛権の行使に対して違憲判断を示した憲法学者の長谷部恭男教授が、憲法についてこのように書かれています。「日本国憲法に定めてある条文の一つ一つも、過去にしてきたことへの失敗があるからこそ、『そういうことはやめてください』と書いてある。ですから、憲法は人びとの歴史から、同じ失敗をしないための教訓として、現在まで受け継がれている」(『憲法の良識』)。
多くの国に多大な犠牲を強いた、あの戦争を二度と繰り返さないために、第12条に規定されているように「不断の努力によつて」、改悪の動きに抗い憲法の要を守ること。それが、これから社会の主役となる子供たちの命の砦として、われわれ主権者がなすべき責務だと思っています。
そして何よりも、今の憲法は、多大な犠牲を強いたアジア諸国などに対して「決して同じ過ちは繰り返しません」という約束であり誓いです。
この憲法に対してどのような態度を取るか。それは、人としてあるべき倫理観を問われる問題ではないでしょうか。私はそのように思っています。
- 志田陽子さん武蔵野美術大学教授
- 遠くを見る目と身近なことに気づく目と
-
憲法は、建物で言えば土台や柱にあたるもので、国とそこに生きる人々の生活を支えるための基本ルールです。そして、何百年もの人類の努力によって少しずつ築き上げられてきたもので、しかも何百年も先の人々に遺産として残していくべきものなので、その意味や存在価値を理解する作業も、尽きることがありません。
その中で最近とくに思うのは、憲法を生かすとは、そういう意味で《遠くを見る目》を持ちながら、自分の身の回りで起きる一見小さな身近なことへの気づきを大切にすることだ、ということです。国際社会の平和や国の統治を考えるという大きな視野と、子どもや高齢者の家庭内・施設内虐待をどう防いで、幸福追求権を考えた《くらしづくり》に貢献する知恵を編み出していくかという《身近なことに気づく目》と……。この二つの目を同時に持つことはなかなか大変ではあるけれど、これができないと憲法は生かせない、憲法はそれを私たちに求めている、だから学びは尽きないのだと思っています。
- 白井明大さん詩人
- 人間が先、国はあと
-
戦争のはじまりは、差別と貧困じゃないかと思う。
差別と貧困は、作られたもの。
世の中に差別がはびこるにつれて、人と人のあいだに憎しみの溝が広がっていく。むやみに他国を敵視する言動が大手をふって歩くようになる。
暮らしが貧しくなるにつれて、自分より貧しい人に、弱い人になぜだか矛先を向けてしまう。そしてますます憎しみの溝が深まってしまう。
ねぇ、たった八十年。ほんの八十年前に、この国は、あちこちの国に攻め込んで、あげくのはてに焼け野原になった。もう二度と戦争はしませんと誓って、なんとかもう一度、国際社会の仲間入りを許されて、平和主義をかかげる国に生まれ変わってやってきた。
戦争で平和は守れない。はじめたらおしまい。ミサイルの雨がふってくるのを止められない。雪だるま式にエスカレートして、おたがい攻めあってボロボロになる。
戦争した国は、全員負け。
平和を守れるのは、平和だけ。
じゃあ、どうしたら?
差別をなくそう。実体のない空虚な憎しみなんかに、心を明けわたさないように。
貧困をなくそう。もともと共同体の富は、そこで暮らす人と人が分け合うものだから。
わたしとあなたと手を取り合って、誰もが平和に、自由に、健やかに、のびのびと暮らせるように、国という共同体を築いたのだから。人間が先、国はあと。わたしのために、あなたのために、一人ひとりの人間のために、国はあるの。
誰もが平等に、自由に、健やかに、豊かに、平和に、のびのびと生きていけることを、わたしは望む。
憲法にもそう書いてある。わたしが、そう決めた。この国の主として、平和を愛するこの世界の一員として、わたしが、あなたが、一人ひとりの人間が、この日本国憲法を決めた。
- 鈴木耕ライター・編集者
-
ぼくは、ベタですがとにかく「9条」が大切だと思っています。「戦わないこと」が生き延びるための最善の策だと思うから。
軍隊を持たない、人を殺さない、人を援ける、人とともに生きる。これが「憲法9条」の精神でしょう。精神なきところにいのちはない。
だからぼくは「自衛隊改組論者」なのです。
自衛隊は、以下の3隊に改組する。 -
緊急災害援助隊
国際災害援助隊
国境沿岸警備隊 -
日本ほど自然災害の多い国は、世界中を見回してもあまりありません。最近の例でも、能登地震、集中豪雨、岩手沿岸山火事…など半年に一度ほどの頻度で大災害に見舞われています。能登地震では援助が完全に出遅れました。むろん、地形や天候など遅延の原因はたくさんあるでしょう。だからこそ、さまざまな状況に備えた訓練や機材の準備などを常にしておくべきです。それに特化した援助隊の編成が必要なのです。
海外の災害援助は外交手段として大切です。外国語のスペシャリストを配置し、緊急時の派遣手段(航空機や艦船)を持った海外援助隊こそ外交の要です。
それでも最低限の国境警備は必要でしょう。海上保安庁を含んだ沿岸警備の部隊を再編制しておくべきです。
最近は自衛隊員不足に悩んでいる。若者が戦争準備の訓練などに拒否感を持つのも分かります。しかし、一方でボランティア活動に熱心な人たちは大勢います。彼らは災害援助のモチベーションは高いはず。新しい就職口としての『自衛隊に入ろう』(高田渡)ですよ。
そのもっとも崇高な精神を掲げているのが「憲法9条」だと、ぼくは思うんです。
- 竹信三恵子さんジャーナリスト
-
男女平等、生存権、労働権と、社会が危機を迎えるたびに憲法のことを思い出し、これに沿って立て直すんだ、と思ってきました。ただ、これは本当に危ない、と思ったのは「5年で43兆円」の異次元の軍拡予算がいきなり登場したときでしょう。
それまで9条の重しによって、歯止めがかかっていた軍拡が、安保法制をはじめとする解釈改憲で解き放たれたようになり、女性の自立に不可欠な社会保障も、働く人の支えも、生活に困って死に追いやられていく人たちの生きる権利も、わきに追いやられていく感じを体感しています。
放蕩息子のように際限なく乱費に向かうのが軍拡の常です。「若旦那、気前がいいね!」とはやされて、言われるままにお店のお金を持ち出さないよう、これまで待ったをかけていた律儀な番頭さんが、邪魔者扱いされて姿を消し、お店が傾く、という落語の世界のような状態に、日本が追い込まれていく気がします。
いなくなって初めてわかる、番頭さんの価値です。いまこそ憲法を掲げて、放蕩息子を悔い改めさせるか、追い出すかしなければ。
- 田端薫マガジン9スタッフ
-
「今ウクライナが停戦に応じたら、87年前のチェコ・ズデーテン地方のようになってしまう。カオルは歴史から何も学んでいないの?」「じゃあ戦争を続けろというの? 毎日何人もの人が死んでるのよ。とにかく停戦して、その後外交交渉すればいいじゃない」。ヨーロッパ人の夫と私の、ウクライナ戦争をめぐる茶の間の議論はいつもこんなふうだ。
夫がいう歴史の教訓とは1938年のミュンヘン会談のこと。ドイツ系住民が多数を占めるチェコのズデーデン地方の帰属を求めるヒトラーに対して英仏の首脳は、これ以上の領土要求を行わないことを条件に、ヒトラーの要求を全面的に認めた。その宥和政策がナチスの勢力拡大を招き、世界大戦への道を開いた……。
夫の言うことは正しい。けれど毎日のニュースを見るたびに「とにかくやめて」と言わずにいられない。この「とにかく」というのは、戦後の平和教育を受けて「9条は日本の宝、人類の叡智」と信じ、大学時代にべ平連の「殺すな!」に感化されて生きてきた団塊世代、全共闘世代が内面化している本能的感覚だろう。反戦というより脊髄反応としての厭戦と言ってもいい。
憲法9条2項は確かに現実と矛盾している。世界第7位の軍事力を持ちながら「これを保持しない」なんて嘘じゃん。「専守防衛としての自衛隊の存在を認めて、歯止めを明記する」などなど、護憲的改憲論とか、新9条論とか、確かに頷ける。それでもなお理屈抜きでこの矛盾だらけのお花畑的理想論を死守したい。団塊世代も遠からず消え去る。その時までとにかく9条をこのまま残してください。
- 中島岳志さん政治学者
- 死者の立憲主義
-
私は憲法の主語は、死者だと思っています。民主主義がどうしても生きている人間の過半数の支持によって決定されるのに対し、憲法はその判断を拒否することがあります。例えば、いくら国会の過半数が「言論の自由を多少抑制しても構わない」という法律を通そうとしても、憲法はその決定を拒絶します。過去に様々な困難にぶつかり、失敗体験を繰り返してきた死者たちが、自分たちの経験に即して、「こんなことはやってはいけない」と未来の国民に制約をかけている。これが「死者の立憲主義」です。
このことがよくわかるのが97条の条文です。97条は基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と明記していますが、それは「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であり、「過去幾多の試錬に堪へ」たものとして「現在及び将来の国民に対し」「信託されたものである」とされます。この条文の主語は、間違いなく死者たちでしょう。「幾多の試錬」に直面してきた死者が、未来の私たちに「信託している」。それが基本的人権の尊重なのです。
- 永田浩三さん武蔵大学教授、元NHKプロデューサー
-
何と言っても好きなのは、憲法の前文です。松元ヒロさんが舞台で、切々と語るとき、いつも涙がこぼれます。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
この憲法は、あのアジア・太平洋戦争の加害と被害を二度と繰り返さないと、世界に誓ったもの。戦争のない平和な世界をつくることを、国の基本にすえたのです。
にもかかわらず。被爆者や空襲被害者たちが国家による補償を求める際、政府が持ち出すのが「受忍論」です。戦争だから仕方がない、我慢せよというロジック。しかし、戦争だから我慢が当然という論法は、日本国憲法の精神に反するものです。にもかかわらず、野蛮な旧憲法下の呪縛からいまも逃れられないことは、あまりに情けない。
ノーベル平和賞を受賞した日本被団協は、核のない地球と国家補償を求め、被爆体験を世界に向けて発信してきました。
世界各地で戦争が続き、核戦争の危機がリアルに迫る中、逆に憲法の前文が光り輝いてみえます。この崇高な精神が体現される世の中をいっしょにつくっていきましょう。
- 平井美津子さん大阪府公立中学校教師、映画『教育と愛国』出演
- 学校の中にこそ憲法を
-
ブラック校則というものが未だに学校に横行している。下着の色から、靴下の色、髪形、防寒着まで多岐にわたっている。何のためにあるのかわからない校則。守らせることが目的化し、何のためにそれを守らなければならないのかが忘れられている。教師には指導力が求められる。だから、自分が疑問に思っていても、守らせるという指導力を発揮できなければ学校の中で教師として失格とされる。守らせるためには、時には怒鳴りつけるようなことまで起きる。それで守らせても、果たして子どもは納得できるのだろうか。
私は憲法13条を教えている。「憲法にはとてもいいことが書いてあるけど、とくに13条がすごくいいよ。人は個人として尊重され、幸福を追求する権利がある。どう? みんなが自分の幸せを求め、自分の意志で生きていくことが何よりも大切ということだよ」
この条文に一番ふさわしくないのがブラック校則だろう。教師がしなければならないことは、ブラック校則をやみくもに守らせることではなく、子どもたちの声を聞くことを土台にした教育だろう。憲法13条に基づいた学校教育を目指さなければ、子どもたちは学校でのびのびと生活ができないのではないだろうか。憲法を学校に生かす。学校の中にこそ憲法を。強く思う。
- 福島みずほさん参議院議員
- 私は日本国憲法が大好きである。日本国憲法は元気でいいんだといつも励まし続けてくれている。NHK の朝のドラマ『虎に翼』は本当に感動した。日本国憲法ができてそれを具体化していくこと、それが描かれていたからである。
- 私は弁護士として、例えば両親が結婚届を出さないで生まれてきた子どもである婚外子の住民票の続柄差別裁判、戸籍の続柄差別裁判、法定相続分の差別裁判等を担当した。かつては、住民票の続柄欄は「長男」「長女」「二男」「二女」など、婚外子は「子」と書かれていたのである。そのことが法の下の平等を規定した憲法14条に反すると提訴し、その代理人の一人になった。裁判の過程で、自治省が通知を出し、子どもはみんな「子」の記載に変わった。憲法を根拠に問題提起をすれば変わるのだということを実感した。生きている人間がいて、法律や制度があるのだから、それは変えられる、変えていくのだという確信である。憲法はだからその時まさに味方であった。
- 同性婚の判決で同性婚を認めないことは、憲法14条、憲法13条、憲法24条違反というのが高裁判決で出ている。その通りである。法の下の平等の憲法14条も家族の中の個人の尊厳と両性の本質的平等を規定する憲法24条も大好きである。戦争しないと決めた憲法9条ももちろん心の支えであり、憲法9条を活かしていくのだという思いで政治の場でがんばっている。労働基本権の条文も、健康で文化的な最低限度の生活を定めた25条の条文も大好きである。思想良心の自由を定めた19条、表現の自由を定めた21条もとても重要な条文である。でも1番大好きな条文は実は憲法13条である。憲法13条は個人の尊重と幸福追求権を掲げている。個人の尊重、そして一人一人がすべての人が幸福追求権を持つのだという。条文は全ての人を応援しているものである。
- 私は憲法を根拠に裁判を闘ってきたので、憲法は六法全書の中に閉じこもっているのではなく、まさに効力を持つ大事なものだと思っている。現実を変えていく「武器」とも言える。そして、具体的な効力を発揮してきた。憲法9条があったので、長らく日本は専守防衛、海外に武器を売らない、軍事研究はしない、非核三原則、敵基地攻撃能力は保有しないなど、憲法9条をもとに様々な政策、原理を打ち出してきた。憲法はまさに効力を持っているのである。だからこそ、憲法を守り、活かしていくことをたくさんの人とやっていきたい。
- 憲法は、法の下の平等と規定していても、個人の尊重、幸福追求権が定められていても、それらが現実化していない事は百も承知である。だからこそ、憲法をもとに現実を変えていく、そのことをこれからもたくさんの人とやっていきたい。
- 保坂展人さん世田谷区長
- 「憲法を使う」ことについて、もっと技術を磨き、角度を工夫していくことが大切だ。こんな感覚は、土井たか子(2014年没・元衆議院議長・元社民党党首)さんの側で、十数年を過ごしてきたことで「体感」したものだ。やはり同世代であった國弘正雄(2014年没・元参議院議員・文化人類学者)さんは「新憲法が出来た時に仰ぎ見るような感動を覚えた」と語っていたが、お二人とも、神戸大空襲などで街が焼け野原になり、多くの人が亡くなっていった原風景が原点にある。少し年長の田英夫(2009年没・元参議院議員・ニュースキャスター)は元特攻隊員で、体当たりボート「震洋」の艇隊長として出撃を待っている状態で8月15日を迎えたが、憲法に対する思いは熱かった。
「戦争だけは繰り返してはならない」という言葉、私の祖母や両親と食卓を囲んで語らった1960年代に何度となく聞いた。私の憲法は、こうして戦争体験をへた世代から引き継いだ「非戦」のメッセージである。また、私自身の経験として、中学校卒業時の内申書に「政治活動」について詳細に書かれたことを訴えた裁判で、16年間にわたり原告として活動したことも大きい。 「思想信条・良心の自由」をめぐり争った裁判で、「憲法を使う」という感覚が芽生え、在任中546回の国会質問で鍛えられた。現在は、空襲犠牲者への自治体としての見舞金に取り組もうとしている。これもまた、「憲法を使う」仕事のひとつだ。
- 芳地隆之マガジン9スタッフ
-
1980年4月。高校3年生になったばかりの政治経済の授業で日本国憲法第19条、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」が取り上げられた。先生は、
「君たちの先輩で『思想や良心は内面のものだから(自由は)当たり前のことではないですか。どうしてわざわざ憲法に書くんですか』という質問をする生徒がおった。君たちはどう思う?」
ぼくたちが答えあぐねていると、
「権力者はときに他人の心も支配しようとする。『そんなこと考えたらいかん』とか『そういう思想は危険や』とか。そういうことが二度と起こらんように、『人の内面に踏み込んではいかん』と書かれたわけや」
ぼくはジョン・レノンの『イマジン』を連想した。あの歌には「(頭の中で)世界はひとつになる」という詞があった。
6月12日、大平正芳首相が亡くなった。ぼくらの高校(旧制中学校時代)の先輩である。国会で「アー、ウー」と歯切れの悪い答弁を揶揄されることもあったが、クリスチャンで沈思黙考する政治家という印象が強かった。翌月に開催されるモスクワ・オリンピックへの不参加を、米国に追従して判断せざるをえなかったことも体調を悪化させた一因だったと思う。東西冷戦の時代。「想像してごらん、国なんてないんだ」と歌ったジョン・レノンは12月8日、ニューヨークで凶弾に倒れた。1980年はぼくにとっての憲法元年だった。
- 盛田隆二さん小説家
- 母がパーキンソン病で亡くなった後、認知症を発症した父を十年にわたって介護する日々にあって、老健に入所した折や、デイサービスを利用する際に、介護保険制度には感謝したし、精神科病院への入退院をくりかえす統合失調症の妹の世話をしながら、月の自己負担が二千五百円ですむ障害者総合支援法にはかなり助けられたという実感はあるものの、それらの制度や法律を憲法と結びつけて考えたことはなかった。
- でも今、改めて思う。明治憲法に存在せず、GHQ草案にもなかった生存権保障。医療や社会福祉を保障する憲法二十五条がなければ、国民はそれらの立法措置を講ずるよう国に求める権利さえ持たなかった。憲法は国民が生きていくうえで有効な武器なのだ。そんな思いを補強する新刊が出たので紹介したい。
- 大城聡『不確実な時代を生きる武器としての憲法入門』(旬報社)だ。「憲法は自分を守り、自由に生きていくための武器になる」と弁護士の大城さんは書く。大地震、カルト宗教、ブラック企業、生成AIなどに立ち向かう際の最強の武器になると説く。ハンセン病の人たちが「法律が間違えている」と宣言する力となった憲法。最高法規である憲法は「たとえ法律であっても泣き寝入りせずに、おかしいものはおかしいと闘える武器」なのである。若い人にこそ読んでほしい憲法の入門書だ。
- さて、米国ではトランプ政権が暴走の限りを尽くし、「法による支配」が危機に瀕している。そんな時代だからこそ、憲法前文が一条の光に思える。前文には「平和」という言葉が「恒久の平和を念願し」「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」「平和を維持し」「平和のうちに生存する権利を有する」と四回もくりかえし出てくるが、合衆国憲法でPEACEという単語は、「平時」や「平穏」の意味で使われるものの、「平和」の理念を謳い上げてはいない。また憲法二十四条では「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」としているが、米国では議論が何度も戦わされたものの「両性の平等」は憲法にいまだに記されていない。「平和」と「人権」を重んじる日本国憲法。とても誇らしい。
- 柳 広司さん小説家
-
憲法についてコメントを、というお題である。ここでいう憲法とは、聖徳太子の十七条憲法でもドイツのワイマール憲法でも大日本帝国憲法でもなく、一九四六年十一月三日に公布され、翌四七年五月三日に施行された日本国憲法のことである。
憲法とは何か? 小説家が抱くイメージは、国の有るべき姿、進むべき方向性を掲げた〈言葉の柱〉だ。日本国憲法は百三本の言葉の柱(条文)からできている。
有るべき姿である以上、現実と言葉の乖離は常に存在する。むしろ、放っておけば必ず腐敗する権力者の逸脱を押し止どめ、向かうべき道を示し続けるガイドが憲法の役割だ。
このため憲法(言葉)は、常に現実(権力)から挑戦を受けてきた。言葉を現実の側に引きずり下ろそうとする力に抗い、押し返してきたのが、戦後の市民運動である。最近「戦後の市民運動は失敗だった、無駄だった」というような声を聞くが、これは権力や資本が垂れ流す偽情報(フェイク)である。その証拠に、戦後八十年間、自分たちの都合に合わせて憲法を変えようとしてきた権力者たちの試みは、すべて失敗しているではないか。
日本国憲法は決して国際社会で孤立したガラパゴス的存在ではない。国連憲章と重なる部分の多いグローバルな言葉の柱だ。ロシアによるウクライナ侵攻、さらにはイスラエルによるガザ虐殺の現実を前にして、日本のみならず国際社会の有るべき姿が揺らいでいる。こんな時こそ、言葉を高く掲げよう。日本の憲法は暗闇の中に灯る一条の光となるに違いない──。それが小説に携わる者の夢想である。