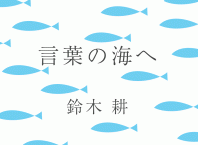今月のニュースの最大の論点は、6月12日からの安倍首相のイラン訪問だ。安倍首相の「外交好き」はいまに始まったことではなく、首相になってからの訪問国はすでに50か国を超え、日露首脳会談は二十数回に及ぶ。日米首脳会談も、回数の多さでは世界でもトップクラスになろうか。ところが、その成果となるとさっぱりで、ロシアとの北方領土問題の解決はいっこうに進まず、もっとも近い国であるはずの韓国との間は、最悪と言ってもいい状況になっている。
その中で、今回のイラン訪問は、両国からの日本に対する仲介の期待が大きく、安倍外交の初めての「外交らしい外交」だといっても過言ではないだろう。といっても、イランの日本に対する信頼感は安倍外交の成果ではない。1979年のイラン革命によって米国とイランとの関係が決定的に悪くなったとき、中東からの石油が止まったら大変だと考えた日本政府が「米国より中東寄り」の姿勢を取った成果が、40年ぶりに評価されたものだと言えようか。
日本の現職の首相がイランを訪問するのは、78年の福田赳夫氏以来41年ぶりで、イラン革命後は初めて。首相がイランの最高指導者と会見するのも初めてなのである。石油ショックのおかげで、米国一辺倒でなかった成果が40年ぶりに表われたという不思議な縁であり、外交関係においては何がプラスになるか分からないという実例の一つだろう。
ところが、またまた、ところが、である。安倍首相とイラン政府の高官が会談しているさなかに、ホルムズ海峡付近で日本のタンカーに対する攻撃があり、米国の高官がイラン政府の関与を示す映像を公表したが、イラン政府は攻撃を全面的に否定している。
国連のグテレス事務総長は「独立した団体による調査が必要だ」と述べ、第三者による調査の必要性を訴えた。折角の「安倍外交」が、何が何だか分からないような状況になりかかっている。
そのうえさらに、米国の無人機をイランが撃墜するという事件まで起こった。イランは「領空侵犯」を理由にしているが、米国はそれを否定している。あわや戦争かという危機は、トランプ大統領の「戦争はしたくない」のひと言で留まったが、もし本当に戦争がしたかったらどうなっていたか。安倍外交どころではない。
アジアでは中国の天安門事件から30年、国内に批判の声が渦巻く?
アジアでは、中国の学生らによる民主化運動を軍隊が鎮圧した天安門事件から30年。6月1日付けの朝日新聞と東京新聞は、中国政府がいまだに事件について「反革命暴乱」との評価を変えないことに対して、秘かに批判する声が国内に出ていることを示す記事を一面に大きく掲げた。
朝日新聞に掲載されたのは中国紙のカメラマンが撮影した事件当時の写真で、ずらりと並ぶ軍の車両の前で、軍に捕まった市民が1人ひざまずかされている姿が写っている。「写真を通じて多くの人に真相を知ってもらいたい」と本人から提供されたものだという。
東京新聞の記事は、毛沢東の秘書を務め、今年2月に101歳で死去した李鋭氏の日記に、民主化のデモを武力で鎮圧したことで、「(党は)永遠の罪人となり、汚名を長く後世に残すだろう」と記されているという内容だった。日記はサンフランシスコ近郊に住む李氏の娘(68)からスタンフォード大学に寄贈されたものだという。
2つの記事を並べて読むと、中国政府の姿勢を批判する声が国内に渦巻いているかのようにもみえるが、果たしてどうなのか。毛沢東の文化大革命に対して、すべて「四人組」のせいにして毛沢東の責任を問わなかった前例もあるだけに、一党独裁の中国にはまだまだ分かりにくいことが多いようだ。せめて天安門事件くらい「あれはやり過ぎだった」と中国政府が言ってくれたら、いいのだが…。
領土取り戻すのに「戦争も」という驚くべき発言!
北方領土・国後島へのビザなし訪問に参加していた日本維新の会の丸山穂高・衆院議員(35)が、「領土を取り戻すには戦争も」という驚くべき発言をしていたことが明るみに出た。
さすがに、日本維新の会も「除名処分」にしたが、そんなことで済ませていいはずはない。少なくとも衆議院議員の除名処分は当然の、腹の立つ発言だ。
戦後70余年。35歳の若さでは、戦争に対する反省は「遠い昔のこと」かもしれないが、「何があっても戦争はしない」ということを日本人としての最低限の資格として学ぶ時間はあったはずだ。
いや、そこまでいうと、「二度と戦争はしない」と誓ったはずの日本が、戦後一貫して憲法違反だとしてきた集団的自衛権の行使を認め、日本を再び「戦争のできる国」にしたのは誰か、ということになるのだろうが…。
香港の大規模デモ、「逃亡犯条例」を撤退に追い込む
海外がらみのニュースでは、もう一つ、香港の「逃亡犯条例」改正に反対する学生たちのデモがますます燃え上がり、行政長官も条例の審議延期を宣言した。しかし、廃案ではなかったことによってデモ隊はさらに膨れ上がり、香港政府も無期限延期と譲歩したが、それでも収まりそうもないところまできている。
香港は、「一国二制度」という条件付きで中国に返還された経緯があるが、今回の「逃亡犯条例」改正によって、香港の逃亡犯を中国に送り返して裁判を受けさせられるようになれば、「一国二制度」は有名無実になってしまう。香港の市民にとっても譲れないところなのだろう。
デモがどう収束するか予断は許されないが、中国の独裁体制がもう少しゆるんで、「香港寄り」に変わることがあったらいいな、という思いは、中国本土にもあるのではなかろうか。
警官襲撃は計画的、日本も新たな「銃規制」を考えないと
国内の事件に目を向けると、大阪府吹田市で6月16日、交番の巡査が襲われ、実弾5発入りの拳銃が奪われるという事件があった。3人勤務の交番に別の事件を通報して2人を出動させ、1人になった警官を包丁で襲ったもので、中学校時代の友人の住所・氏名を使った計画的な犯行だった。
奪った拳銃で何をしようとしていたのかは分からない。周辺の学校などはすべて休校とされ、警察が捜索していたところ8時間後に山中で逮捕できたからよかったが、この事件で、日本でも新たな「銃規制」の方法を考えないといけないことが浮かび上がったといえよう。
これまで米国で「銃の乱射事件」による大量殺人事件が起こるたびに、銃規制がない(できない)米国の後進性が問題にされてきたが、日本では厳しい銃規制があるので心配ないと言われてきた。
しかし銃規制はあっても、警官が持っている拳銃を計画的に奪おうという犯行が起こったのだから、それに対する対応策を考えないといけない。1人勤務の交番も多いし、拳銃を持っているからという理由で、警官の命まで危険にさらされることになってはならない。この際、警察関係者による慎重かつ多角的な取り組みを期待したい。
国会は「多数派」が何でもできるのか、麻生氏らの問責ならず
立憲民主、国民民主、共産など野党は6月20日、麻生財務相兼金融相の問責決議案と金子原二郎参院予算委員長(自民)の解任決議案を共同提出したが、多数を持つ与党側に否決された。
麻生氏の問責決議案は、老後に2000万円の資金が必要とした金融審議会の報告書の受け取りを麻生氏が拒否したことを理由にして、「自らが大臣として諮問したにもかかわらず、気に入らないから受け取らないという前代未聞の暴挙に出た」と批判している。
また学校法人「森友学園」をめぐる財務省の決裁文書改ざん問題なども列挙して、「隠蔽体質の根深さを如実に示すとして閣僚の辞任も求めた。
金子氏の解任決議案では、野党側が4月から要求している参院予算委員会の開催に2か月以上も応じていないことを理由とし「看過できない深刻な事態だ」と主張している。
日本維新の会は、金子氏の解任案の提出には加わったが、麻生氏の問責案には加わらなかった。
国会では「多数」がものを言うのはいつものことだが、それにしても最近の様相は、あまりにもひどすぎないか。

ハンセン病の差別、日本国家の最大の恥
ハンセン病患者の強制隔離政策で、差別の苦しみを味わったのは患者だけではなかった。家族も同じ、いや患者よりむしろ家族のほうが苦しみは大きかったかもしれない。患者の家族であることさえ語れなかったのだから、その苦しさは、たとえる言葉もなかっただろう。そうした家族らが国に損害賠償を求めた訴訟の判決が6月28日に熊本地裁である。
ハンセン病の患者に対する日本社会の差別意識のすごさは、言葉が見つからないほどひどいものだった。それを教えてくれたのは、私の朝日新聞社会部の先輩記者、藤田真一さんだった。
藤田記者との付き合いは、1968年に連載『NHK』の取材班として一緒に取材したときからだ。疋田桂一郎記者をキャップとする、いわゆる「疋田飯場」で同じ仕事をしていれば、人柄も考え方もよく分かり、藤田記者は私の最も尊敬する先輩記者の一人となった。
その藤田記者が、のちに編集委員としてひとりで書いた連載記事に「植物人間の記録」「お産革命」「これからの生と死」「盲(もう)と目あきの社会」というのがある。そのテーマを見ていただければ、それだけでも分かるように、藤田記者の関心は人間そのもの、とくに差別にさらされている人たちの人権にあった。
その藤田記者が定年後、フリーのジャーナリストとして取り組んだのがハンセン病患者への差別のすさまじさを告発する仕事だった。日本はいわゆる「らい予防法」によって患者を強制的に収容所に隔離する政策を100年近く続けてきた国で、強制収容されると本名も名乗れず、偽名を名乗らされるのが常だった。家族からハンセン病患者が出たとなると、縁談も何もかもダメになるからだ。
「らい予防法」が廃止されたのは1996年だが、その1年ほど前から藤田記者は、国立療養所多磨全生園に隔離されていた森元美代治・美恵子夫妻が本名を名乗って(カミング・アウト)、らい予防法によって奪われた人生を社会に告発したいとしていた仕事にかかわっていた。そして、「らい予防法」の廃止と同時に、森本夫妻の証言を収めた『証言・日本人の過ち』(人間と歴史社)が出版された。
私はそれを読んで、ハンセン病に対する日本社会の差別意識のすさまじさと、それを告発する藤田記者の精神力の強さに、深く感動したのである。
ハンセン病の患者だけでなく、国はその家族にまで損害賠償を認めるかどうか。すでに亡くなった藤田記者に代わって、28日の「家族訴訟」判決に注目しよう。