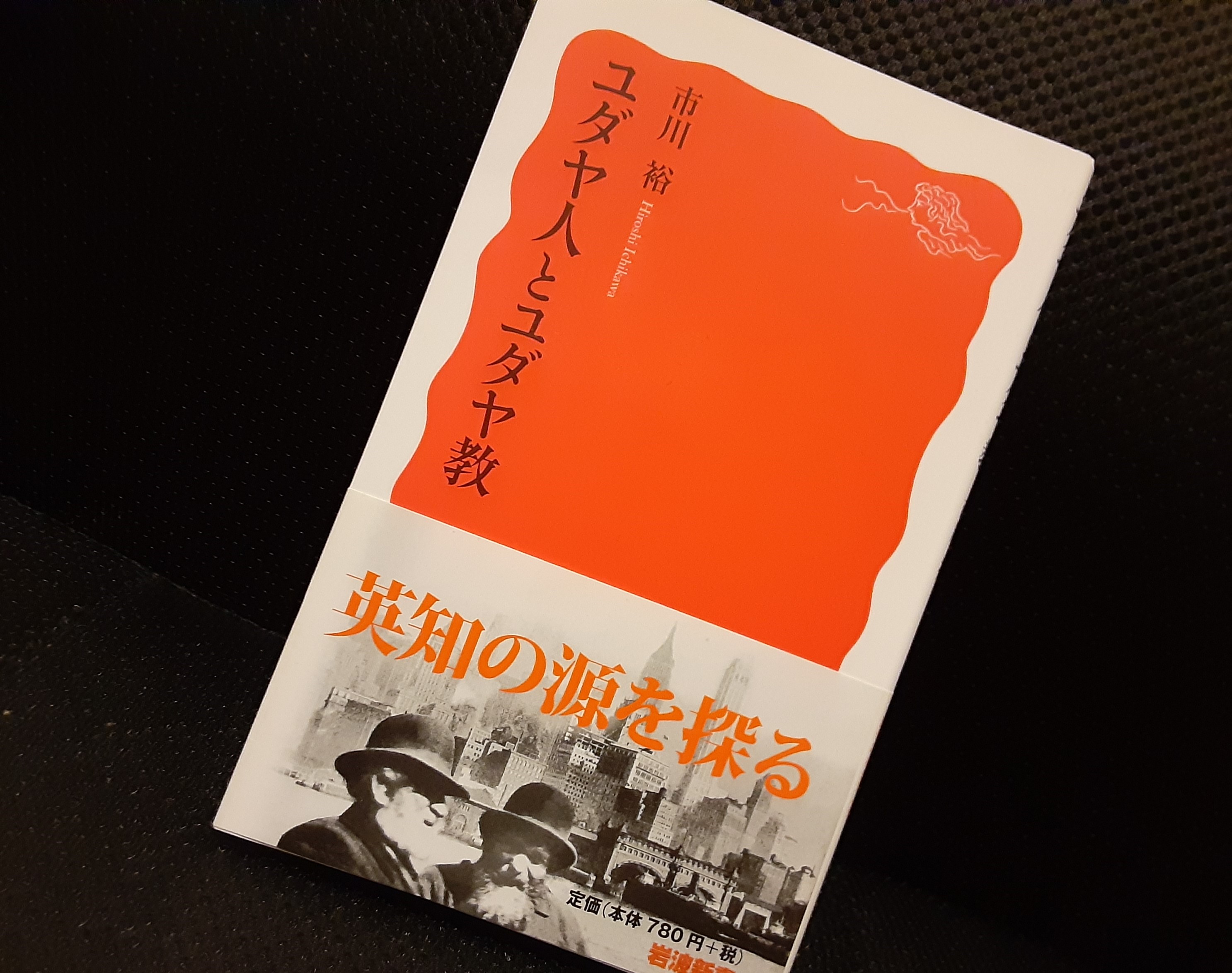国家は頭の中にある
国家の誕生時から戦火を生き延びていくことを運命づけられたイスラエルは、中東最強の軍事国家である。と同時に、常に周辺諸国との緊張関係のなかにあるがゆえに、高度な軍事技術を転用した先進的なテクノロジーを提供する企業を数多く輩出するイノベーション大国でもある。『イスラエルがすごい マネーを呼ぶイノベーション大国』(新潮新書)は、イスラエルのハイファ大学国家安全保障センターのダン・シュフタン教授の言葉を紹介している。
「戦争が起きても、我々のビジネスにはさほど支障を来さない。その理由は、我々のビジネスモデルは、頭の中にあるからだ。工場をミサイルで破壊することはできるが、頭の中にある知恵とイノベーション精神を破壊することはできない。もしもイスラエルでビジネスを続けられなくなったら、他の場所へ移って続ければいい。我々は戦争によって被害を受けても、2日後には忘れて、前に進んでいく」
同書によれば、人口わずか900万人の国でイノベーティブな産業を発展させていくための基本は懐疑の精神だ。自らの頭で考えること。それは軍隊にも及んでいるという。シュフタン教授によれば、イスラエル国防軍の戦闘機のパイロットがある目標を攻撃するよう命令されても、ターゲットに近づいて、「この攻撃を実施するのは間違っている」という結論に達した場合、攻撃命令を実行する必要はないという。その代わり、パイロットは基地に帰投してから、なぜ爆撃に加わらなかったかを明確に説明する義務が課せられる。上官も誤った判断をする可能性があるので、命令といえども盲従せず、常に自分の頭で判断することが求められるのである。イスラエル国防軍では、「一兵卒でも将軍と議論を戦わせるのは当たり前」なのである。
国土を失っても、頭の中までは奪われないという「国家観」をもっている限り、自分たちは生き残っていける。そこにはハード(軍備)だけではなく、ソフト(情報)によって安全保障を確立するという発想があり、そのルーツは「ミシュナ」というユダヤ教の口伝律法集(トーラー)にあるのではないか。
宗教的規範のみならず、社会的法規範をも包括したミシュナは、ユダヤ人が自分たちの社会が消滅の危機に瀕したとき、社会を存続させるために、生活のすべてを神の法によって統治する方法を模索した結果、生まれたものである。西暦200年頃に編まれ、全6巻63編からなるヘブライ語で書かれた法規範には、礼拝とイスラエルの地の農産物奉納を定めたもの(第一巻)、祭日の規定を集めたもの(第二巻)、神殿供犠の規則集(第五巻)、穢れとその清め方を定めたもの(第六巻)など宗教に係る内容のほか、親族を形成して子孫を残すことや、結婚と離婚に関する家族法を定めたもの(第三巻)、ユダヤ人同士の日常生活に関するルールを定めたもの(第四巻)がある。とくに第四巻には、刑事罰と法廷における裁判の規定、土地や家屋の賃借権をめぐる細かな事例に対する法規定も並んでおり、『ユダヤ人とユダヤ教』(岩波新書)によれば、ミシュナは「ラビたち律法学者によって営まれる『持ち運びのできる国家』に他なら」ず、「世界のどこにいようとも、ミシュナさえあればユダヤ社会は維持できる」ものなのである。
「国家は頭の中にある」と「持ち運びのできる国家」は共鳴する。
ロシア系、ウクライナ系移民のいる国として
映画『声優夫婦の甘くない生活』は、ソ連解体直前にイスラエルに移住した初老のユダヤ系ロシア人、声優夫婦の物語である。ソ連で名の通った2人はイスラエルで声優の仕事を探すも、かつて携わった往年の名画のロシア語吹き替えはなく、妻はテレフォンセックスで若い女性に扮したことが当たって指名が相次ぎ、夫は映画館で密かにビデオ撮影する海賊版の制作を手伝うはめになる。
おかしくも切ない物語だが、夫婦がイスラエルで声優を目指したのは、それだけロシア語系住民が多いからだ。とりわけロシア、ウクライナからのユダヤ系住民の移住が増え、人口の10%以上に当たる約100万人ともいわれている。
イスラエルの副首相・ナフタリ・ベネットは、ロシアがウクライナを侵攻した2022年2月当時は首相を務めており、それ以降、両国の停戦交渉の仲介役を果たしてきた。ロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領ともコンタクトがとれる稀有な政治家である。ベネットは今年の2月、両国が停戦交渉を進めたいにもかかわらず、西側諸国――とりわけ米国、英国――が交渉をボイコットしていると発言している。
西側ははたしてゼレンスキー大統領が主張する、クリミア半島をロシアから奪回するまで軍事援助を続けるのか。一方、プーチン大統領は領土の拡張という、ナチス・ドイツの敗戦の原因となった「レーベンスラウム」(生存圏)の考え方を捨てられないのか。
ドイツの歴史家・セバスチャン・ハフナーは『ヒトラーとは何か』(草思社文庫)のなかで、18世紀半ばから19世紀にかけての産業革命以来、「民族の繁栄と権力の度合いはもはや所有する土地の大きさではなく、科学技術のレベルによって決まるようになっていたのである。科学技術にとって生存圏の大小など関係なかった」と書いている。ハフナーによれば、1500年前にヨーロッパで民族が定住して以降、戦争が起こり、講和が結ばれ、領土の変更がなされたりしても、そこに住む人々は変わらなかった。支配者が代わっても、住民は自分たちの場所にとどまり続けた。それをヒトラーが変えた。レーベンスラウム(生存圏)を獲得し、そこに住む人々を押し出し、自分たちの民族を住まわせようとしたのである。ユダヤ人に対しては抹殺を試みた。そしてそれは失敗した。
「科学技術や産業の発展という視点からすれば、生存圏が拡大するというのは、ただ人口密度の低い土地がひろがるだけのことであり、これはまさにハンディキャップが増えることを意味する。ソ連などはそのことでたいへん苦労している。天然資源は豊かでも、広大で人口密度の低いシベリアなど、いくらがんばっても開発できず、いつまでたっても発展はおぼつかない」
ウクライナはシベリアではない。しかし、現在のロシアの姿勢はかつてシベリアを征服していったときの精神と変わらないのではないか。
イスラエルにとって米国は最も重要な同盟国であるが、対米一辺倒のような外交は行わない。国の存続に関わるからだ。イスラエルにとって、ロシア、ウクライナのどちらか一方に肩入れることは、自国の生存戦略としての選択肢としてありえないのである。
「ホロコーストをめぐって 1」で取り上げた『ダビデの星を見つめて 体験的ユダヤ・ネットワーク論』から再び引用しよう。著者の寺島実郎は、自身が三井物産社員として1987年にニューヨークに着任後、知己を得た事業家であり発明家でもあったD・スペクター氏についてこう評している。「まるで無から有を生ずるように、自分の知恵と努力で付加価値を生み出していく人物こそが尊敬されるべきだ、という考え方に徹している。逆に、親譲りの財産や親の影響力を基盤に安定を享受しているだけの人物を心の底から軽蔑している」
ぼくはここにきて、日本とイスラエルの生存戦略の違い、いや日本における国際社会における生存戦略の欠如を痛感せざるをえなくなるのである。個の強さが、ひいては国の安全保障に資するという考え方をぼくたちは覚えていた方がいいだろう。
(「ホロコーストをめぐって」 了)
(参考書籍)
熊谷徹著『イスラエルがすごい マネーを呼ぶイノベーション大国』新潮選書
市川裕著『ユダヤ人とユダヤ教』岩波新書
セバスチャン・ハフナー著・瀬野文教訳『ヒトラーとは何か』草思社文庫
寺島実郎著『ダビデの星を見つめて 体験的ユダヤ・ネットワーク論』NHK出版
(参考映画)
エフゲニー・ルーマン監督『声優夫婦の甘くない生活』2019年 イスラエル
ユダヤ人の国家観を知る上で入門書となる本である